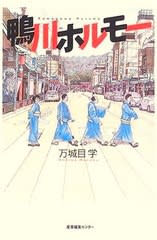論文というと時節柄卒論や修論を連想されると思いますが,まぁ 似たような話題です.
理工学では研究成果をその分野の専門雑誌(論文誌)に発表することも重要.発表するには,まず論文誌に論文を送る.雑誌側では専門家(レフェリーという)に論文を読んでもらって雑誌掲載の可否を判断してもらう.可と判断されれば論文が日の目を見る.
というわけで私が書いた論文が日の目を見ることになった.
論文を送る側では,上の手順で,まずどの論文誌に論文を出すかが問題.じつはこの論文はまずアメリカの論文誌に送って掲載否とされた.アメリカの論文誌に送ると意地悪されるというのは前から聞いていたが,その通りだった.日本の論文誌JJAPに出したら可であった.
この論文の内容は,かくかくのビームを作れば,これこれの効果があると言うもの.アメリカのレフェリーの意見はまず,「これこれの効果」はかってのソ連の論文で否定されているということだった.ソ連流にちゃんと計算してもそんなことはないと反論したら,こんどは「かくかくのビーム」の作り方を示せという.そういうビームの作り方を書いた論文を2-3挙げたら,もっと詳しく書けという.詳しく書いて,現状ではこれこれの困難があると説明を加えたら,これを逆手にとられて,やっぱり出来ないじゃないか,この論文は机上の空論だとのご宣託.これで半年ほどを浪費してしまった.
なぜ初めから日本の論文誌に送らなかったの,と言われそうだ.論文誌の善し悪しの一面はimpact parameterとして定量化されていて,日本の論文誌のfactorは欧米誌ほど良くない.
でももっと大きな個人的な理由は,論文に自信がなかったこと.
とうに退官・退職された大先生が学会等で頓珍漢なことを発言なさるのを目にすることがある.
この場合も日本の論文誌に送ると,レフェリーには多分年下の知人で,「あの人も本気でこんな阿呆らしいことを考えているのか,脳軟化症じゃないか」などと思われたらどうしよう...なんて考えてしまった (アメリカの論文誌でもアメリカの知人がレフェリーする可能性はあるが,もう会う機会はありそうもないから,いいのである).
でも日本人レフェリーのコメントを読んだら好意的だったので安心した,
理工学では研究成果をその分野の専門雑誌(論文誌)に発表することも重要.発表するには,まず論文誌に論文を送る.雑誌側では専門家(レフェリーという)に論文を読んでもらって雑誌掲載の可否を判断してもらう.可と判断されれば論文が日の目を見る.
というわけで私が書いた論文が日の目を見ることになった.
論文を送る側では,上の手順で,まずどの論文誌に論文を出すかが問題.じつはこの論文はまずアメリカの論文誌に送って掲載否とされた.アメリカの論文誌に送ると意地悪されるというのは前から聞いていたが,その通りだった.日本の論文誌JJAPに出したら可であった.
この論文の内容は,かくかくのビームを作れば,これこれの効果があると言うもの.アメリカのレフェリーの意見はまず,「これこれの効果」はかってのソ連の論文で否定されているということだった.ソ連流にちゃんと計算してもそんなことはないと反論したら,こんどは「かくかくのビーム」の作り方を示せという.そういうビームの作り方を書いた論文を2-3挙げたら,もっと詳しく書けという.詳しく書いて,現状ではこれこれの困難があると説明を加えたら,これを逆手にとられて,やっぱり出来ないじゃないか,この論文は机上の空論だとのご宣託.これで半年ほどを浪費してしまった.
なぜ初めから日本の論文誌に送らなかったの,と言われそうだ.論文誌の善し悪しの一面はimpact parameterとして定量化されていて,日本の論文誌のfactorは欧米誌ほど良くない.
でももっと大きな個人的な理由は,論文に自信がなかったこと.
とうに退官・退職された大先生が学会等で頓珍漢なことを発言なさるのを目にすることがある.
この場合も日本の論文誌に送ると,レフェリーには多分年下の知人で,「あの人も本気でこんな阿呆らしいことを考えているのか,脳軟化症じゃないか」などと思われたらどうしよう...なんて考えてしまった (アメリカの論文誌でもアメリカの知人がレフェリーする可能性はあるが,もう会う機会はありそうもないから,いいのである).
でも日本人レフェリーのコメントを読んだら好意的だったので安心した,