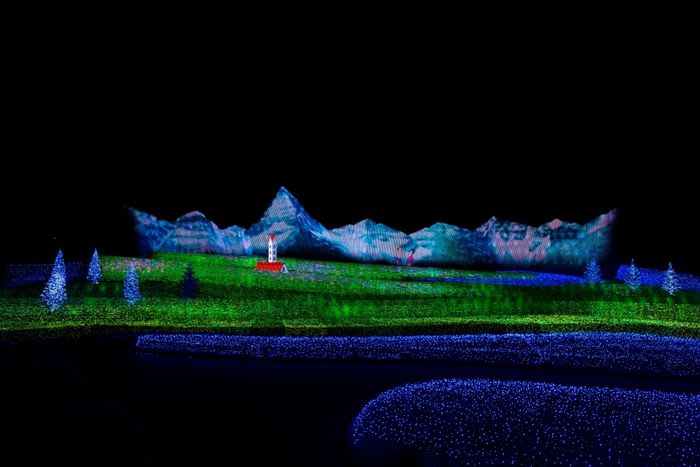2015年12月20日(日)晴 8.1℃~2.2℃
「エルニーニョ現象の影響」
昨年は12月17日の夜から雪が降り出し、18日には大雪となり毎日雪片付けだった。
気象庁の発表では、今年の冬は暖冬傾向だという。エルニーニョ現象が起きた時の冬の気候は、東日本や西日本で日照時間が少なくなり、降水量が多めになる傾向があるという。
降水量には雨だけでなく雪も含まれる。例えば、昨年二月、東北、関東地方を襲った豪雪は、冬型の気圧配置が緩んだ時に現れやすい南岸低気圧の影響を受けた。
あの時の豪雪で、雪に慣れていない地域はパニックになった。交通障害、電線への着雪による停電、ビニールハウスや車庫の倒壊、雪かきでのけがなど、さまざまな被害が報告された。

今年は豪雪かと予想して例年より早く樹木の雪囲い、鉢物を小屋へ、白菜、大根、ネギなど冬野菜の確保等をした。今までは予想がはずれて降雪がなく凌ぎやすい。それでも、暖冬になると南岸低気圧の発生が指摘されているので安心はできない。
小屋の中に取り込んだ植物は、まだまだ休眠状態にならず花を咲かせている。正月に飾る盆栽の梅の蕾が赤く膨らんできた。ヒーターの温度を低めにして開花時期を調整し、元旦に開花させたい。
「エルニーニョ現象の影響」
昨年は12月17日の夜から雪が降り出し、18日には大雪となり毎日雪片付けだった。
気象庁の発表では、今年の冬は暖冬傾向だという。エルニーニョ現象が起きた時の冬の気候は、東日本や西日本で日照時間が少なくなり、降水量が多めになる傾向があるという。
降水量には雨だけでなく雪も含まれる。例えば、昨年二月、東北、関東地方を襲った豪雪は、冬型の気圧配置が緩んだ時に現れやすい南岸低気圧の影響を受けた。
あの時の豪雪で、雪に慣れていない地域はパニックになった。交通障害、電線への着雪による停電、ビニールハウスや車庫の倒壊、雪かきでのけがなど、さまざまな被害が報告された。

今年は豪雪かと予想して例年より早く樹木の雪囲い、鉢物を小屋へ、白菜、大根、ネギなど冬野菜の確保等をした。今までは予想がはずれて降雪がなく凌ぎやすい。それでも、暖冬になると南岸低気圧の発生が指摘されているので安心はできない。
小屋の中に取り込んだ植物は、まだまだ休眠状態にならず花を咲かせている。正月に飾る盆栽の梅の蕾が赤く膨らんできた。ヒーターの温度を低めにして開花時期を調整し、元旦に開花させたい。