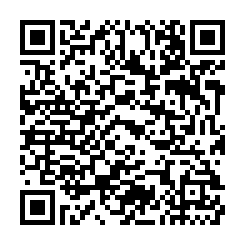本日も易きに流れてマクドで2時間宝島読書。
目に付くのは雑学おじいさん植草甚一のエッセイや、ハワイアン・カウボーイ片岡義男の小説だ。
どちらも日本的な純文学や私小説でないところ、例えば口語体や乾いた文体が当時の私の共感を呼んだ。
当時で言うところのフィーリングが合ったのだ。
両人ともアメリカに対する憧れはハンパじゃない。
いうならば、ある意味、宝島のサブカル的なカラーやテイストを決定付けるふたりだ。
当時のサブカルチャーは、アメリカ的なものとほぼイコールだった。
当時大学生だった私は、彼らの著作を片っ端から読んだものだ。
アメリカを知るためではなく、アメリカ的なものを知るためだ。
大学では近代アメリカ文学の講義を受けていて、フィッツジェラルドやヘミングウェイ、フォークナーやスタインベックなどの短編を読んでいた。
宝島と大学の講義がうまくシンクロして、そこからアメリカン・ニュー・シネマやフォークロックへと視野は広がっていった。
とにかくアメリカ的で明るく乾いた、ペンキやメッキでコーティングされた、幻想的現実に憧れたものだ。
その匂いをいち早く嗅ぎつけて、日本的なものに変換し、小説という形にしたのが村上春樹だ。
その「風の歌を聴け」での登場は4年の後だ。
その頃私はすでに社会人となり、宝島からは隔絶された生活空間にいた。
目に付くのは雑学おじいさん植草甚一のエッセイや、ハワイアン・カウボーイ片岡義男の小説だ。
どちらも日本的な純文学や私小説でないところ、例えば口語体や乾いた文体が当時の私の共感を呼んだ。
当時で言うところのフィーリングが合ったのだ。
両人ともアメリカに対する憧れはハンパじゃない。
いうならば、ある意味、宝島のサブカル的なカラーやテイストを決定付けるふたりだ。
当時のサブカルチャーは、アメリカ的なものとほぼイコールだった。
当時大学生だった私は、彼らの著作を片っ端から読んだものだ。
アメリカを知るためではなく、アメリカ的なものを知るためだ。
大学では近代アメリカ文学の講義を受けていて、フィッツジェラルドやヘミングウェイ、フォークナーやスタインベックなどの短編を読んでいた。
宝島と大学の講義がうまくシンクロして、そこからアメリカン・ニュー・シネマやフォークロックへと視野は広がっていった。
とにかくアメリカ的で明るく乾いた、ペンキやメッキでコーティングされた、幻想的現実に憧れたものだ。
その匂いをいち早く嗅ぎつけて、日本的なものに変換し、小説という形にしたのが村上春樹だ。
その「風の歌を聴け」での登場は4年の後だ。
その頃私はすでに社会人となり、宝島からは隔絶された生活空間にいた。