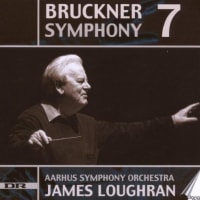山田和樹が指揮する日本フィルの定期。1曲目は貴志康一(1909‐1937)のヴァイオリン協奏曲。ヴァイオリン独奏は日本フィルのソロ・コンサートマスター田野倉雅秋。田野倉は2019年9月に間宮芳生(1929‐)のヴァイオリン協奏曲を演奏した(バックは今回と同じく山田和樹指揮日本フィル)。そのときの熱演を記憶しているのだが、それとくらべると、今回はすっきりスマートに演奏していたように思う(日本フィルも同様)。それはそれでよいのだが、今回は音の細さを感じた。前回は感じなかったので、今回の演奏スタイルのせいか。
ところでこの曲は、小味渕彦之氏のプログラム・ノートによれば、全3楽章のうちの第1楽章が1934年3月29日にベルリンで、20世紀の音楽史にその名を残すゲオルク・クーレンカンプの独奏、貴志康一自身の指揮、映画会社ウーファのオーケストラで初演されたという(全曲の初演は1944年1月17日に大阪で、辻久子の独奏、尾高尚忠指揮大阪放送管弦楽団によって行われた)。
当時クーレンカンプに初演をお願いすることは、20代の若者の貴志康一にはたいへんな出来事ではなかったろうか。その気負いのためか、第1楽章に横溢する和風のテイストは、わたしにはクーレンカンプを意識した(あるいはベルリンの聴衆を意識した)もののように聴こえた。
その意識は仕方がないし、むしろ当然だと思うが、でも、いま聴くと、こういってはなんだが、そのテイストはいかにもステレオタイプで、外国人が好むような(ある意味で)珍妙なところがある。わたしは居心地の悪さを感じた。もちろんそれを否定するのではなく、歴史の一断面として捉えるべきだが。
2曲目はウォルトン(1902‐1983)の交響曲第1番(1935)。尾高忠明がレパートリーにしているので、尾高の指揮で何度か聴いたことがある。その記憶とくらべると、山田和樹の指揮は目の覚めるような極彩色に彩られ、まったく別の曲のように聴こえた。しかも振幅が大きく、音楽の高まりと沈潜との差は、高層ビルほどの落差があった。加えて、とくに第1楽章と第2楽章では破格のエネルギーがフル回転して、恐ろしいほどだった。
だが、第2楽章まででエネルギーを使い切ったのか、第3楽章はなんとか持ちこたえたが、第4楽章では集中力にゆるみが出た。そして最後の2組のティンパニが連打する箇所では、八方破れの爆演と(日本フィルの定期会員であるわたしも)思わざるを得ない演奏になった。日本フィルの未来を託すのは山田和樹しかいない(そうなってほしい)と思うがゆえに(※)、あえていうのだが、最後の最後まで緊張を途切れさせずに、アンサンブルをきっちり保ってほしい。
(2022.9.3.サントリーホール)
(※)山田和樹は8月末で日本フィルの正指揮者を退任したらしい。だが、いまはともかく、いつかは渡邉暁雄→小林研一郎と続く日本フィルの支柱を引き継いでほしい。(2022.9.6.追記)
ところでこの曲は、小味渕彦之氏のプログラム・ノートによれば、全3楽章のうちの第1楽章が1934年3月29日にベルリンで、20世紀の音楽史にその名を残すゲオルク・クーレンカンプの独奏、貴志康一自身の指揮、映画会社ウーファのオーケストラで初演されたという(全曲の初演は1944年1月17日に大阪で、辻久子の独奏、尾高尚忠指揮大阪放送管弦楽団によって行われた)。
当時クーレンカンプに初演をお願いすることは、20代の若者の貴志康一にはたいへんな出来事ではなかったろうか。その気負いのためか、第1楽章に横溢する和風のテイストは、わたしにはクーレンカンプを意識した(あるいはベルリンの聴衆を意識した)もののように聴こえた。
その意識は仕方がないし、むしろ当然だと思うが、でも、いま聴くと、こういってはなんだが、そのテイストはいかにもステレオタイプで、外国人が好むような(ある意味で)珍妙なところがある。わたしは居心地の悪さを感じた。もちろんそれを否定するのではなく、歴史の一断面として捉えるべきだが。
2曲目はウォルトン(1902‐1983)の交響曲第1番(1935)。尾高忠明がレパートリーにしているので、尾高の指揮で何度か聴いたことがある。その記憶とくらべると、山田和樹の指揮は目の覚めるような極彩色に彩られ、まったく別の曲のように聴こえた。しかも振幅が大きく、音楽の高まりと沈潜との差は、高層ビルほどの落差があった。加えて、とくに第1楽章と第2楽章では破格のエネルギーがフル回転して、恐ろしいほどだった。
だが、第2楽章まででエネルギーを使い切ったのか、第3楽章はなんとか持ちこたえたが、第4楽章では集中力にゆるみが出た。そして最後の2組のティンパニが連打する箇所では、八方破れの爆演と(日本フィルの定期会員であるわたしも)思わざるを得ない演奏になった。日本フィルの未来を託すのは山田和樹しかいない(そうなってほしい)と思うがゆえに(※)、あえていうのだが、最後の最後まで緊張を途切れさせずに、アンサンブルをきっちり保ってほしい。
(2022.9.3.サントリーホール)
(※)山田和樹は8月末で日本フィルの正指揮者を退任したらしい。だが、いまはともかく、いつかは渡邉暁雄→小林研一郎と続く日本フィルの支柱を引き継いでほしい。(2022.9.6.追記)