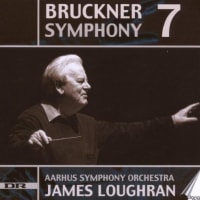サントリーホール サマーフェスティバル2022が始まった。今年のプロデューサーはウィーンの現代音楽アンサンブル「クラングフォルム・ウィーン」だ。第一夜は比較的大きな編成の曲を集めたプログラム。指揮は現代音楽に強いエミリオ・ポマリコ。
1曲目はヨハネス・マリア・シュタウト(1974‐)の「革命よ、聴くんだ(ほら、仲間だろう)」(2021)。シュタウトの作品は、2016年10月にカンブルラン指揮の読響でヴァイオリン協奏曲「オスカー」(ヴァイオリン独奏は五嶋みどり)を聴いたことがあり、おもしろかった記憶があるので、今度も楽しみにしていたが、それほどでもなかった。中間部でちょっとしたパフォーマンスがあり、その部分で音楽が陰りをみせたことが印象に残る。
2曲目はミレラ・イヴィチェヴィチ(1980‐)の「サブソニカリー・ユアーズ」(2021)。未知の作曲家だ。長い持続音のうえに短音が次々に生起する。その音の生きの良さに惹かれる。全体的に明るいテクスチュアだが、後半になって変化が生じた。
3曲目は塚本瑛子(1986‐)の「輪策赤紅、車輪」(2017)。これも未知の作曲家だ。ベルリン在住とのこと。題名はドイツ語でrad rat rot red, raederとなり、韻を踏んでいる。無音の間(ま)が頻出し、断片的な音楽が続く。音が鮮明だ。2曲目のイヴィチェヴィチと似たところのある作りだが、二人それぞれ自分の音をもっている。
4曲目は武満徹(1930‐96)の「トゥリー・ライン」(1988)。この流れのなかで(とは、いまを生きる作曲家たちのなかで、という意味だが)、武満徹がどう聴こえるか、一抹の不安があったが、いざ演奏が始まると、なるほどこれはドビュッシーの直系だと、それはそれなりに受け止めることができた。音の輪郭が明瞭だったことが幸いした。
5曲目はゲオルク・フリードリヒ・ハース(1953‐)の「ああ、たとえ私が叫ぼうとも、誰が聞いてくれよう…」(1999)。ハースは2017年の当フェスティバルのテーマ作曲家で、ヴァイオリン協奏曲第2番が世界初演された。わたしはいまでもその曲の第8部「純正音程」の美しさが忘れられない。今回の曲では、何者かの呼吸のような不穏な音型が繰り返され、そこに金属系の打楽器の微細な音が鳴り続ける。息をひそめるような緊張感から解放されない音楽だ。
全般を通して、クラングフォルム・ウィーンの演奏は、緻密でしっとりまとまったアンサンブルを聴かせた。わたしは2015年8月にザルツブルク音楽祭でブーレーズの「ル・マルトー・サン・メートル」などを聴いたが(指揮はカンブルラン)、今回はそのときのキャラが立った演奏とはだいぶ印象が異なる。日本人演奏家がかなり参加していたことも一因か。
(2022.8.22.サントリーホール)
1曲目はヨハネス・マリア・シュタウト(1974‐)の「革命よ、聴くんだ(ほら、仲間だろう)」(2021)。シュタウトの作品は、2016年10月にカンブルラン指揮の読響でヴァイオリン協奏曲「オスカー」(ヴァイオリン独奏は五嶋みどり)を聴いたことがあり、おもしろかった記憶があるので、今度も楽しみにしていたが、それほどでもなかった。中間部でちょっとしたパフォーマンスがあり、その部分で音楽が陰りをみせたことが印象に残る。
2曲目はミレラ・イヴィチェヴィチ(1980‐)の「サブソニカリー・ユアーズ」(2021)。未知の作曲家だ。長い持続音のうえに短音が次々に生起する。その音の生きの良さに惹かれる。全体的に明るいテクスチュアだが、後半になって変化が生じた。
3曲目は塚本瑛子(1986‐)の「輪策赤紅、車輪」(2017)。これも未知の作曲家だ。ベルリン在住とのこと。題名はドイツ語でrad rat rot red, raederとなり、韻を踏んでいる。無音の間(ま)が頻出し、断片的な音楽が続く。音が鮮明だ。2曲目のイヴィチェヴィチと似たところのある作りだが、二人それぞれ自分の音をもっている。
4曲目は武満徹(1930‐96)の「トゥリー・ライン」(1988)。この流れのなかで(とは、いまを生きる作曲家たちのなかで、という意味だが)、武満徹がどう聴こえるか、一抹の不安があったが、いざ演奏が始まると、なるほどこれはドビュッシーの直系だと、それはそれなりに受け止めることができた。音の輪郭が明瞭だったことが幸いした。
5曲目はゲオルク・フリードリヒ・ハース(1953‐)の「ああ、たとえ私が叫ぼうとも、誰が聞いてくれよう…」(1999)。ハースは2017年の当フェスティバルのテーマ作曲家で、ヴァイオリン協奏曲第2番が世界初演された。わたしはいまでもその曲の第8部「純正音程」の美しさが忘れられない。今回の曲では、何者かの呼吸のような不穏な音型が繰り返され、そこに金属系の打楽器の微細な音が鳴り続ける。息をひそめるような緊張感から解放されない音楽だ。
全般を通して、クラングフォルム・ウィーンの演奏は、緻密でしっとりまとまったアンサンブルを聴かせた。わたしは2015年8月にザルツブルク音楽祭でブーレーズの「ル・マルトー・サン・メートル」などを聴いたが(指揮はカンブルラン)、今回はそのときのキャラが立った演奏とはだいぶ印象が異なる。日本人演奏家がかなり参加していたことも一因か。
(2022.8.22.サントリーホール)