夕暮れの霞の山吹恋をする 乙女の髪にガルフ・ナポリは海の風
■
御輿の担ぎ手捜しで一日忙殺。どの町でもそうだろうが、時
代とともに屈強な若者が少なくなり平均年齢が上昇加速する。
上限年齢の50歳を取っ払い、定員数に1.5~2倍に増や
し短い距離で頻繁に交代するか、巡行距離を短くするしかな
いが、御輿ひとつも上がらぬでは末が心配とは「この俺も歳
を食ったかなぁ」。男性平均年齢約76(女性は83)歳。
山振の立ちよそひたる山清水 くみに行かめど道の知らなく 高市皇子
そんな中、元の職場の仲間とひととき花見を楽しむ。話の内
容それは、ひ・み・つ。少し気になることがある。それは自
分が去った職場に‘面白しろさ’がなくなったのではという
思いを伝えた。要するに‘梁山泊’のような人物がいなくな
ったという老婆心に尽きるが、そのことと企業の衰退とイコ
ールに必ずしも繋がるわけではないが大いにありうることだ
としみじみと満開の桜に重ね合わせていた。‘♪〽 人生は
短い’(ビートルズ“恋を抱きしめて”)。なんとかせんと
いかん(東国原英夫)か。
■ Red Clif Ⅱ
Red Clif Ⅱ
映画『レッド・クリフ パート2』は最高傑作だ。それ以上
書くことも、屋上屋を重ねる様で、出来ればジョン・ウー監
督には『五丈原の戦い』までも撮ってもらいたいものだと付
け加えておこう。 五丈原の戦い
五丈原の戦い
映画では登場のなかった龐統。連環の計で火攻めの成功を契
すため拝風台で東南の風を起こそうとする諸葛孔明もなかっ
た。こういった常道をはずし、主体的に舟を連結する慢心曹
操。風向きの反転を待つ諸葛孔明。周瑜の策謀による蔡瑁、
張允の処刑。総攻撃を引き留める小喬。スリルとサスペンス
溢れる展開。『借東風』。風見鶏とは日和見主義と蔑まれる
が、人智の限りを尽くした研ぎ澄まされた機動力でもある。
■ Kerria japonica
Kerria japonica
山吹の名は、山で風に揺れている姿を表現した「山振(やまぶ
り)」に由来するといわれるバラ科ヤマブキ属の落葉低木。黄
色の花をつけ、春の季語。低山の明るい林の木陰などに群生
し樹木ではあるが、茎は細く柔らかい。背丈は1~2m。先
端はやや傾き、往々にして山腹では麓側に垂れる。地下に茎
を横に伸ばし、群生する。葉は鋸歯がはっきりしていて薄い。
晩春に明るい黄色の花を多数つけ、多数の雄蕊と5~8個の離
生心皮がある。心皮は熟して分果になる。北海道から九州ま
で分布し、国外では中国に産する。古くから親しまれた花で、
庭に栽培される。花は一重のものと八重のものがあり、特に
八重咲きが好まれよく栽培される。一重のものは花弁は5枚。
金貨の代名詞「ヤマブキ」。花言葉は「待ちかねる」。
かくしあらば何か植ゑけむ山吹のやむ時もなく恋ふらく思へば 読人不知
■
『借東風』とは臨機応変でもある。南仏プロバンス旅行は空
中分解。保険で掛けていたオプショナルの南伊カプリ島旅行。
介護者を抱えて長期旅行は難しい。まして、先延ばしても良
い条件はこない。ならば思い立ったら吉日と定める。行き先
も見えぬ息詰まるかのような日常から愛する者とともに離れ
たい。朝鮮半島の真西に位置するナポリ湾。東風に髪をなび
かせる少女時代の魂。そんな幻想的で難解な歌を詠った。
カプリ島 Isola di Capri
Isola di Capri
ポンペイ Pompei
Pompei
ソレント Sorrento
Sorrento
ナポリ Galerii
Galerii
ローマ
パレルモ
■ Hermann Emil Fischer
Hermann Emil Fischer
食糧問題は解決している。それが出来るのは人的資源に恵ま
れた日本だと、ここだけの話だけれどそう思っている。その
鍵語は『酵素』或いは『微生物生理機能学』。酵素とは、生
体でおこる化学反応を自身は反応の前後で変化せず、特定の
化学反応の反応速度を速める分子のこと。その役割は、生命
を構成する有機、無機化合物を取り込み、必要な化学反応を
引き起こすことにある。 基質に結合する酵素
基質に結合する酵素
食糧用植物の安定生産は、先ず、その種の固有安定生育条件
⇒①大気条件、②地下(土壌)条件、③日照条件、④養分供
給条件を循環時系列制御で確定。ここで②の条件で、共生育
成する酵素(及び微生物)の制御技術が重要となる。例えば
、大腸菌は人間と同じく70%が水分で、残りの16.5%がタンパ
ク質6%がRNA(リボ核酸)、0.9%がDNA(デオキシリボ核酸)、
3%の脂質、0.3%の金属イオンで構成されているが、これらの
育成条件(温度、水素イオン濃度)、酸素、栄養源、糖、ア
ンモンアなどの二次最適化技術が重要となる。 アデノシン三リン酸/ATP
アデノシン三リン酸/ATP
■
ところで微生物は、真核生物+原核細胞(真正細胞+古細胞)
からなり、その種類は百万から千万種に及ぶといわれている
が、これらの機能を解析・抽出できれば解決するが、例えば
酪酸の生成には酸素供給を止め、乳酸を生成するには、酸素
を供給するといった具合に。また非水耕栽培植物で土壌栽培
に、水循環と同様に土壌粉体を連続乃至は間欠循環できれば、
根菜類のコンパクトで省力で、高生産性の栽培が可能となり、
もう米国、豪州、中国に頼らなくても学園都市ならぬ田園都
市で、他の田園都市と地産地消の高度分業連携システムの構
築が可能となる。そういった意味では彦根-長浜は絶好の条
件を備えていると思う。 相馬暁教授『2020年農業時代が来る』
相馬暁教授『2020年農業時代が来る』
第21回宮城県産直交流会記念講演
そういうわけで、今年も諦めず、稲作のミニマム試験栽培を
行うことにした。
鴬の来鳴く山吹 うたがたも君が手触れず 花散らめやも 大伴池主

■











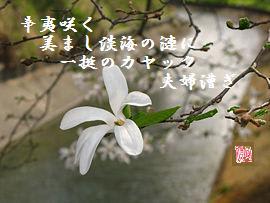



 シャーレ
シャーレ







 にいがたのろしPJ シンボルデザイン
にいがたのろしPJ シンボルデザイン 
 信玄の狼煙台ネットワーク
信玄の狼煙台ネットワーク







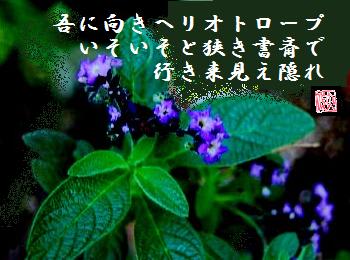

 彦根城に移築された三の丸
彦根城に移築された三の丸

 小谷城址航空写真
小谷城址航空写真

 cmosセンサ
cmosセンサ













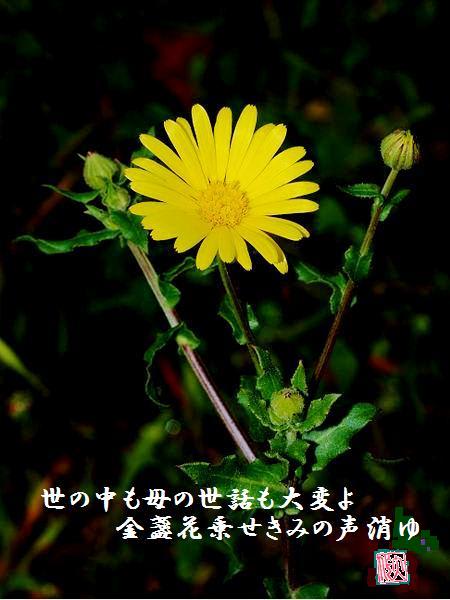


 彦根城空中撮影
彦根城空中撮影







