
【十王村六角堂の五角形の小池】
五つの要素を並列的に図案化できる図形として、洋の東西を問わず使われてきた。世界中で魔術の
記号とされ守護に用いることもあれば、上下を逆向きにして悪魔の象徴になることもある。悪魔の
象徴としてとらえる際には、デビルスターと呼ばれることもある。また、外側の五つの三角形が星
の光彩を連想させることから星を表す記号として用いられてきた。なお、内側に生じる小さな正五
角形を取り除いた形(☆:五光星)もしばしば五芒星と呼ばれ、この「五光星」には「五稜星」と
いう別名がある。五芒星は、陰陽道では魔除けの呪符として伝えられ、印にこめられたその意味は、
陰陽道の基本概念となった陰陽五行説、木・火・土・金・水の五つの元素の働きの相克を表したも
のであり、五芒星はあらゆる魔除けの呪符として重宝されきたという。歴史的に確認されているも
っとも古い五芒星は、紀元前三千年頃のメソポタミアの書物である。シュメール人はこれをUB(ウ
ブ)と呼び、下向き五芒星を「角・小さな空間・穴」などの意味を表す絵文字として用いた用いた
が、エジプトでは子宮を表わし性的意味合いとして用い、バビロニアでは、図形の各側面に前後左
右と上の各方向を割り当て、それぞれ木星・水星・火星・土星、そして上に地母神イシュタルの現
れとされた金星を対応させていいたといわれている。五芒星に五惑星を対応させる考え方は、後の
ヨーロッパにも見られられる。また、火(アカ)・水(アオ)・風(シロ)・土(クロ)の四大元
素に霊(創生)を加えた五つのエレメントにもそれぞれの頂点が対応させられ、それは現在でも魔
法などのシンボリズムに使われている。
「どんな言語で説明するのもむずかしすぎるというものごとが、私たちの人生にはあります」
とオルガは言った。
たしかにその通りだ、とつくるはワインを飲みながら思った。他人に説明するだけではない。
自分に説明をするのだって、それはやはりむずかしすぎる。無理に説明しようとするとどこか
で嘘が生まれる。いずれにせよ明日になれば、いろんなことが今より明らかになるはずだ。そ
れを待てばいい。もし明らかにならなくたって、それでかまわないじゃないか。仕方ないさ。
色彩を欠いた多崎つくるは、色彩を欠いたまま生きていけばいいのだ。それで誰かに迷惑をか
けるわけではない。
彼は沙羅のことを思った。彼女のミントグリーンのワンピースと、明るい笑い声と、彼女が
手を繋いで一緒に歩いていた中年の男のことを思った。でもその考えもまた、彼をどこにも運
んでいかなかった。人の心は夜の鳥なのだ。それは静かに何かを待ち受け、時が来れば一直線
にそちらに向けて飛んでいく。

彼は目を閉じ、アコーディオンの音色に耳を澄ませた。その単調なメロディーは人々の賑や
かな話し声をくぐり抜けて聞こえてきた。まるで潮騒にかき消されそうになる霧笛のように。
つくるはワインを半分だけ飲み、札と小銭を適当に置いて席を立った。アコーディオン弾き
の前に置かれた帽子にユーロのコインを入れ、みんなにならって、通り過ぎるときに街灯に繋
がれた大の頭に手を触れた。それでも大は置物のふりでもしているみたいに、身動きひとつし
なかった。それから彼はゆっくり歩いてホテルに向かった。途中キオスクに寄って、ミネラ
ル・ウォーターとフィンランド南部のより詳しい地図を買った。

大きな通りの中央に設けられた公園には、作り付けの石のチェス・テーブルが並び、人々が
持参した駒でチェスを楽しんでいた。全員が男で、その多くは高齢者だった。ピツェリアにい
る人々とは違って、彼らはどこまでも寡黙だった。それを見物している人々もまた寡黙だった。
熟考は深い沈黙を必要とするのだ。道を行く人々の多くが犬を連れていた。大たちもまた寡黙
だった。通りを歩いていると、時折焼き魚の匂いや、ケバブの匂いが風に乗って漂ってきた。
もう夜の九時近くだというのに、花屋はまだ店を開けており、そこには色とりどりの夏の花が
並んでいた。夜というものを忘れてしまったかのように。
ホテルのフロントデスクで七時にウェイクアップ・コールを頼んだ。それからふと思いつい
て尋ねてみた。「この近くにプールはありますか?」
従業員は眉を少ししかめ、考えを巡らせ、それから丁寧に首を横に振った。まるで国家の歴
史の不備を詫びるように。「申し訳ありませんが、この近くにはプールはございません」
彼は部屋に戻り、窓の分厚いカーテンをぴたりと引き、外の光を遮ってから、服を脱いでベ
ッドに入った。しかしそれでもまだ光は、簡単に消すことのできない古い記憶のように、どこ
からともなく忍び入ってきた。部屋のうす暗い天井を見上げていると、クロを訪ねようとする
自分が、名古屋ではなく、こうしてヘルシンキにいることが奇妙なことに思えた。北欧の夜の
独特の明るさは、彼の心に不思議な震えをもたらした。身体は眠りを求めているのだが、頭は
今しばらくの覚醒を求めている。
それからシロのことを思った。もう長いあいだ彼女の夢を見ていない。昔はよく彼女が登場
する夢を見たものだ。多くの場合それは性夢であり、彼は彼女の中で激しく射精した。そして
目が覚めて、洗面台で精液に汚れた下着を洗いながら、いつも複雑な思いにとらわれたものだ
った。罪悪感と強いあこがれが分かちがたく絡んだ奇妙な感情だった。それはおそらく、現実
と非現実とがこっそり混じり合う、暗い人知れぬ場所でしか生まれない特殊な感情だった。彼
はその感情を不思議に懐かしく思った。どんな夢でもいい、どんな気持ちになってもいい。も
う一度シロの出てくる夢が見られるといいのだが。
やがて眠りは訪れたが、そこには夢はなかった。
七時にウェイクアップ・コールがかかってきて、それでようやく目を覚ました。ずいぶん長
く深く眠ったという感覚があり、身体全体が心地良く庫れていた。シャワーを浴び、髭を剃り、
歯を磨き終えるまでその峰れは残っていた。空は隙間なくうっすらと曇っていたが、雨が降り
出しそうな気配は見えなかった。つくるは着替えて、ホテルの食堂でビユッフェ式の簡単な朝
食をとった。
九時過ぎにオルガのオフィスを訪れた。坂道の途中にあるこぢんまりとしたオフィスで、彼
女の他には魚のような目をした長身の男が一人いるだけだった。その男は電話に向かって何か
を説明していた。壁にはフィンランド各地のカラフルなポスターが貼ってあった。オルガはプ
リントアウトした何枚かの地図をつくるにくれた。ハメーンリンナの街から湖沿いにしばらく
行ったところに小さな町があり、そこにハアタイネンー家のサマーハウスがあった。その場所
に×がつけられていた。湖はまるで運河のように、うねりながら細長くどこまでも続いていた。
おそらく何万年か前に、移動する氷河によって深く削られたのだろう。

「道はたぶん簡単にわかると思いますよ」とオルガは言った。「フィンランドは東京やニユー
ヨークとは違います。交通量も多くないし、道路標識を辿っていけば、そしてエルクにさえぶ
つからなければ、そこに着けるはずです」
つくるは礼を言った。
「車は予約してあります。まだ二千キロしか走っていないフォルクスワーゲン・ゴルフです。
料金も少しだけですが割引になっています」
「ありがとう。素晴らしい」
「いろんなことがうまく行くことを析っています。せっかくフィンランドまでいらっしやった
のですから」とオルガはにっこりと微笑んで言った。「もし何か困ったことがあったら私に電
話をしてください」
そうする、とつくるは言った。
「エルクには気をつけて。愚かな動物です。あまりスピードを出さないように」
二人はまた握手をして別れた。
レンタカーのオフィスでまだ真新しい紺色のゴルフを借り、ヘルシンキの中心から高速道路
に乗るまでの道筋をデスクの女性に説明してもらった。少しばかり注意が必要だが、それほど
むずかしい道筋ではない。そしていったん高速道路に乗ってしまえば、あとは簡単だ。
つくるはFMラジオの音楽を聴きながら、時速百キロ前後で高速道路を西に向かった。ほと
んどの車は彼を追い越していったが、気にしなかった。車のハンドルを握るのは久しぶりだし、
おまけに左ハンドルだ。それに彼としてはできることなら、ハアタイネンー家が昼食を済ませ
た頃に、彼らの家に到着したかった。時間はまだたっぷりある。急ぐことはない。クラシック
音楽専門局は軽快できらびやかなトランペット協奏曲を流していた。
道路の両側はおおむね森だった。国土全体が瑞々しく豊かな緑色で覆われているような印象
があった。樹木の多くは白樺で、そこに松やトウヒやカエデが混じっていた。松は幹が直立し
たアカマツで、白樺は枝がしだれたように大きく垂れ下がっていた。どちらも日本では見かけ
ない種類のものだ。その間にときおり広葉樹も見受けられた。大きな翼を持った鳥が、地上の
獲物を探しながら風に乗ってゆっくりと空を漂っていた。ところどころに農家の屋根が見えた。
農家はひとつひとつが大きく、なだらかな丘陵に沿って栂が続き、放牧されている家畜の姿も
見えた。牧草が刈られ、機械で大きな丸い束にまとめられていた。
ハメーンリンナの街に着いたのは十二時前だった。つくるは駐車場に車を駐め、十五分ばか
り街を散策した。それから中心の広場に面したカフェに座ってコーヒーを飲み、クロワッサン
をひとつ食べた。クロワッサンは甘すぎたが、コーヒーは濃くてうまかった。ハメーンリンナ
の空もヘルシンキと同じように、やはりうっすらと全体的に曇っていた。太陽の姿は見えない。
中空あたりにオレンジ色の溶んだシルエットが見えるだけだ。広場を吹き渡る風はいくぶん肌
寒く、彼はポロシャツの上から薄手のセーターを着た。

ハメーンリンナには観先客の姿はほとんど見当たらなかった。買い物袋を抱えた普段着の人
々が行き来しているだけだ。街の中心にある通りも、観光客相手というよりは、地元の人々や、
あるいは別荘で暮らす人々が日常的に必要とする食品や雑貨を並べた商店が中心になっていた。
広場を挟んだ正面には大きな教会があった。丸い緑の屋根を持ったずんぐりとした教会だ。黒
い鳥たちの群れが磯の波のように、その屋根から屋根へと忙しく飛び移っていた。白いカモメ
たちが怠りのない目であたりをうかがいながら、広場の石畳をゆっくりと歩いていた。
広場の近くには野菜や果物を売るカートがいくつか並んでおり、彼はそこでサクランボを一
袋買い、ベンチに座って食べた。サクランボを食べていると、十歳か十一歳くらいの二人の女
の子がやってきて、少し離れたところから彼をじっと見ていた。おそらくこの街にやってくる
東洋人はそれほど多くないのだろう。一人はひょろりと背が高く色白で、もう一人は日焼けし
た頬にそばかすがあった。二人とも髪をお下げにしていた。つくるは二人に向かって微笑んだ。
二人は用心深いカモメのように、少しずつ彼に近づいてきた。
「中国人?」と背の高い方が英語で尋ねた。
「日本人だよ」とつくるは言った。「近いけど、ちょっと違う」
二人はよくわからないという顔をしていた。
「君たちはロシア人?」とつくるは尋ねた。
二人は首を横に何度か振った。
「フィンランド人」とそばかすの方が真剣な顔で言った。
「それと同じだよ」とつくるは言った。「近いけど、ちょっと違う」
二人は肯いた。
「ここで何をしている?」とそばかすの方が尋ねた。英語の構文を試すみたいに。たぶん学校
で英語を勉強していて、外国人相手にそれを試してみたいのだろう。
「友だちに会いに来た」とつくるは言った。
「日本からここまで何時間かかる?」と背の高い方が尋ねた。
「飛行機でだいたい十一時間」とつくるは言った。「そのあいだに二度食事をして、映画を一
本見た」
「どんな映画?」
「『ダイ・ハード12』」
それでどうやら少女たちは満足したようだった。二人は手を繋ぎ、スカートの裾を翻して広
場を走って去っていった。風に吹かれる草王のように。人生についての省察や警句はなかった。
つくるはほっとしてサクランボを食べ続けた。
つくるがハアタイネンー家のサマーハウスに辿り着いたのは一時半だった。彼らの住まいを
見つけるのは、オルガが予言したほど簡単ではなかった。そこには道路と呼べるようなものが
存在しなかったからだ。もし一人の親切な老人がいなかったら、ひょっとして永遠にその家は
みつからなかったかもしれない。
道路沿いに車を停め、グーグルの地図を片手に途方に暮れている彼の姿を見て、自転車に乗
った小柄な老人が寄ってきた。古いハンチングをかぶり、ゴムの長靴を履いていた。耳からた
くさんの白い毛を出し、目は赤く充血していた。まるで何かに対してひどく腹を立てているみ
たいに。つくるは地図を老人に見せ、ハアタイネンさんのサマーハウスを探しているのだと言
った。
「この近くだ。案内してあげよう」。老人は最初にドイツ語で、それから英語でそう言った。
重そうな黒い自転車を近くの本にそのまま立てかけると、返事も開かずにゴルフの助手席にさ
っさと乗り込んできた。そして古い切り株のようなごつごつとした指を前に突き出して、辿る
べき道を示した。湖沿いに、林を抜ける未舗装路があった。道路というよりは、車の轍だけで
成り立っているような踏み分け道だ。二本の轍の間には緑の草がたっぷりと茂っていた。それ
を進んでいくと、やがて道は二つに分かれた。分岐点には、ペンキで名前を書いたいくつかの
標識が本の幹に釘で打ち付けられ、右側のひとつにHaatainenと書かれていた。
その右側の道をしばらく進むと、やがて開けた場所に出た。白樺の幹の間から湖が見えた。
小さな突堤があり、そこに芥子色のプラスティック製のボートが一隻繋がれていた。釣りをす
るための簡単なボートだ。木立に囲まれたこぢんまりとした木造のキャビンがあり、その屋根
からは四角いレンガの煙突が突き出ていた。キャビンの横にはヘルシンキのナンバー・プレー
トがついた白いルノーのヴァンが駐まっていた。
「あそこがハアタイネンの家だ」と老人は重々しい声で告げた。そしてこれから吹雪の中に出
ていく人のように、帽子をしっかりとかぶり直し、地面にぺっと痰を吐いた。つぶてのように
硬そうな痰だった。
つくるは礼を言った。「自転車を駐めたところまで送りましょう。もう道はわかりましたか
ら」
「いや、その必要はない。歩いて帰れる」と老人は怒ったように言った。たぶんそう言ったの
だと思う。それはつくるには理解できない言語だった。響きからしてどうやらフィンランド語
ではないようだ。そして握手の手を差し出す暇もつくるに与えず、さっさと車を降り、大股に
歩き出した。後ろも振り返らなかった。冥界への道筋を既に死者に教えた死神のように。
つくるは道ばたの夏草の中にゴルフを駐めたまま、老人の後ろ姿を眺めていた。それから車
を降りて大きく息を吸い込んだ。ヘルシンキよりも空気が一段と清浄に感じられた。作りたて
の空気のようだ。緩やかな風が白樺の葉を揺らせ、ボートが突堤に当たるかたかたという軽い
音が時折聞こえた。どこかで鳥が啼いた。よく通る簡潔な声だった。

つくるは腕時計を見た。もう昼食は終わっただろうか? 少し迷ったが、ほかにやることも
思いつかないので、ハアタイネンー家を訪問してみることにした。彼は緑の夏草を踏み、まっ
すぐキャビンに向けて歩いていった。ポーチで昼寝をしていた大が立ち上がり、彼の方を見た。
小さな茶色の長毛大だった。そして何度か吠えた。紐で繋がれてはいなかったが、威嚇的な吠
え方ではなかったので、彼はそのまま前に進んだ。
犬の声を聞いたのだろう。彼が戸口に辿り着く少し前に、ドアが開いて男が顔をのぞかせた。
頬から顎にかけて濃い金髪の髭をのばした男だ。四十代半ばというところだろう。背はあまり
高くない。オーバーサイズのハンガーのように肩がまっすぐ横に広がり、首が長い。髪はやは
り濃い金髪で、もつれたブラシのように見えた。そこから耳が横に突き出している。チェック
の半袖シャツを着て、作業用のブルージーンズをはいていた。彼はドアノブに左手を置いたま
ま、近づいてくるつくるの姿を見ていた。それから犬の名前を呼び、吠えるのをやめさせた。
「ヘロー」とつくるは言った。
「こんにちは」と男は日本語で言った。
「こんにちは」とつくるも日本語で挨拶を返した。「ハアタイネンさんのおたくですか?」
「そうです。ハアタイネンです」と男は流暢な日本語で言った。「私はエドヴァルト・ハアタ
イネンと申します」
つくるはポーチの階段について手を差し出した。男も手を差し出し、二人は握手をした。
「多崎つくると言います」とつくるは言った。
「つくるというのは、ものを作るのつくるですか?」
「そうです。そのつくるです」
男はにっこりとした。「私もものを作ります」
「それはよかった」とつくるは言った。「僕もものを作っています」
犬がやってきて、男の足に頭をすりつけた。それからおまけのようにつくるの足にも同じこ
とをした。それが歓迎の儀式なのだろう。つくるは手を伸ばして犬の頭を撫でた。
「多岐さんはどんなものを作るのですか?」
「僕は鉄道の駅を作っています」とつくるは言った。
「ほう。ご存じですか? フィンランドで最初に鉄道が敷かれたのはヘルシンキと、このハメ
ーンリンナの間です。そんなわけで、ここの人々は駅に誇りを持っています。ヤン・シベリウ
スの生地であることと並んでね。あなたは正しい場所にお見えになったわけだ」
「そうですか。それは知りませんでした。それで、エドヴァルトさんはどんなものを作ってお
られるのですか?」
「私は陶器を作っています」とエドヴァルトは言った。「駅に比べればとても小さなものです。
さあ、どうぞ中にお入りください、タザキさん」
「お邪魔じゃありませんか?」
「ぜんぜん」とエドヴァルトは言った。そして両手を広げた。「ここでは誰でも歓迎します。
何かを作っている人なら、私の仲間です。とりわけ歓迎します」
キヤビンの中には誰もいなかった。テーブルの上にはコーヒーカップがひとつ、ページが開
きっぱなしになったフィンランド語のペーパーバックが一冊載っているだけだった。どうやら
彼はそこで一人で本を読みながら、食後のコーヒーを飲んでいたらしい。彼はつくるに椅子を
勧め、自分はその向かいに座った。本にしおりを挟んでページを閉じ、脇に押しやった。
「コーヒーはいかがですか?」
「いただきます」とつくるは言った。
エドヴァルトはコーヒーメーカーのところに行って、湯気の立つ温かいコーヒーをマグカッ
プに注ぎ、つくるの前に置いた。
「砂糖とクリームはいりますか?」
「いいえ、ブラックでいいです」とつくるは言った。
クリーム色のマグカップは手作りだった。取っ手がいびつで、不思議な格好をしていた。し
かし持ちやすく、手触りに親密な感触があった。家族の中だけで通じる温かい冗談のように。
「そのカップは私の上の娘が作りました」とエドヴァルトはにっこりして言った。「もちろん
実際に窯で焼いたのは私ですが」
彼の目は優しそうな淡い灰色で、それが髪と髭の濃い金色とよく似合っていた。つくるはそ
の男に対してごく自然な好意を持つことができた。都会の生活よりは、森や湖が似合いそうな
タイプだ。
「多崎さんはきっと、エリにご用があって来られたのでしょうね?」とエドヴァルトは尋ねた。
「ええ、僕はエリさんに会いに来ました」とつくるは言った。「エリさんは今ここにおられま
すか?」
エドヴァルトは肯いた。「エリはここにいます。今は娘たちと食後の散歩に出ています。た
ぶん湖の畔を歩いているはずです。とても良い散歩道があるのです。いつものように犬が一足
先に戻ってきました。ですから彼女たちももうすぐ戻ってくるはずです」
「日本語がとてもお上手ですね」とつくるは言った。
「五年日本に住んでいました。岐阜と名古屋です。そこで日本の陶芸を勉強していました。日
本語を覚えないとなにもできません」
「そこでエリさんと知り合ったのですね?」
エドヴァルトは明るい声で笑った。「そうです。あっという間に恋に落ちました。八年前に
名古屋で結婚式をあげて、それから二人でフィンランドに帰ってきました。今はここで陶器を
作っています。フィンランドに戻ってしばらくはアラビア社でデザイナーとして働いていたの
ですが、どうしても自分一人で仕事をしたくて、二年前にフリーランスになりました。週に二
度ですが、ヘルシンキの大学でも教えています」
「いつもここで夏を過ごすのですか?」
「はい、七月初めから八月半ばまではここで生活します。すぐ近くに仲間と共同で使っている
小さな工房があります。午前中は朝早くからそちらで仕事をしますが、いつも昼食をとりにう
ちに帰ります。そして午後はおもにここで家族と共に過ごします。散歩をしたり、本を読んだ
り。ときどきみんなで魚釣りに行ったりもします」
「ここは素敵なところですね」
エドヴァルトは嬉しそうににっこりした。「ありがとう。このあたりはとても静かで、仕事
も進みます。私たちはシンプルな生活を送っています。子供たちもここが好きです。自然とふ
れあうことができます」
部屋の白い漆喰の壁の一面には、床から天井近くまで木製の棚が取り付けられ、そこには彼
が焼いたらしい陶器が並べられていた。それ以外に部屋には装飾と呼べそうなものはほとんど
なかった。飾り気のない丸い時計が壁にかかり、コンパクトなオーディオ・セットと一山のC
Dが、頑丈そうな古い木製キャビネットの上に置かれているだけだ。
「その棚に並んでいる作品の三割ほどは、エリがこしらえたものです」とエドヴァルトが言っ
た。その声には誇らしい響きが聞き取れた。「なんと言いますか、彼女にはナチュラルな才能
があります。持って生まれたものです。それが作品ににじみ出ています。ヘルシンキのいくつ
かの店に置いてありますが、店によっては、私の作品よりむしろ人気があるくらいです」
つくるは少し驚いた。クロが陶芸に興味を持っているという話を耳にしたことは一度もなか
ったからだ。

「彼女が陶器を作っているとは知りませんでした」とつくるは言った。
「エリは二十歳を過ぎた頃から陶芸に興味を持つようになり、普通の大学を卒業したあと、愛
知芸大の工芸科に入り直したのです。私たちはそこで出会いました」
「そうですか。僕はほとんど十代の彼女しか知らないので」
「高校時代のお友だちですか?」
「そうです」
「タザキ・ツクルさん」とエドヴァルトは名前をあらためて口にし、目を細め、記憶を辿った。
「そういえば、あなたの話はエリから聞いたことがあります。名古屋で、とても仲の良い五人
グループの一人だった。そうですね?」
「ええ、そうです。僕らはひとつのグループに属していました」
「名古屋での私たちの結婚式には、そのグループの三人の人たちが来てくれました。アカとシ
ロとアオ。たしかそうでしたね?・ カラフルな人たち」
「そのとおりです」とつくるは言った。「僕は残念ながら、式には出席できませんでしたが」
「でも今こうしてお会いできた」と彼は言って、温もりのある笑みを浮かべた。頬髭が焚き火
の親密な炎のように顔の上で揺れた。「タザキさんは、旅行でフィンランドに来られたのです
か?」
「そうです」とつくるは言った。本当のことを話すと、長い説明が必要になってくる。「旅行
でヘルシンキに来ることがあって、できればエリさんに久しぶりに会いたいと思って、ここま
で足を伸ばしたのです。前もって連絡ができず、申し訳ありませんでした。ご迷惑でなければ
よかったのですが」
「いいえ、いいえ、迷惑なんかじやありません。大歓迎します。こんな遠くまでようこそいら
してくださいました。たまたま私が一人で家に残っていて幸運でした。エリもきっと喜ぶこと
でしょう」
喜んでくれればいいのだが、とつくるは思った。
「作品を拝見してもかまいませんか?」と彼は壁の棚に並んだ陶器を指さして、エドヴァルト
に尋ねた。
「もちろんです。自由に手を触れてもらっていいです。私の作品とエリの作品があちこち混ざ
っていますが、印象がずいぶんちがいますから、説明しなくてもどちらのものか簡単にわかる
でしょう」
つくるは壁際に行って、そこに並べられた陶器をひとつひとつ見ていった。その大半は皿や
鉢やカップといった、実際に食卓で用いることのできる食器だった。それ以外には花器や壷な
どがいくつかあった。
エドヴァルトが言ったように、彼の作品とエリの作品の違いは一目でわかった。滑らかな生
地で、パステル・カラーのものが夫の作品だ。色はところどころで濃くなったり淡くなったり
して、風や水が流れるような微妙な陰影を描き出していた。柄のついたものはひとつもなかっ
た。色の移り変わりがそのまま模様になっている。その発色がかなり高度な技術を要するであ
ろうことは、陶芸にはまったくの素人であるつくるにも容易に想像できた。余計な装飾を排し
たデザインと、滑らかで上品な手触りが彼の作品の特色だった。基本的には北欧風ではあるけ
れど、その削ぎ落とされたようなシンプルさには、日本の陶器の明らかな影響が見られた。持
つと意外なほど軽く、手に馴染んだ。細部にまで丹念に気が配られている。いずれにせよ一流
の職人にしかできない手仕事だ。大量生産をする大きな会社では、たぶんその才能が発揮しき
れなかったのだろう。
それに比べるとエリの作風はずっとシンプルだった。技術的な観点から見れば、夫の作品の
緻密さ、精妙さには遥かに及ばない。全体的に肉厚で、縁が描くカーブも微妙に歪んでいたし、
洗練されたシャープな美しさはうかがえない。しかし彼女の作品には、見るものの心を不思議
にほっとさせる温かな持ち味があった。僅かに不揃いなところが、またざらりとした手触りが、
自然素材の布を手にしたときのような、縁側に腰を下ろして空を流れる雲を眺めているときの
ような、静かな落ち着きを与えてくれた。
彼女の作品の特色は夫の作品とは逆に、模様にあった。どの作品にも、まるで風に吹き寄せ
られる木の葉のように、ある場合には散り散りに、ある場合にはまとまって、細かい模様が描
かれていた。模様の散らし方によって、全体の印象は淋しげになり、また華やかにもなった。
その精妙さは古い着物の小紋を思わせた。つくるはひとつひとつの模様が何をあらわしている
のかを見きわめようと、目を近づけてみたのだが、形象の意味を特定できなかった。不思議な
図形だ。しかし少し距離をとって眺めると、森の地面にはらはらと散った木の葉にしか見えな
い。匿名の動物たちが人知れず、こっそりと音もなく踏みしめていく木の葉だ。
彼女の作品にとっての色彩は、夫の作品とは違ってあくまで背景に過ぎなかった。模様をど
う生かすか、どのように浮かび上がらせるか、それが色彩に与えられた役目だった。色彩はご
く淡く、寡黙に、しかし効果的に模様の背景を担っていた。
つくるはエドヴァルトの食器とエリの食器を交互に手にとって見比べていった。この夫婦は
実際の生活においても、きっと上手にバランスをとって暮らしているのだろう。そう思わせる
心地良い対比があった。スタイルは異なっているが、それぞれが相手の持ち味を受け入れよう
としている。
「妻の作品を、夫である私がこんなにほめるのは、正しくないことかもしれません」とエドヴ
ァルトはつくるの様子を見ながら言った。「日本語でなんと言いましたか。身びいき--そう
ですね?」
つくるは微笑んだだけで何も言わなかった。
「でも私は、夫婦だからというのではなく、エリの作品が好きです。もっと上手に、きれいに
陶器を作る人は、世の中に多くいますでしょう。でも彼女の作るものには、狭さがありません。
心の広さが感じられます。もっとうまく言えるといいのですが」
「おっしやっていることはよくわかります」とつくるは言った。
「そういうものはきっと、天から与えられたものですね」、彼は天井を指さした。「ギフト。
そして彼女はこれから先、もっと上手になっていくにまちがいありません。エリにはスペース
がまだうんと残されています」
外で犬が吠えた。いかにも親しげな、特別な種類の吠え方だった。
「エリと娘たちが戻ってきたようです」とエドヴァルトが顔をそちらに向けて言った。そして
立ち上がり、ドアの方に向かった。
つくるは手にしていたエリの陶器を注意深く棚に戻し、そこに立ったまま、彼女が戸口に現
れるのを待った。
PP.260-278
村上春樹 『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』
多崎つくるを主人公とした物語から水幸亭落成式にはじまる十王村の五角堂(『十王村龍門之図』)
への巡礼と続いた旅はいよいよ佳境へと突入する。村上春樹の渾身の現在の寓話の核心とはなにか
?! 「たまには熟っくりと本を読もう!」で明らかにされるペンタブラムの確信とはなにか?!
乞うご期待!











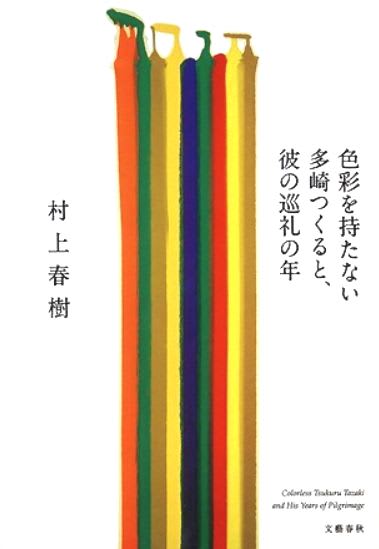
















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます