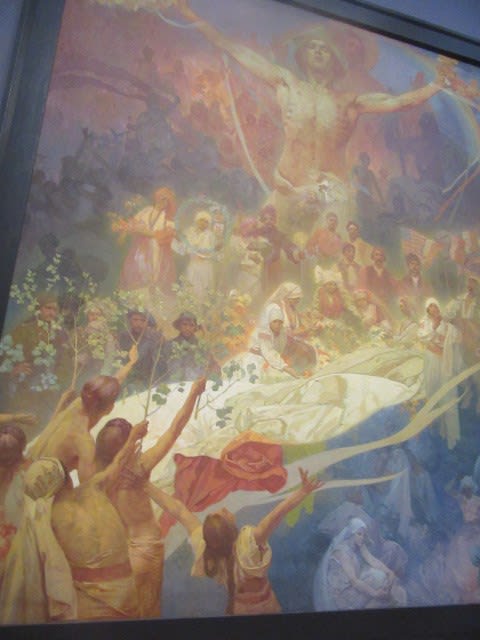おはようございます。
先日、国立新美術館のミュシャ展を見に行った。家内がむかしからミュシャのファンで、10年以上も前になるが、プラハに遊んだとき、一緒にミュシャ博物館を訪ねた。そのとき以来、ぼくも気に入って、とくに、19 世紀パリの伝説的女優 サラ・ ベルナールのポスターは印象に残っている。また、ギフトショップで買った”四つの花”は、今も部屋に飾ってある。本展にも、これらの作品をはじめ、いわゆるアールヌーボー様式の華やかなポスターがたくさん展示されているが、今回の目玉は、あまり知られていなかった”超大作”スラブ叙事詩、全20作である。
まず、どれほどの”超大作”か、見ていただきましょうか。スラブ叙事詩はスラブ民族の苦難と栄光の歴史を辿ってゆくのだが、その終盤の場面を飾る部屋が、うれしいことに撮影可能なのだ。こんなふうに。


パリで成功をおさめていたミュシャは、当時、オーストリア・ハンガリー帝国に支配されていた故郷のチェコのことを忘れてはいなかった。祖国が自由と独立を求め闘っている中、自身もスラブ民族をテーマにした作品を手掛けていた。そして、50歳のとき、故郷、プラハへ戻り、本作にとりかかった。なんと、17年の歳月をかけて、巨大なカンヴァスに、古代から近代に至るスラブ民族の歴史画を描いた。これら20点が、チェコ国外では初めての公開ということで、とにかく、奇跡的な展覧会なのだ。
さて、20作のスラブ抒情詩のすべてをここで説明することは、ぼくには、とても出来ないので、いくつかの画面を紹介して、お茶を濁したい。この展覧会に行く前に、NHKの”華麗なるミュシャ/祖国への旅路/パリ・プラハ二都物語”を見ておいたので参考になった。そのテレビ画像も利用させてもらいながら、進めてみたい。
スラヴ叙事詩
1:原故郷のスラヴ民族(トゥーラニア族の鞭とゴート族の剣の間に)

他民族(騎馬民族など)の侵入から身をひそめるスラヴ民族の祖先たち。

2:ルヤーナ島でのスヴァントヴィート祭(神々が戦いにあるとき、救済は諸芸術の中にある)

6:東ローマ皇帝として戴冠するセルビア皇帝ステファンドゥシャン(スラヴ法典)


11:ヴィートコフ山の戦いの後(神は力でなく、真理を体現する)

どの画面の主人公も小さく描かれ、庶民が前面に出ている。チェコの人々を写生して、それを歴史画の中にとり入れている。

15:イヴァンチツェの兄弟団学校(クラリツェ聖書の印刷)

17:聖アトス山

18:スラヴ菩提樹の下で行われるオムラジナ会の誓い(スラヴ民族の復興)

19:ロシアの農奴制廃止

20:スラヴ民族の賛歌
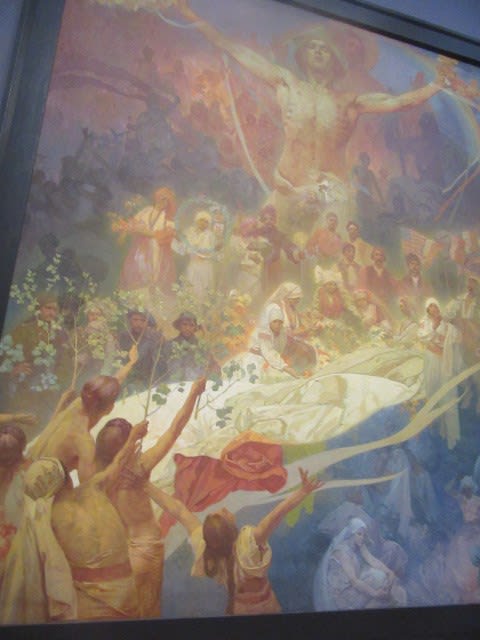
1939年3月、ナチスによってチェコスロヴァキア共和国は解体される。ミュシャは、彼のスラヴ叙事詩が国民の愛国心を刺激するものであるという理由で逮捕される。厳しく尋問を受け、体調を崩し、78歳で他界した。

(プラハの街↑)
それでは、みなさん、今日も一日、お花見でもしながら、お元気で! ぼくは、これから、都内の桜見物へ。