
出光美術館で開催されている”屏風の世界/その変遷と展開”を先日覗いていた。展示作品の中に岩佐又兵衛のが数点、含まれていること知り、是非にと思っていた。今年はじめ、東博で”洛中洛外図屏風舟木本”を観て、5月に”浄瑠璃絵巻”等を観て、そして、この日と、最近、連続して岩佐又兵衛を観ている。また今月、山種でも観る予定だ。ぼくが又兵衛フアンになってから、いろいろな美術館が次々と、ぼくのために又兵衛展覧会を開いてくれる。うれしいことだ。
第1部”日本式屏風の誕生”では、重要文化財の”四季花木図屏風(伝土佐光信)と”四季花鳥図屏風(能阿弥)”が展示されていたが、ぼくが、その部屋をぐるっと見まわして、一番、惹かれた、ひとつの屏風があった。いつかどかで観た風景のような気がしたのだ。”西湖図屏風(狩野元信)”(室町時代)だった。
実は20年ほど前、中国浙江省杭州市出身の仕事仲間の案内で、西湖(中国読みでシーフー)を訪れたことがあるのだ。うつくしい湖だったので印象に残っている。ただ、一度だけみた風景がぼくを惹きつけたのだから、やっぱりすごい絵だと思った。屏風では高い峰が描かれていたが、たしか西湖の廻りには高い山はなかったはずだ(笑)。説明文に、この屏風をじっと眺めれば、鶴をつれ、この地に隠棲した林和靖(詩人)の気分に近づけるだろう、とあった。屏風絵の中に鶴をつれた男がいた。この男が林和靖だろうか。屏風の前の椅子にしばらく座り、西湖をながめ、当時のことを想った。友人がこの辺りは中国でも一番美人の多いところだと自慢していた。あの西施も、浙江省の出身らしい。 芭蕉の句にもある。象潟や雨に西施がねぶの花
第二部”物語絵の名場面”には、お待ちかね(笑)、又兵衛さんの登場だ。”三十六歌仙図屏風”が光っている。上段に歌合わせをしている三十六歌仙が、そしてそれぞれの和歌の色紙も。左右隻の端が、人麻呂と紀貫之で、並べると、二人がにやにや何か話している様子でなる。小野小町のうわさ話でもしているのだろうか(笑)。業平は右隻の方にいる。みな何かを話しているのに、ひとりぽつんという感じ。ひとりひとり、個性豊かに描かれている。双眼鏡でみたい感じ。一方、下段には、平家物語、伊勢物語、和漢の故事、風俗、山水が団扇に描かれ、波の上に貼られている。
三十六歌仙図”人麻呂”と”赤人”は、それぞれ個別の紙本墨画淡彩図があり、双眼鏡でみなくても、繊細な筆使いがよくわかる。又兵衛作の、もうひとつ六曲一双の蟻通・貨狄(ありどうし・かてき)造船図屏風もあり、計4点も観られてうれしかった。本当は十六歌仙図をここに掲載したかったが、重い図録は買わない主義だし(汗)、絵ハガキもなかったので、ちらしの裏にモノクロでのせてあった”蟻通・・”を代表でここに載せる。
蟻通・貨狄造船図屏風

その他、この二部には、宇治橋柴舟屏風(桃山時代、紙本金地着色)や源氏物藤裏葉(伝土佐光信)そして業平東下り図屏風(伝俵屋宗達)など、いいものが集まっていた。
業平東下り図屏風

第三部”風俗画の熱気と景観図の大空間”も楽しい展示物が多かった。今年も行く予定している祇園祭の”祇園祭礼図屏風(桃山時代)と江戸名所図屏風(江戸時代)、そしてちらし表紙絵に採用された”南蛮屏風”、世界地図・万国人物図屏風(江戸時代)等々。
祇園祭りでは、今も続いている、なぎなた鉾や月鉾が描かれていたし、江戸名所では、上野から品川辺りまでの、生き生きした人々の姿が描かれ、楽しそうな話声が聞こえてくるようだった。湯女に背中を流してもらっている男、遊郭であそんでいるような場面、そして今もある上野東照宮、不忍池や湯島天神、芝の増上寺などの景観。洛中洛外図のような、当時の風俗、風景が細かく描かれている。智恵子抄ではないけれど、”東京には空がない、ほんとの空が見たいと言う”。江戸には、本当の空がある、そんな気持ちにさせてくれる絵である。
江戸名所図屏風(部分)

そして、ちらしの表紙を飾る、華やかな、南蛮屏風(桃山時代)。光の当て方を工夫して、金色の雲を効果的に浮き出させているという説明があった。さらに、部屋のあちらこちらに、古九谷の大皿や古伊万里の壺、そして硯箱、香呂等いろいろな焼き物、工芸品も展示されていた。
いいものをみさせてもらった。次回もぜひ行こう。いいタイトルだな。

















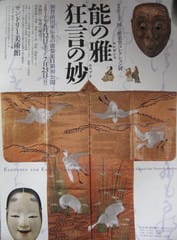

























 ついでながら、ぼくはこれで68.0キロまで戻しました、えへん。
ついでながら、ぼくはこれで68.0キロまで戻しました、えへん。



























 や、ややめてください、それだけは
や、ややめてください、それだけは

 こんなプレイボーイとはつきあえない、さっと雲がくれした。
こんなプレイボーイとはつきあえない、さっと雲がくれした。
















