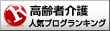■ 市の園芸教室「春まき野菜の作り方」に参加してきました。
会場は市ふるさと農園のホール、時間は9:30~12:00、参加者は50人だった。
受講者は、60歳以上7割、4,50代3割の男女という感じ。
家庭菜園を趣味にしている人がほとんどのようでした。
初めて行く場所なのでJR稲毛駅前のバス時刻がつかめず、余裕をもって出かけたつもりですが、開始時刻を1,2分過ぎていた。
講師の方は、○原農業高校の教師(この時も農業をやっておられた)を定年退職され、3年ほど過ぎた方。
現在、住まいの○の宮で田、畑(梨栽培)をやり、3日勤務で高校の講師と今回のような講座を引き受けているらしい。
今回の内容の要点を列記してみます。
・野菜の分類(果菜、葉菜、根菜、科別分類)
・栽培する品種を選定するとき
・野菜の種類によって栽培の難易度がある
・多湿に強い野菜と弱い野菜
・連作障害をおこす要因
・連作障害が出やすい野菜と出にくい野菜
・連作障害を少なくするための生態的除去、物理的除去、科学的除去
・肥料について(3要素、微量要素、施肥の方法、元肥、追肥)
・病害虫対策
・日常管理
話の中で印象に残った点は、土の状態、特に地温。育苗の方法。定植の時期。石灰の用い方。せん虫。接木。よい苗の条件、… …など。
自分としては、アンダーラインの知識がイマイチでしたので、今後の野菜づくりにだいぶ役立ちそうです。