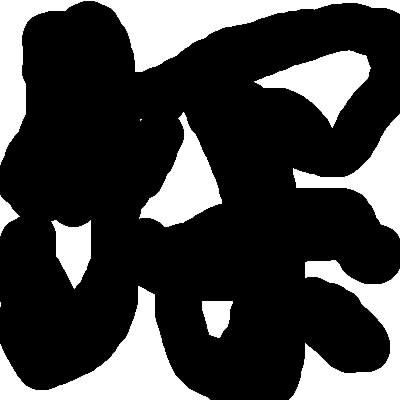
通り慣れた道だった。道の隅々まで見覚えがあった。あの角を曲がるといつも口の開いたごみ箱が置いてあるということまで、エミーには分かっていた。この国が左右反対だと分かった瞬間から、奇妙な吐き気は消えた。するとその光景はいつも見慣れた町そのものに思えるようになったのだ。
「おい、バックルパーじゃないか。」
不意に後ろから声がした。
「おお、ユング!!元気だったのか。」声の主を見て、思わずバックルパーは言葉を返した。竹馬の友、ユングの姿がそこに立っていたのだ。
「元気なものか、俺の心臓が止まりそうになったとき、おいおい泣いていたのはお前じゃないか。」
「そうだった。お前は死んだのだ。原因も分からずに、な。また訳の分からないものを食ったのだろう。」
「おいおい、こんなところに来てまで、減らず口をたたくんじゃない。バックルパー、それよりお前こそどうしたのだ、見たところ、叩いても死にそうには見えないが、それにエミーまで、一体何があったのだ。事故か。」
「ユング、今は詳しく言えないんだ。まあ、あれは事故のようなものだった。俺達はヅウワンに会いに来たんだ。」
「ヅウワンも気の毒だったな。あんな死に方をするなんて、早く行ってやれ。彼女、こちらに来てからずっと家でふさぎっぱなしだ、よほど悲しかったのだろう。しかしお前やエミーの顔を見れば、一変に元気になるだろう。」
「ありがとうユング。ヅウワンは家にいるんだね。」
「ああ。今度ヅウワンとみんなで食事をしようぜ。」
「そうだな。」
「では、」
二人は足早に歩きだした。しばらく歩いていると、後ろから、再びバックルパーを呼ぶ声が聞こえてきた。バックルパーが振り返ると、ユングが走り寄って来るところだった。何か言い忘れたのだろう、二人は足を止めてユングを待った。
「忘れる所だったよ。」そう言ってユングが駆け寄り、突然真顔になった。
「そのまま普通に話している振りをするんだ。」ユングは圧し殺すような声で言った。
「どうした。」けげんそうにバックルパーは聞き返した。
「周りを見るな。お前はつけられているぞ。何をした。」
「何だって、」
「警備隊の奴らだ。」




























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます