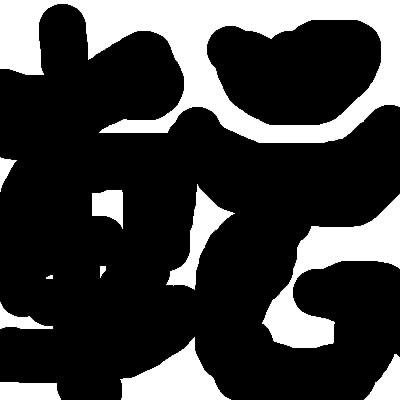「これ、何の図かしら。」
「多分、図書館だと思うよ。」カルパコが身を乗り出して図を指さした。
「ほら、ここが図書室で、この横が司書室だろう。」
「するとこの赤い線は何を意味するの?」
「ここを通おれってことだろうな。ここのところが、二枚目の文と合うだろう。ほら。」カルパコは図の右下の扉を指さした。
「配置図右下の小さな扉から入れ、か。ほんとだ、きっと、そ . . . 本文を読む
ユングの葬儀はひっそりと行われた。バックルパーの家族の他はエミーの友達が三人、図書館の方からはミネルバという女司書一人が参列しただけだった。二十年も努めた図書館なのに、どうして館長は来ないのか。バックルパーに腹立たしい思いが盛り上がってきた。悲しい喪失感がとげのように突き刺さってくる。
ユングの寂しい人生は自分のせいだと、バックルパーは考えていた。二人とも故国に身寄りはなかっ . . . 本文を読む
「何をそんなに驚いているんだ。」後ろにカルパコが立っていた。
「カルパコ、もう、びっくりさせないでよ。」
「ごめん、ごめん、なにか深刻そうだったから声をかけそびれちゃって。」
「ちょっと考え事してたの。」エミーが言い訳をした。
「おーい、」
ダルカンとエグマが手を振っている。皆がそろうと、エミーの不安もあっという間に消えてしまう。アモイ探偵団の力なのだ。
「さあ、行こうか。 . . . 本文を読む
エミーはバックルパーの仕事場にいた。仕事場にはヒノキの香りが立ち込めていた。樽を作るための、ヒノキの曲げものが何枚も棚に積み上げられていた。バックルパーは仕入れたばかりのヒノキの板を何枚も壁に立て掛けているところだった。
「おい、いい所に来た。ちょいと手伝ってくれないか。これを運ぶんだ。」
「ええっ、悪い所に来てしまったわ。」そうぶつぶついいながら . . . 本文を読む
「新字体が制定されるとほとんど同時に、旧字体で書かれた本はことごとく焼き捨てられたのだ。旧字体はもともと砂漠の民の文化そのものだったのだが、その本を痕跡も残さぬように国中の本を没収してまわったのだ。それはとても奇妙な事だ。」
「どうしてですか?」
「考えても見よ、クルゾの文化を抹殺するというのなら分かるが、自分の文化を抹殺してしまうというのだ。普通では考えられないことだ。」
「そういえ . . . 本文を読む
エミー達は、ただ聞くしかなかった。その話にどう反応して良いのか分からなかったのだ。パルマの話は続いた。
「砂漠の民の生への執着心は、この地に合理的な産業を発展させ、そのおかげで砂漠の生活では考えられないような豊かな国が生まれた。セブ王はその力を誇示するために二対の像を作ったのだ。それがセブ王の噴水なのだよ。」
「二対ですか、でもセブ王の噴水は、一つしかありませんね。するとも . . . 本文を読む
先住民グルゾには私有の概念がなく、肥沃な土地に育つ動植物と共に平和に生きていた。一年を通じて、甘酸っぱいコンクの実がたわわに実り、おとなしいヤクがのんびり草を食んでいた。そして至る所にクルソンの木が自生していた。クルソンとはグルゾの古いことばで薬木を意味しているのだが、クルゾ人はそれを万能薬として用い、何かあると、その樹皮を剥いで口に入れた。するといい気持になり、たいていの病気は治ると信じられてい . . . 本文を読む
ジルは不気味で、無愛想な男だったが、あっさり四人を通してくれた。ジルの最後の言葉は何かしら優しさが感じられて、エミーは親しみを持った。
奥の部屋には、至る所に擦り傷やはがれた所のある古びたテーブルが一つ置かれていた。パルマという名の老婆は、そのテーブルに向かって何か書き物をしていた。
「あの、すみません、」エミーが呼びかけた。
「おや、珍しいこともあるもんだ、こんな所に若い子がやって来 . . . 本文を読む
セブズーの町の中心街から少し離れたところに四丁目の街角がある。狭いが堅牢な石畳の街路が網の目のように通っている。その街路の両脇には様々な店舗が店を構えている。町中の商店が一か所に集まったような賑やかな一角になっている。子供だけで歩くのがはばかられるような雰囲気がいつも漂っていた。実際、子供だけで四丁目に行くことは学校からも親からも固く禁じられているのだった。
子供が一人で四丁 . . . 本文を読む
「違うのよ、王国の隠された歴史を調べているのよ。」
「隠された歴史だって、」
「そうなの、ユングさんなら何か知らないかと思って来たの。ねえ、王国の歴史にはどこか隠されたところがあるのかしら、そのことに関して昔からのいい伝えのようなものはありませんか。」
「そんな話を誰から聞いたのかね。」
「アモイ探偵団に依頼があったのよ。王家の眠らされた歴史に光をあてよって、」
「誰がそんな . . . 本文を読む