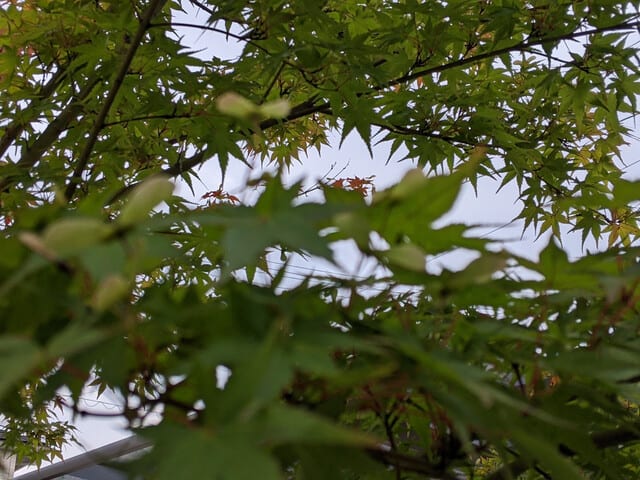
此謂知本。此謂知之至也。
右伝之五章。蓋釈格物致知之義。而今亡矣。間嘗窃取程子之意、以補之曰、所謂致知在格物者、言欲致吾之知、在即物而窮其理也。蓋人心之霊、莫不有知。而天下之物、莫不有理。惟於理有未窮。故其知有不尽也。是以大学始教、必使学者、既凡天下之物、莫不因其已知之理、而益益窮之、以求至乎其極。
至於用力之久、而一旦豁然貫通焉、則衆物之表裏精粗、無不到、而吾心之全体大用、無不明矣。此謂物格。此謂知之至也。
所謂「格物致知」の重要性を述べた部分で、秦の始皇帝によって失われた部分のそれに当たる本文があったというのだ。これを「知を致すは物に格(いた)るに有り」とよみ、知っている知をもとにして理を極めてゆくと、急に物の世界を貫通するように、心の本体と自らのするところ作用が明白に認識される。すなわち「物格」が「知の至り」として経験されるということなのである。
もしかしたら、我々の一部の人々が、やたら箱物をつくりたががるのは、物格の気分を味わいたがるということなのであろうか。実際は、鄭玄の解釈、「物を格たして知をいたす」――つまり自分が実現した物事の善し悪しが、自分の知の善し悪しとなる、みたいな解釈のほうが、現実にも良くおこっている。朱子はそれへの抵抗を無理やりやらざるを得なかったのかもしれない。みな、砂場の城を自分の手柄以上に認識するところからあまり抜け出せない。砂場をつくったのはお前ではない。
理を突き詰めなさいといえば自分勝手な裁断ばかり、逆に実現したものが凡てだといえば人を使って物を作って威張りたがる。手間をかけることが出来る王に向かってならともかく、こんな我々にとって、何かを実現したり認識を高めるみたいなことを大衆教育で行おうとすること自体が間違っているのかもしれない。AIの議論もあいかわらず、大衆を王として扱っている。だいたい作文コンクールで評価が高そうな作文を書こうとしている時点で頭がAI化しているのである。大衆教育というのは正解や独創性を生み出すためにやってるんじゃねえぞ、人間のクソじみた愚かさを共有するためにやっているのである。









