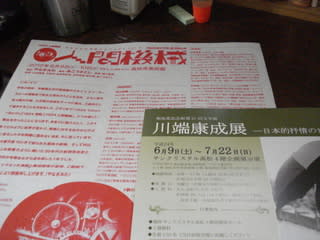中国でやってた「三国志 Three Kingdoms」を少しずつ見ている。曹操の俳優(と日本の声優・ 樋浦勉さん)がよく、どうみても奸雄にはみえん、というか、一番頭の良さそうなのはやっぱり曹操。いまのところ、劉備は自分の先祖を自慢するおホモだち野郎にすぎない。義兄弟の張飛は、劉備が「お前は酒のむな」と言ったとたんに酒を飲んでしまうようなアホだし。関羽は髭が長すぎる。黙っていることが多いから賢そうにみえるけどどうかな……。
やっと第一部の最後(18話)までたどり着いた。筋肉馬鹿・呂布の最期であった。さっさと曹操軍と戦うべきところ、貂蝉(←まだ生きてた!)が計ったように危篤になったので、世話になっている公台の忠告を無視して「おれは看病に専念するっ」とか、いきなり戦国の世に「愛妻物語」。やっぱりすさまじく馬鹿だった呂布。だいたい、この突然の貂蝉の病気が、怪しい。このひと、もともと董卓と呂布の仲を裂こうとした王允の差し向けた刺客。女の演技を侮ってはならぬよ。呂布に惚れておるかのように振る舞っていたが、あやしいぞ。董卓をヤったあと、残るは呂布でしょうが。無理に病気になって、呂布を陥れたのではなかろうか。水攻めで進退窮まり部下に裏切られてつかまった呂布が刑場にひかれてゆくとき、ちゃんとぴんぴんして出てきたではないか。最期もわざとらしく、「将軍と一緒に死にます」とかすがりついていたが、こんな
韓国ドラマ風のシーンを曹操が許すはずがない。
曹操も貂蝉と寝室で遊びたいに決まっている。ということで、曹操が「二人を引き離し、呂布だけをやってしまえ」と命じたのは当然。呂布は最期まで馬鹿なので「お前が生きていればそれでいい。あの世で会おう」とか言っていたが、誰がお前と会うかっ。というか、その前に自分が乗ってた赤兎馬に感謝の一言もないとは、まったく恩というものが分かっておらぬな。例の牛乳引きの犬みたいに、馬が天国までお供したかもしれんのに。
劉備は、前回、戦場で離ればなれになってしまった義兄弟と再会して、お手て繋いでどっかに行ったはずなのに、なぜか呂布が曹操の前に引き出されてきた場面に登場。呂布が命乞いをするのでいったせりふが実に陰険かつリスキー。「曹操殿にお願いごとがあります。呂布には三人の父がいました。丁原、董卓、王允。三人とも呂布の世話になりました。曹操殿には是非呂布の四人目の父親になってほしいのです。」無論、この三人は呂布に裏切られ悲惨な最期を遂げている。言われた曹操は当然大爆笑。(ここで、「おい劉備、おれに死ねと言うのか」とかキレないところがさすが曹操殿)……まあ、それはともかく、腹黒おホモ劉備、さすがに、戦争より女をとったかわいそうな呂布の気持ちはわからない。先祖が自慢な奴なので、父親をころころ変えた人の孤独な気持ちもわからない。(そういえば以前、呂布と一対一で戦っていた張飛が負けそうになったので、関羽と劉備が助けに行ったことがあったが、三対一とは卑怯なり。)しかし、ここでも呂布は空前のアホだったので、逆ギレして「この大耳野郎が!」と劉備をどなりつける。囚われの身で誹謗中傷はあかん。だいたいその耳は劉備のよりどころである先祖から戴いたもの。
公台は昔、曹操に仕えていた。でも曹操が、叔父一族をあっさり皆殺しにすることをみて離叛する。どうも公台は、ニーチェを読むべきだ。曹操が感じているように、世の中もっとでたらめに出来ているのだ。アホスギ呂布が正攻法で言うこと聞く訳がなかろうが……。曹操が「お前が死んだら妻や子はどうするのだ」と言うと「大丈夫だ。天命を見出すであろう」って、酷い。少しは呂布を見習って家庭を大事にしなさい。で、結局曹操が彼の家庭の世話をすることに。処刑される前の公台のせりふ「なんといい眺めだ」って、文人になった方がよかったんじゃないかな……。
曹操は、公台が処刑されるのを見届けて涙を流す。するとそばにいた一兵士が「なんで泣いてるんですか」とか言う。軍律が乱れとるのう……。曹操も「おれは泣いてない」と言い張る。なにこのお涙頂戴。私が脚本家だったら、「おれは泣いてない」と怒った曹操はついでにそのくだらない私語をした兵士を叩き切るね。そして劉備の腹黒顔をもう一回映すね。