J-CASTニュース 11/21(月) 17:33配信
蓮舫代表の夫の扱いに批判殺到 「ペット以下の存在」「そのうち居なくなる」
 自宅と家族を紹介しイメージアップを狙ったようだが・・・(画像は2016年9月13日の日本外国特派員協会での会見時)
自宅と家族を紹介しイメージアップを狙ったようだが・・・(画像は2016年9月13日の日本外国特派員協会での会見時)
二重国籍問題がくすぶり続けている民進党の蓮舫代表(48)。そのイメージアップを狙ったのか、テレビカメラを東京目黒区にある豪邸に初めて入れ、子供や母親、夫といった家族全員を紹介したところ、内容があまりにも酷すぎるとして激しい批判が起きた。
こうした番組の場合は普通、夫婦円満や家族仲の良さを強調するものだが、蓮舫氏は終始、夫で早稲田大学で非常勤講師をしている村田信之さん(50)を「ペット以下の存在」「そのうち居なくなる」などとディスり続けた。そのため、家庭内虐待が行われているのではないか、などといった噂まで立つことになった。
■「仮面夫婦なのでは?」
蓮舫代表が出演したのは2016年11月18日放送のTBS系バラエティー番組「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」。テレビカメラが入ったのは代表の母親と夫と子供が暮らす「生家」。玄関を開けると3匹の犬が出てきて吠え続けたが、それを制することなく収録が続けられた。寝室に行くとベットが2つあり、夫と別々に寝るのかと聞かれると、怪訝な顔をして「もちろんです」。一緒に寝ることは「ない」。甘えたくなることはないのか、の質問にも、
「その気持ちが無いですね。感情として」
と、ぶっきら棒に答えたため、「仮面夫婦なのでは?」といったナレーションが入った。
次に行ったのは長女(19)の部屋。蓮舫氏と村田氏には双子の男女の子供がいて、2人とも海外留学をしているが、たまたま長女が2日前に帰省したのだという。その長女は、「家の中の序列はどうなっているのか」という質問に対し、蓮舫氏がズバ抜けて上で、その下に自分達子供が来て、次はペットで、父親の地位はずっと下だと手を下げて見せた。その時に代表は娘の手を取りさらに下に下げた。
さらに、誕生日毎に家族写真を撮っている写真で、夫の髪の毛が年々薄くなっていることについても、蓮舫氏は、 「そのうちフェイドアウトするんじゃないですかね。居なくなる」 などと語った。』
日本人のよく使う言葉、遂に本性を表したと言えます。
人間性が、政治家として問われます。
出世と目的のためには、手段を選ばないマキャベリストで、今話題になっている(psychopathy、サイコパシー)の気質の持ち主では有りませんか。
最近の中国人は、近代化の下儒教の教えを忘れているのではないでしょうか。
国を治めるには必ずまずその家を斉えなければ( ととのえなければ)ならないが、自分の家さえ教えることができないのに、国の人民を統治できないの教えどおりです。
民進党も蓮舫代表で、もうお終いです。
出典『大学』の書き下し文と現代語訳:12 - Biglobe
www5f.biglobe.ne.jp › china › dai012
所謂治国必先斎其家者、其家不可教、而能教人者無之。 ... いわゆる国を治めるには必ずまずその家を斉えなければ( ととのえなければ)ならないが、自分の家さえ教えることができないのに、国の人民を統治して教えることなどとても ...儒教(儒学)の基本思想を示した経典に、『論語』『孟子』『大学』『中庸』の四書(ししょ)がありますが、ここでは儒者の自己修養と政治思想を説いた『大学』の解説をしています。『大学』は元々は大著の『礼記』(四書五経の一つ)の一篇を編纂したものであり、曾子や秦漢の儒家によってその原型が作られたと考えられています。南宋時代以降に、『四書五経』という基本経典の括り方が完成しました。
『大学』は『修身・斉家・治国・平天下』の段階的に発展する政治思想の要諦を述べた書物であり、身近な自分の事柄から遠大な国家の理想まで、長い思想の射程を持っている。しかし、その原文はわずかに“1753文字”であり、非常に簡潔にまとめられている。『大学』の白文・書き下し文・現代語訳を書いていく。
参考文献(ページ末尾のAmazonアソシエイトからご購入頂けます)
金谷治『大学・中庸』(岩波文庫),宇野哲人『大学』(講談社学術文庫),伊與田覺『『大学』を素読する』(致知出版社)
中国古典
『大学』:12(現在位置)
[白文]
所謂治国必先斎其家者、其家不可教、而能教人者無之。故君子不出家、而成教於国。孝者所以事君也。弟者所以事長也。慈者所以使衆也。
[書き下し文]
所謂国を治むるには必ず先ずその家を斎うとは、その家教うべからずして、能く人を教うる者はこれ無し。故に君子は家を出でずして、教えを国に成す。孝は君に事うる(つかうる)所以なり。弟(てい)は長(ちょう)に事うる所以なり。慈(じ)は衆を使う所以なり。
[現代語訳]
いわゆる国を治めるには必ずまずその家を斉えなければ(ととのえなければ)ならないが、自分の家さえ教えることができないのに、国の人民を統治して教えることなどとてもできないからである。そのため、君子は家を出ずに、自らの修身・斉家の徳を通じてその教えを国全体に及ぼすことができるのである。親への孝は、主君に仕える忠につながる。兄への悌は、長者に仕える順につながる。子弟への慈は、大衆を慈しむ恵につながっているという所以である。
[補足]
儒教では『治国』の基盤に『斉家』があると考えるのが基本であるが、ここでは『国を治めること』と『家を斉えること』がどのように相関しているかを分かりやすく説いている。親に孝行を尽くす斉家の徳は、主君に忠誠を尽くすという治国の『忠』の徳につながっていく。同様に、兄に対する悌という斉家の徳は、目上の人に従順に従うという治国の『順』の徳につながる。そして子弟への慈愛は、大衆への『恵』の徳を生み出す母胎となるのである。















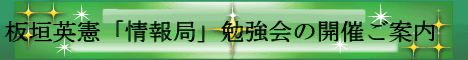







 自宅と家族を紹介しイメージアップを狙ったようだが・・・(画像は2016年9月13日の日本外国特派員協会での会見時)
自宅と家族を紹介しイメージアップを狙ったようだが・・・(画像は2016年9月13日の日本外国特派員協会での会見時)




