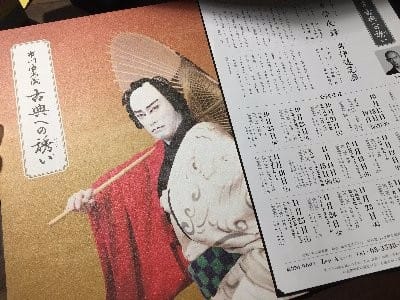友だちが彦根へ来た目的は、こちら。

※クリックすると大きくなります。
NHKの、おんな城主直虎特別展「直虎から直政へ」、
彦根城博物館で開催中の(明日まで)展示を見るためです。
ついでに彦根城を見ていこうと。
ずいぶん昔に、一度来たことがあると言うてはりました。

彦根城博物館の入り口。
直虎については、資料が少なく、不明なことが多いようで、
ドラマが始まった時に、「直虎は男」という資料が見つかったとか、
話題になりましたよね~
展示されてるものには、静岡の井伊家の史料や、
涼潭寺の南渓和尚やその弟子、昊天らの資料、
彦根藩井伊家に至るまでの美術品や古文書などが展示されてました。
昊天さんは、彦根の涼潭寺を開いた人。
直政の配下として、武装して戦っていたようですよ。
いろいろ発見があって、おもしろかったですね。

キレイなのでパチリ。
開国記念館で、410年祭の展示をしています。
時間切れで、入らなかったんですけどね。

佐和口から入るとここを登ります。
天秤櫓の石垣が見えていますね。

堀切をすすむと、左手に鐘の丸。
春は桜が見事なここも、秋は紅葉が広がります。
くるりと曲がって、天秤櫓に廊下橋。

敵が攻め込んできたときは、廊下橋を壊して敵の侵入を防ぎます。
天秤櫓は、長浜城大手門のリサイクルと言われています。
左右対称の形状から天秤櫓と呼ばれていますが、
左右の石垣が、組み方が異なっているのも特徴。
右が築城された時の打ち込みはぎ積み、左は、
江戸後期に修復されたという落とし積み。

ちょっと曇ってますが、彦根城天守。
キレイですよね~~ 種類の違う破風がカッコいいですよね。
大津城を移築したと言われてます。
この日は混んでて、入場制限がありました。
小さなお城で、階段の傾斜がきついしね。
文句をいうてるオジサンがいたんですけど、
ちょっと、ムッと来ましたね。
「並んで階段登ったのに、なんもないとこやな。
降りるために登ったようなもんや。
これで1000円も取って、ぼったくりやな」
1000円は、国の名園である「玄宮楽々園」の見学と、
410年祭の展示をしてる多聞塔(開国記念館)の見学も入ってますよ。
というか、国宝のお城ですよ。
410年前のまま、戦いのために、武装してるお城です。
鉄砲狭間や侍の隠し部屋とかありますよ。
確かに、姫路城のように大きくはないですけど。
なんもないって、城になにを期待してるんですかね。
資料館のように展示物があるのは、
大阪城とかのようにレプリカのお城ですよ。
展望台もないですけど、窓から琵琶湖が見えます。

ほんとに、残念なオジサンがいるもんです。
もっと、彦根城について勉強してからきてください!
もやもやしましたけど、天守を降りてから、
急いで、彦根城博物館のお庭の方へ。
そうです。ひこにゃんです。
登場時間が決まってるので、急がないと会えないっ!

間に合いました~~
とにかく、ゆる~く、動いてはるんで、間に合いました!
いつ見ても、いやされるますね!
デビューした頃は(10年前)ハグして、
ツーショット写真も撮れたんですけどね。
さてさて、ドラマの方は、あと3回ですって。
直虎が亡くなったのは、天正10年と史料に書かれているそうです。
天正10年といえば・・・そう、6月2日、本能寺の変がありました!
・・・その後に、亡くなるということですね。
ということは、直政は堺まで行っていた家康と一緒に、
あの「伊賀越え」をするシーンが描かれるんでしょうね。
信楽の多羅尾氏の館に宿泊して、
御斉峠のあたりを通ったようですけどね。
今週も、楽しみです~~

※クリックすると大きくなります。
NHKの、おんな城主直虎特別展「直虎から直政へ」、
彦根城博物館で開催中の(明日まで)展示を見るためです。
ついでに彦根城を見ていこうと。
ずいぶん昔に、一度来たことがあると言うてはりました。

彦根城博物館の入り口。
直虎については、資料が少なく、不明なことが多いようで、
ドラマが始まった時に、「直虎は男」という資料が見つかったとか、
話題になりましたよね~
展示されてるものには、静岡の井伊家の史料や、
涼潭寺の南渓和尚やその弟子、昊天らの資料、
彦根藩井伊家に至るまでの美術品や古文書などが展示されてました。
昊天さんは、彦根の涼潭寺を開いた人。
直政の配下として、武装して戦っていたようですよ。
いろいろ発見があって、おもしろかったですね。

キレイなのでパチリ。
開国記念館で、410年祭の展示をしています。
時間切れで、入らなかったんですけどね。

佐和口から入るとここを登ります。
天秤櫓の石垣が見えていますね。

堀切をすすむと、左手に鐘の丸。
春は桜が見事なここも、秋は紅葉が広がります。
くるりと曲がって、天秤櫓に廊下橋。

敵が攻め込んできたときは、廊下橋を壊して敵の侵入を防ぎます。
天秤櫓は、長浜城大手門のリサイクルと言われています。
左右対称の形状から天秤櫓と呼ばれていますが、
左右の石垣が、組み方が異なっているのも特徴。
右が築城された時の打ち込みはぎ積み、左は、
江戸後期に修復されたという落とし積み。

ちょっと曇ってますが、彦根城天守。
キレイですよね~~ 種類の違う破風がカッコいいですよね。
大津城を移築したと言われてます。
この日は混んでて、入場制限がありました。
小さなお城で、階段の傾斜がきついしね。
文句をいうてるオジサンがいたんですけど、
ちょっと、ムッと来ましたね。
「並んで階段登ったのに、なんもないとこやな。
降りるために登ったようなもんや。
これで1000円も取って、ぼったくりやな」
1000円は、国の名園である「玄宮楽々園」の見学と、
410年祭の展示をしてる多聞塔(開国記念館)の見学も入ってますよ。
というか、国宝のお城ですよ。
410年前のまま、戦いのために、武装してるお城です。
鉄砲狭間や侍の隠し部屋とかありますよ。
確かに、姫路城のように大きくはないですけど。
なんもないって、城になにを期待してるんですかね。
資料館のように展示物があるのは、
大阪城とかのようにレプリカのお城ですよ。
展望台もないですけど、窓から琵琶湖が見えます。

ほんとに、残念なオジサンがいるもんです。
もっと、彦根城について勉強してからきてください!
もやもやしましたけど、天守を降りてから、
急いで、彦根城博物館のお庭の方へ。
そうです。ひこにゃんです。
登場時間が決まってるので、急がないと会えないっ!

間に合いました~~
とにかく、ゆる~く、動いてはるんで、間に合いました!
いつ見ても、いやされるますね!
デビューした頃は(10年前)ハグして、
ツーショット写真も撮れたんですけどね。
さてさて、ドラマの方は、あと3回ですって。
直虎が亡くなったのは、天正10年と史料に書かれているそうです。
天正10年といえば・・・そう、6月2日、本能寺の変がありました!
・・・その後に、亡くなるということですね。
ということは、直政は堺まで行っていた家康と一緒に、
あの「伊賀越え」をするシーンが描かれるんでしょうね。
信楽の多羅尾氏の館に宿泊して、
御斉峠のあたりを通ったようですけどね。
今週も、楽しみです~~