―知識人は感情の発露をしたのだろうか?―
保坂正康はまた「あちこちで「万歳」の声が上がった。アメリカに押さえつけられて背伸びできない鬱屈感があった。特に感情の発露は知的階層に多かった。」とも書いている。
伊藤整が「あゝこれで言い、これで大丈夫だ、もう決まったのだ、…」と言ったとか。長與善郎は「国民の顔がパッと明るくなったのが印象的だ。生きているうちにこんな嬉しい、痛快、こんなめでたい日に遭えるとは思わなかった、…」と云ったとか。保坂はそういう文献の文脈から知識人の感情を想像したのであろう。
しかし、永井荷風は「10/18、この日内閣変わり、人心更に恟々たり。日米開戦の噂益々盛なり。12・8に渡米開戦の号外出づ。12/9近隣物静かになる。12/12電車やその他の広告に「屠れ英米我らの敵だ進め一億火の玉だ」、12/31除夜の鐘なるを聞かず。翌正月元日、新年賀状一枚もなきは法令ためなるべし。」と日記に事実だけを単に羅列している。
荷風は6月の段階では「米国よ。速やかに起つて、この狂暴なる民族に悔悛の機会を与へしめよ。」と書いている。
彼は当時の憲兵や特高が彼の日記を読むのを恐れて、自分の日記においてすら、感情の発露を隠したのである。
当時は正に全体主義、軍国主義の最盛期であり、軍国的でない感情の発露は控えねばならない、或いは偽らねばならなかった。そうした背景を保坂は何処まで把握して、「知的階層に感情の発露が多い」と言ったのか、その本意は理解できない。
敗戦で朝日新聞を辞めた武野武治(むのたけじ)が云うように、「国民不在のままに戦争が開始され、国民不在のままに戦争が終了させられたことだった。」という捉え方が一般的に客観的な事実であったと思う。
多くの国民にとって、何の情報も与えられない暗黒の時代と捉えるべきではないだろうか。
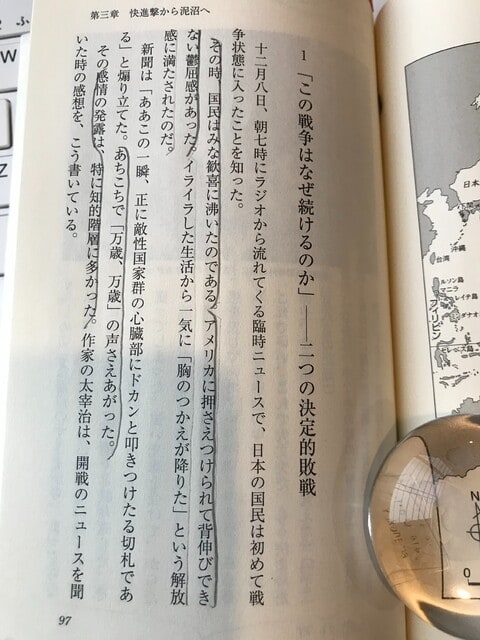
保坂正康『あの戦争は何だったのか』より
【引用文献:保坂正康『あの戦争は何だったのか』新潮新書、勝田龍夫『重臣たちの昭和史(下)』文春文庫、永井荷風『断腸亭日乗(下)』岩波文庫、鎌田慧『反骨のジャーナリスト』岩波新書】




















