原子力ルネサンスだそうだ.原子力発電は CO2発生が少ないからだそうだ.
私の直感では, CO2 さえ減らせばよいというのはあやしい.排出量取引なんて聞くだけでいかがわしいではないか.
地球温暖化はエネルギーを使用することそのものが究極の原因だろう.究極の解決策は人口を減らし,江戸時代のようにのんびり暮らすことだ.みんななんとなくそう思っているから,少子化がとまらず,「コンクリートからひとへ」という内閣が登場したのだろう.
しかしそれでは経済が活性化しない.金儲けの道が閉ざされる.そこで利口な人たちが,CO2 へと問題をすり替えた...というのが,私なりのうがった見方.科学的根拠はないが,この問題に関しては,おおかたの科学的根拠が疑問.
いまのところ CO2 削減はエネルギー利用の効率化を意味しており,それはそれで悪くはない.しかしいずれエネルギー使用そのものが問題として顕在化するだろう.
そうなったとき残っているのは,原子力発電が遺した放射性廃棄物という「負の遺産」だけ?
原子力はパンドラの函と言われたが,この函はもう開いている.廃棄物処理とか古い原子炉を廃炉とするという問題に直面せざるを得ない時代が来ている.しかしこうした,いわばネガティブな問題に対処する技術者は養成されているのだろうか.
半世紀ちかく前,国立大学にはつぎつぎと「原子力工学科」が誕生した.しかし,原子力に逆風が吹くと,次々と姿を消した.場当たり的に対処して来たツケが回ってきて,「技術がない・優秀な技術者がいない」ということになっているのでは.
東大大学院の工学系研究科原子力国際専攻はじめ,あちこちの大学で「原子力」が復活している.けっこうなことである.しかし学生さんには半世紀前のようなバラ色の夢はない.彼らを待っているのは公害処理・予防という地味な使命である.
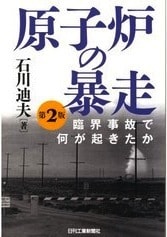
さて,この本は
石川 迪夫 「原子炉の暴走―臨界事故で何が起きたか」日刊工業新聞社; 第2版 (2008/03)
原子力推進派の原子炉事故の解説書.著者はもとの原研東海研究所から北大教授をへて,退職後は政府関係のいろいろな委員や顧問を歴任.
前半の,たとえ話などを随所にまじえた原子炉工学の解説は平易でよく理解できる (それにしても,私が学生だった頃の先生は講義がへたであった).技術者の反応度事故防止への取り組みには頭が下がるし,事故の確率は減少したし,これからも減少するだろう.
後半は原子力反対派とマスコミへの敵意が丸出しで鼻白む.
ご説に従えば,PWR,BWR では重大事故は起きる訳がなく,安全評価はあり得ない前提のもとでのシミュレーションを求めており,チェルノブイリ事故は旧式の原子炉を程度の低い運転員が操作したために起きたということになる.北陸電力志賀原子力発電所の臨界事故は,ずーっと黙っていればよかったのに...ということらしい.
事故がゼロだとしても (ゼロになるとは誰も断言出来ないと思うが),原子力発電に放射性廃棄物という大問題があることに変わりはないとは,当然かもしれないが,この本には書いてない.
私の直感では, CO2 さえ減らせばよいというのはあやしい.排出量取引なんて聞くだけでいかがわしいではないか.
地球温暖化はエネルギーを使用することそのものが究極の原因だろう.究極の解決策は人口を減らし,江戸時代のようにのんびり暮らすことだ.みんななんとなくそう思っているから,少子化がとまらず,「コンクリートからひとへ」という内閣が登場したのだろう.
しかしそれでは経済が活性化しない.金儲けの道が閉ざされる.そこで利口な人たちが,CO2 へと問題をすり替えた...というのが,私なりのうがった見方.科学的根拠はないが,この問題に関しては,おおかたの科学的根拠が疑問.
いまのところ CO2 削減はエネルギー利用の効率化を意味しており,それはそれで悪くはない.しかしいずれエネルギー使用そのものが問題として顕在化するだろう.
そうなったとき残っているのは,原子力発電が遺した放射性廃棄物という「負の遺産」だけ?
原子力はパンドラの函と言われたが,この函はもう開いている.廃棄物処理とか古い原子炉を廃炉とするという問題に直面せざるを得ない時代が来ている.しかしこうした,いわばネガティブな問題に対処する技術者は養成されているのだろうか.
半世紀ちかく前,国立大学にはつぎつぎと「原子力工学科」が誕生した.しかし,原子力に逆風が吹くと,次々と姿を消した.場当たり的に対処して来たツケが回ってきて,「技術がない・優秀な技術者がいない」ということになっているのでは.
東大大学院の工学系研究科原子力国際専攻はじめ,あちこちの大学で「原子力」が復活している.けっこうなことである.しかし学生さんには半世紀前のようなバラ色の夢はない.彼らを待っているのは公害処理・予防という地味な使命である.
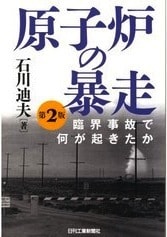
さて,この本は
石川 迪夫 「原子炉の暴走―臨界事故で何が起きたか」日刊工業新聞社; 第2版 (2008/03)
原子力推進派の原子炉事故の解説書.著者はもとの原研東海研究所から北大教授をへて,退職後は政府関係のいろいろな委員や顧問を歴任.
前半の,たとえ話などを随所にまじえた原子炉工学の解説は平易でよく理解できる (それにしても,私が学生だった頃の先生は講義がへたであった).技術者の反応度事故防止への取り組みには頭が下がるし,事故の確率は減少したし,これからも減少するだろう.
後半は原子力反対派とマスコミへの敵意が丸出しで鼻白む.
ご説に従えば,PWR,BWR では重大事故は起きる訳がなく,安全評価はあり得ない前提のもとでのシミュレーションを求めており,チェルノブイリ事故は旧式の原子炉を程度の低い運転員が操作したために起きたということになる.北陸電力志賀原子力発電所の臨界事故は,ずーっと黙っていればよかったのに...ということらしい.
事故がゼロだとしても (ゼロになるとは誰も断言出来ないと思うが),原子力発電に放射性廃棄物という大問題があることに変わりはないとは,当然かもしれないが,この本には書いてない.
















