【社説①】:週のはじめに考える 都議会を討論の広場に
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:週のはじめに考える 都議会を討論の広場に
四年に一度の蜃気楼(しんきろう)−。こう皮肉られるのが地方議会です。選挙になると一票のお願いに姿を現すが、普段の活動は見えにくい。二十五日の東京都議選告示を前に、その存在意義を考えます。
札幌市から車で約一時間。北海道栗山町は、人口約一万一千人の自治体です。
この町で二〇〇六年、画期的な条例が制定されました。全国初の「議会基本条例」です。
議会の理念を定め、町民や町長との関係、議会の機能強化や情報公開などを盛り込んだ、議会運営の最高規範です。
きっかけは議員らの危機感でした。「住民は困り事があれば行政を頼るでしょう? 議会は頼られていなかった」。鵜川(うかわ)和彦議長(65)が振り返ります。
議会の存在感を高めるための自己改革が始まりました。
◆基本条例の制定急げ
柱の一つは住民に情報を公開し、議会参画を促す試みです。全議員が三班に分かれ、町内各地で議会報告会を開きました。請願・陳情が出れば必ず提案者の意見を聞き、議会運営の提言をするモニター制度も導入しました。
もう一つは、議会の機能強化。町の基本構想や基本計画を、議決の対象に加えました。質疑を活発にするため、町側が議員に逆質問できるようにし、議員同士の討議も拡充しました。
「住民の声を聞くことが当たり前になりました。町との質疑も緊張感を伴います」と鵜川さん。
この改革を明文化したのが栗山町議会基本条例です。住民と行政を巻き込んで地域を活性化するツールとして、この十五年間で各地に広がりました。
早稲田大学マニフェスト研究所が二〜三月に行った調査によると、全国約千七百の地方議会のうち、少なくとも八百八議会が基本条例を制定しています。
議会による政策立案が盛んになり、先進的な運営も見られます。例えば、年間を通じて開催できる「通年議会」(静岡県藤枝市)。政党・会派ごとでなく、委員会ごとに行政側をただす「委員会代表質問」(岐阜県可児(かに)市)。コロナ禍で条例化した「オンライン委員会」(茨城県取手市)…。
基本条例は都道府県でも神奈川、愛知など三十二議会が制定済みですが、東京にはありません。都議会=写真=のこの四年間の改革は、飲食を伴う会合への政務活動費の支出禁止など当然の内容が多く、遅れています。
大胆な改革を進め、基本条例の制定を加速するべきです。
住民ニーズが複雑化・多様化する中、税金の使い道や暮らしの行方を首長に一任するわけにはいきません。地方自治体は、首長と議会がともに住民の選挙で選ばれる二元代表制。議会は首長と対等の立場に立ち、住民にとって最良の結論を導く力量を備えていなければならないからです。
残念ながら、現実の都議会には疑問符が付く。根深い問題は、知事や行政とのなれ合いです。
◆住民参画と機能強化
本来は是々非々で臨むべきですが、長く自民党中心の与党が存在し、今は都民ファーストの会が中心です。知事に協力する代わりに、政策決定や議会質問で野党より優遇してもらえる。これでは正常なチェック機能は働きません。
昨年来、新型コロナウイルス対策で小池百合子知事が行った専決処分は約二十回に及びます。緊急時に議決を経ないで済む手続きで、予算総額は一兆円超です。
臨時議会開催や特別委員会設置を求めた野党に対し、与党は後ろ向きでした。こうして議論の乏しいまま知事の言い分が通り続ければ、都議会の意義は失われます。都民の不利益や税金の無駄遣いにつながりかねません。
単に与党として、または野党として存在感を発揮するのではなく、都議会一体となり知事に向き合わねばなりません。幅広い住民の参画を仰ぎ、議会機能を強化する改革を目指すべきで、その指針となるのが基本条例です。
全国の条例の原点となった栗山町は、議会を「討論の広場」と位置付けました。都議会を真の広場にできるか。議会改革は、都議選の大事な争点です。
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2021年06月20日 06:52:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。
















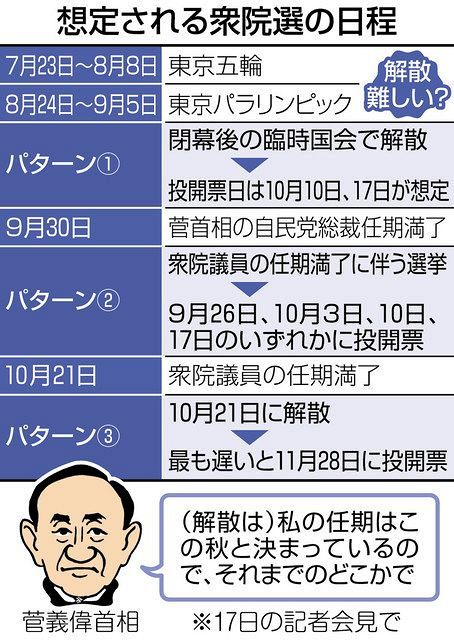



![豊田商事会長刺殺事件の真相とは?永野一男や犯人&残党の現在まとめ[放送事故]のイメージ](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/static.cdn.xtreeem.com/production/posts/eyecatches/000/002/037/original.jpg?1504216328)




