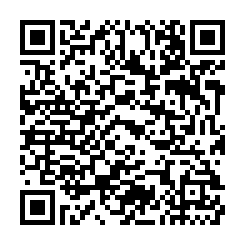現在執筆中の小説の冒頭を抜粋しました。
1973年の4月から11月までの京都を舞台に、主人公の青春模様を活写しています。
当時の社会現象や出来事、河原町や同志社大学界隈の懐かしい店々など、京都に住んだことがある方にはもちろん、訪れたことのある方にも面白く読んでいただける小説です。
本書は近日中にAmazon Kindle Storeから発売予定です。
『1973 追憶の京都』(仮題)
その期間や内容はそれぞれだが、人には等しく青春というものが存在する。
青春に限らず、朱夏や白秋もあるだろうが、ここでは青春について述べる。
それはほとばしる情熱や歓喜の期間だったり、あるいはほろ苦い思いや挫折の期間だったり、それらが入りまじった混沌の期間だったりする。
それをリアルタイムで体感、実感する者もいるだろうし、無意識にすごし、あとになって気づいたり追想したりする者もいるだろう。
大学一回生の沢井俊介にとって、まさに今がその青春ということになる。
昭和四十八年四月から、俊介の京都でのひとり暮らしの大学生活は始まった。
大阪万博で日本は世界にその経済力を示し、田中角栄が昨年発表した『日本列島改造論』に基づいた全国の土地開発ラッシュで、当分、今の好景気は続いていくだろう。
その好景気の中で俊介の大学生活もバラ色になるはずだ。
昔聴いた『憧れのハワイ航路』の歌が思わず口に出る。
晴れた空、そよぐ風、望み果てない大学生活の潮路だ。
小学生の時に見たテレビドラマの『青春とはなんだ』や『これが青春だ』では、スポーツに明け暮れる高校生活が青春だったし、映画の『若大将シリーズ』では、スポーツや音楽プラス恋愛の大学生活が青春だった。
しかしスポーツや恋愛とは無縁だった俊介の田舎での高校生活は、テレビや映画で見る青春とはほど遠いものだった。
生まれ育った兵庫の山奥でも、情報だけはテレビやラジオ、週刊誌などを通して入ってきたが、いかんせん、田舎の高校生活の中に、その情報を活用できる環境は整っていなかった。都会で流行りのファッションをしようにも、そんな服を売っている店はないし、最新のヒットチャートのレコードを買おうにも、一時間以上かけて町のレコード店まで行かなくてはならなかった。よしんば、そんな奇異なファッションをしたところで笑いものになるだけだろうし、歌謡曲くらいしか知らない同級生たちに、クリームやレッド・ツェッペリンの話をしても煙たがられるだけだった。
ならば、大学四年間こそがバラ色の青春を謳歌すべき期間だと自分に言いきかせ、高校三年の一年間は受験勉強はもちろん、『平凡パンチ』や『プレイボーイ』から最新の若者文化の情報を収集することもおこたりなかった。
また雑誌の通信販売で買ったフォークギターの上達にも力を注いだ。
スポーツ万能の若大将みたいな運動神経のない自分にしてみたら、青春のもうひとつの彩り、音楽に懸けるしかないと考えたからだ。
女にモテるためには、スポーツマンかミュージシャンの二者択一しかない。スポーツマンになれない俊介にとって、手っとり早くミュージシャンになるためには、ギターが必須アイテムだった。若大将はもちろん、巷で流行りのフォークの貴公子、吉田拓郎もギターで女をとりこにしているではないか。
そんなわけで、俊介は受験勉強とおなじくらいの情熱で、『ヤングセンス』や『ガッツ』といったギターのバイブルをもとに日々練習に励んだ。その甲斐あってか、Fコードの壁もなんとか乗り越え、今ではコードネーム付きの楽譜さえあれば、その巧拙はさておき、ほとんどの曲は弾き語りできるようになった。
肝心の大学のほうも、第一志望の同志社大学文学部英文学科に見事合格した。
英文学科を選んだのは、もちろん英語にも興味はあったが、それ以上に、ほかの学部や学科にくらべて女子学生が格段に多いという不埒な理由からだ。(To be continue)
1973年の4月から11月までの京都を舞台に、主人公の青春模様を活写しています。
当時の社会現象や出来事、河原町や同志社大学界隈の懐かしい店々など、京都に住んだことがある方にはもちろん、訪れたことのある方にも面白く読んでいただける小説です。
本書は近日中にAmazon Kindle Storeから発売予定です。
『1973 追憶の京都』(仮題)
その期間や内容はそれぞれだが、人には等しく青春というものが存在する。
青春に限らず、朱夏や白秋もあるだろうが、ここでは青春について述べる。
それはほとばしる情熱や歓喜の期間だったり、あるいはほろ苦い思いや挫折の期間だったり、それらが入りまじった混沌の期間だったりする。
それをリアルタイムで体感、実感する者もいるだろうし、無意識にすごし、あとになって気づいたり追想したりする者もいるだろう。
大学一回生の沢井俊介にとって、まさに今がその青春ということになる。
昭和四十八年四月から、俊介の京都でのひとり暮らしの大学生活は始まった。
大阪万博で日本は世界にその経済力を示し、田中角栄が昨年発表した『日本列島改造論』に基づいた全国の土地開発ラッシュで、当分、今の好景気は続いていくだろう。
その好景気の中で俊介の大学生活もバラ色になるはずだ。
昔聴いた『憧れのハワイ航路』の歌が思わず口に出る。
晴れた空、そよぐ風、望み果てない大学生活の潮路だ。
小学生の時に見たテレビドラマの『青春とはなんだ』や『これが青春だ』では、スポーツに明け暮れる高校生活が青春だったし、映画の『若大将シリーズ』では、スポーツや音楽プラス恋愛の大学生活が青春だった。
しかしスポーツや恋愛とは無縁だった俊介の田舎での高校生活は、テレビや映画で見る青春とはほど遠いものだった。
生まれ育った兵庫の山奥でも、情報だけはテレビやラジオ、週刊誌などを通して入ってきたが、いかんせん、田舎の高校生活の中に、その情報を活用できる環境は整っていなかった。都会で流行りのファッションをしようにも、そんな服を売っている店はないし、最新のヒットチャートのレコードを買おうにも、一時間以上かけて町のレコード店まで行かなくてはならなかった。よしんば、そんな奇異なファッションをしたところで笑いものになるだけだろうし、歌謡曲くらいしか知らない同級生たちに、クリームやレッド・ツェッペリンの話をしても煙たがられるだけだった。
ならば、大学四年間こそがバラ色の青春を謳歌すべき期間だと自分に言いきかせ、高校三年の一年間は受験勉強はもちろん、『平凡パンチ』や『プレイボーイ』から最新の若者文化の情報を収集することもおこたりなかった。
また雑誌の通信販売で買ったフォークギターの上達にも力を注いだ。
スポーツ万能の若大将みたいな運動神経のない自分にしてみたら、青春のもうひとつの彩り、音楽に懸けるしかないと考えたからだ。
女にモテるためには、スポーツマンかミュージシャンの二者択一しかない。スポーツマンになれない俊介にとって、手っとり早くミュージシャンになるためには、ギターが必須アイテムだった。若大将はもちろん、巷で流行りのフォークの貴公子、吉田拓郎もギターで女をとりこにしているではないか。
そんなわけで、俊介は受験勉強とおなじくらいの情熱で、『ヤングセンス』や『ガッツ』といったギターのバイブルをもとに日々練習に励んだ。その甲斐あってか、Fコードの壁もなんとか乗り越え、今ではコードネーム付きの楽譜さえあれば、その巧拙はさておき、ほとんどの曲は弾き語りできるようになった。
肝心の大学のほうも、第一志望の同志社大学文学部英文学科に見事合格した。
英文学科を選んだのは、もちろん英語にも興味はあったが、それ以上に、ほかの学部や学科にくらべて女子学生が格段に多いという不埒な理由からだ。(To be continue)