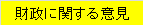日本の高度成長を支えた団塊の世代が大学生の頃、国立大学の授業料は年間12000円であった。当時の親の収入を考慮しても破格の安さであり、この安い授業料が地方に住んでいる金のない家庭の子息でも優秀であれば大学に進学することを可能にした。
能力ある多くの若者であれば住所や親の収入に関係なく国立大学で高等教育をうけられる環境を提供していたのである。
しかし、財政健全化第一主義の財務省とそれに追随した文部省により、大学への資金補助が減少し授業料が高騰した。
現在では、国立大学といえども普通の家庭が東京の大学に通わせることは困難になっており、一方大学も今の授業料では運営が難しくなっている。
毎日新聞が実施した授業料のあり方に関する国立大アンケートの結果からは、多くの大学が物価や人件費の高騰にあえぎながら学生の負担を考慮して授業料を上げずにいる実態が垣間見える。
アンケートに回答した78大学のうち、授業料の値上げを検討していると回答したのは既に値上げを発表した東大を含む5大学にとどまった。値上げを検討していないと回答した大学は72大学と大半を占める。検討しない理由としては44大学が「学生や保護者の負担が避けられない」、34大学が「志願者・入学者が減る懸念がある」を挙げた。一方で、国から配分される運営費交付金は、回答した78大学中70大学が増額を求めている。
国が大学への支援を減額した結果、大学の経営が苦しくなり、同時に学生や保護者の負担が厳しくなっており、ある程度以上の収入が無いと能力があっても大学進学が困難となっている。
資源の無い日本の国力の要は人材である。人材育成の為にせめて国立大学の授業料は大幅に下げ、能力ある者が大学教育をうけられるようにすべきである。
能力ある多くの若者であれば住所や親の収入に関係なく国立大学で高等教育をうけられる環境を提供していたのである。
しかし、財政健全化第一主義の財務省とそれに追随した文部省により、大学への資金補助が減少し授業料が高騰した。
現在では、国立大学といえども普通の家庭が東京の大学に通わせることは困難になっており、一方大学も今の授業料では運営が難しくなっている。
毎日新聞が実施した授業料のあり方に関する国立大アンケートの結果からは、多くの大学が物価や人件費の高騰にあえぎながら学生の負担を考慮して授業料を上げずにいる実態が垣間見える。
アンケートに回答した78大学のうち、授業料の値上げを検討していると回答したのは既に値上げを発表した東大を含む5大学にとどまった。値上げを検討していないと回答した大学は72大学と大半を占める。検討しない理由としては44大学が「学生や保護者の負担が避けられない」、34大学が「志願者・入学者が減る懸念がある」を挙げた。一方で、国から配分される運営費交付金は、回答した78大学中70大学が増額を求めている。
国が大学への支援を減額した結果、大学の経営が苦しくなり、同時に学生や保護者の負担が厳しくなっており、ある程度以上の収入が無いと能力があっても大学進学が困難となっている。
資源の無い日本の国力の要は人材である。人材育成の為にせめて国立大学の授業料は大幅に下げ、能力ある者が大学教育をうけられるようにすべきである。