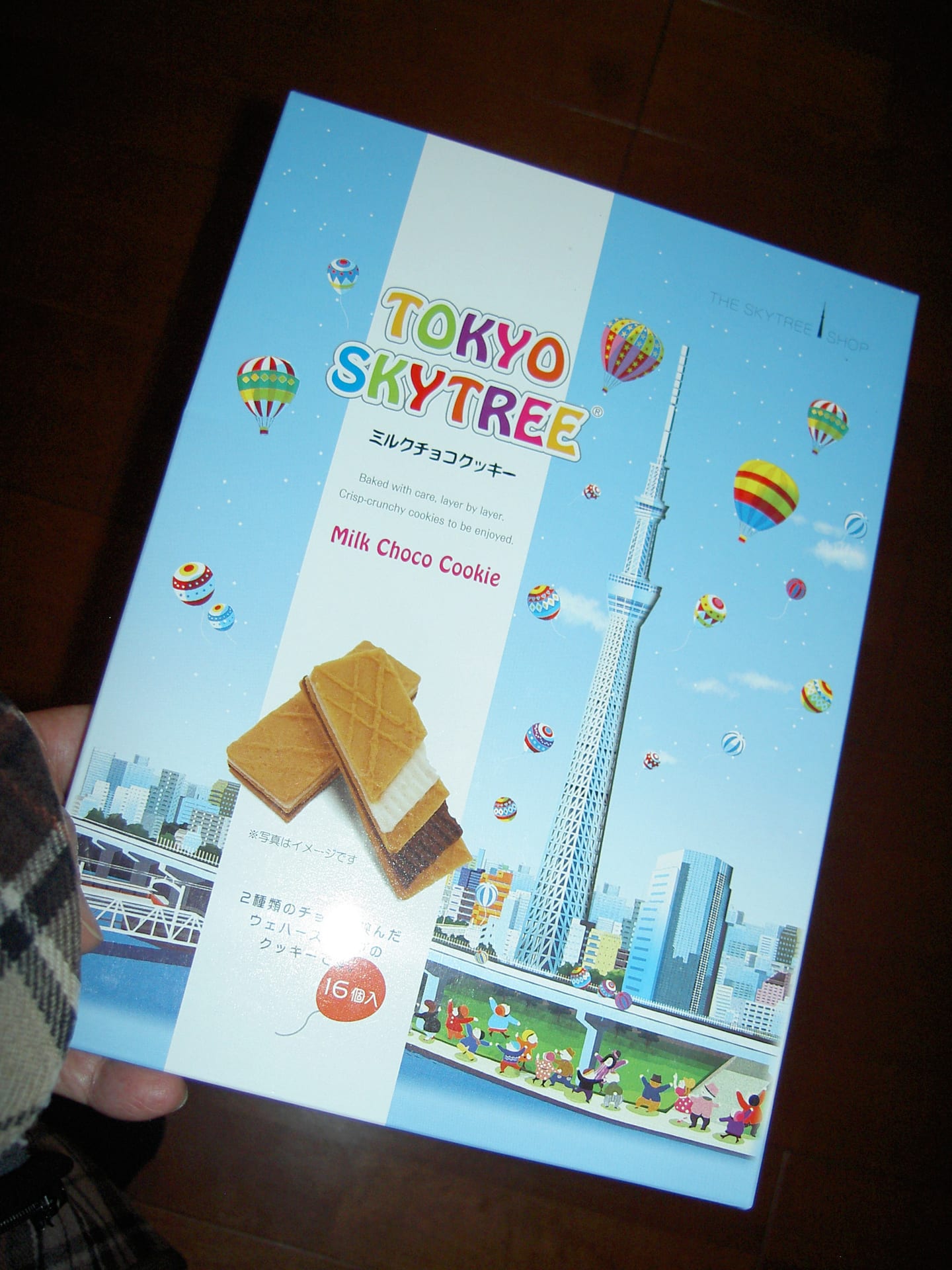十勝、早春のブラウン その壱
20XX-4-17(土) 晴れ 10°C.
朝8時にF氏と二人で北見市を出発。十勝の広大な畑作地帯を流れる川に繁殖しているブラウントラウトを見に行った。
途中の峠道は鹿撃ち禁猟区になっているせいか10頭ほどの雌鹿の群がいた。

鹿たちは突然何の前ぶれもなく道路に飛び出し、車と激突することは稀ではない。鹿の飛び出しにとりわけ注意しながら峠を越えた。まだ十勝の連山は雪が多い。里にでるとあちこちで伐採地跡の野焼きをやっていた。

北見市から約2時間で十勝の大畑作地帯を流れる目的の川に着いた。上流から源流域にかけては、川というよりは畑作地帯の中を直線的に流れる純人工的な水路のようにも見える。どうみても本来の自然河川とは言い難い。
各所に低い落差工がありその下は広い水深のあるたまりを形成している。夏場にはしばしば、そこを回遊する大型ブラウンの群もみられる。
水温は9℃。水はきれいで水量も落ち着き岸辺にはフキノトウが沢山出ている。岸辺の雪はほとんど解けていた。いかにもブラウンがいそうな感じでさっそく釣り始めたが生体反応なし。昨年もそうであったが、この時期、ブラウンの活性がほとんどないかのように見える。
普段、釣り人は見かけない川だがこの日は違った。橋という橋の付近には釣り人の車が停まっており、私の北見ナンバーをはじめ帯広ナンバーのみならず釧路や室蘭ナンバーの車まで種々あった。
地元釣り人のみならず北海道各地からフライマンやアングラーがここにブラウン釣りにきているようだ。
土曜日のせいだろうか、少なくとも15人の釣り人が確認できた。またここぞというポイントは釣り人の踏み跡だらけ。川岸にはしっかりと獣道みたいに釣り人の通り道が出来ていた。
この時期、他にターゲットとなるトラウトが少ないせいかも知れないが、ブラウン釣りにこんなに沢山の釣り人が集結するとは驚きだ。
色々意見もあるようだが現実の世界では、ブラウン釣りは人気があることは明白だ。
これだけ釣り人がいると悲しいかな、けっこうマナーの悪いのもいて、釣りエサやルアーの容器、食べ物のゴミなどあちこちに散乱していて目にあまる。

引き続き、比較的釣り人の入っていないと思われる場所を中心に入念にさぐったがまったく魚信なかった。
ブラウンの活性が低いのか多数の釣り人にいじめられているのかはわからないがとにかく釣れない。あちこち探り歩き、やっと釣り人の気配が無くなってきたころ、ぽつぽつと小型ブラウンがかかりはじめた。


























この項 続く。