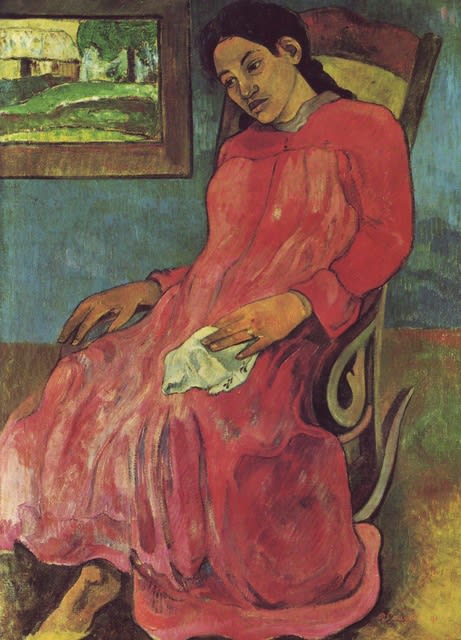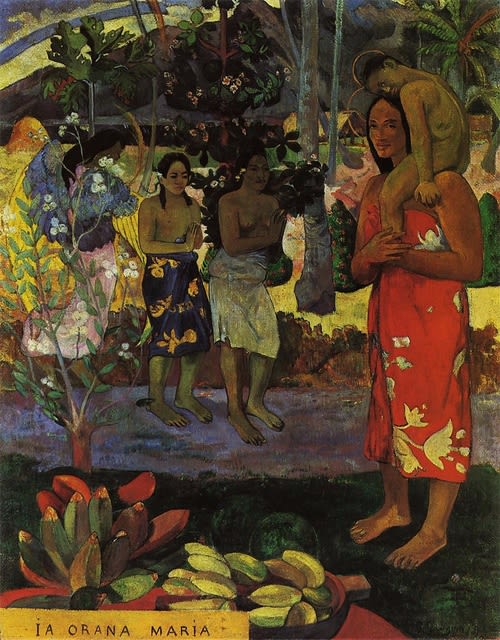美幌川水系源流にオショロコマを捜して50年、いまだ発見できず。
20XX-11-2 (土) 晴れ のち曇り 寒い
朝10:10 朝カップ麺を食べ 北見市を 出発。
釧路川水系支流源流域で遡上大型アメマスを撮影したあと、久しぶりに網走川水系美幌川の源流の支流のひとつでオショロコマを捜してみた。

美幌川水系源流域は何本もの支流があり、深い谷底を流れる支流も多く、しばしば川に到達するのもむずかしいことがある。
これらの支流をシラミつぶしに調査してオショロコマを捜しているが、これまで50年かかっても美幌川水系全域は調べ尽くすことができないでいる。
おびただしい数の小型アメマスがどの支流にもいるがオショロコマは発見出来ない。
支流によってはヤマベが混生しているがアメマスと較べるととても少ない。
この日、美幌川源流域にしては川の水量は意外と多かった。
ダラダラした浅い流れが主体でたまりが少ないがちょっとしたたまりには沢山のエサ取り名人シンコヤマベがいた。

源流に向かってすすみ途中のたまりで シンコヤマベと3年魚ヤマベ少しと、アメマス幼魚〜若魚をかなり釣った。






最後に左沢沿いの道を登ってゆくと滝がありその右手支流のダム下でアメマス、 滝下でもアメマス、ヤマベを釣って終了。









ずいぶん昔のことだが、このダム下に晩秋の頃、大型アメマスが群れていたことがあるが、その後は見ていない。
アメマスは小型のエゾイワナ化したもの多い。美幌川の常で在来の大型アメマスは滅多にみられない。




ダムの上はかなりのダム湖みたいで、その上流は深い谷底を流れ、もしかするとオショロコマがいないだろうかと思うが入って行くのはかなりの決心が必要で今日はパス。
この支流沿いに登ると 小規模な滝が続き、その上はやがてチョロ川になり引き返す。

ウェーダー、両足ともどこか穴が空いたようで冷水が入ってきて両足ぐしょぬれ。
それで戦意喪失し、早めに川をあがって6時過ぎに北見にもどった。
この日も、美幌川水系源流でオショロコマを発見することは出来なかった。

アメマスやヤマベのなかには産卵行動に参加した痕跡を示す個体も多かった。
撮影させていただいた渓流魚たちは全て丁寧にもとの場所にリリースしました。

きょうは かなり疲れたが かみさんが鳥肉と野菜を入れてエノキタケおじやを作った。
エノキタケはこの時期オホーツクではとても多いおいしいキノコでこの日かなり収穫した。
エノキタケのつるつる食感は久しぶりでおいしい。