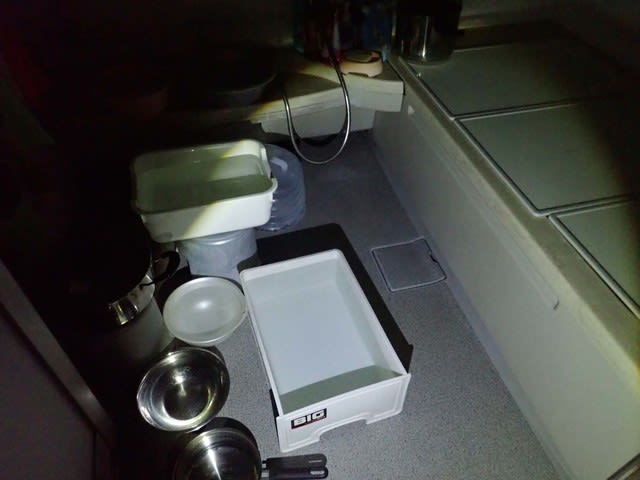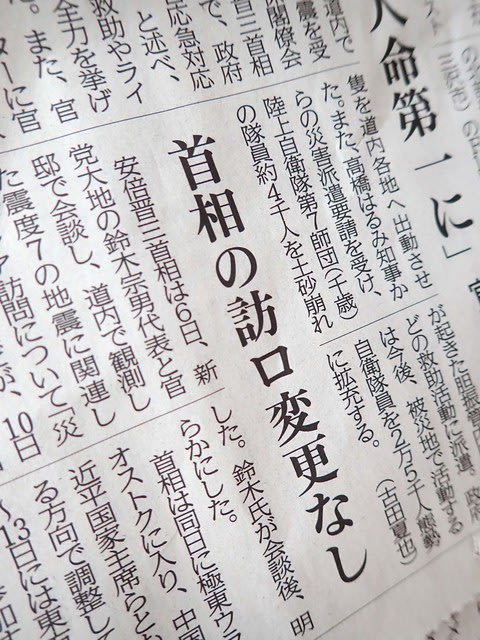湿原のオショロコマと降海型ニジマス 新緑、クロユリと水草が美しい超美麗渓流、
201X-6-11(土) 曇り のち晴れ 暖かい
この日、N川水系のとある支流に湿原のオショロコマを見にいった。

文字通り、超美麗渓流、心が洗われるようなたぐいまれな美しい渓流である。

いっぽう初夏の木々の緑が茂り草丈も高くなり早春のころよりは歩きにくい。


美しい金魚藻がびっしり川面を覆ってで水面が見えないところが多く、餌をその隙間にうまく流し込んで魚を誘うのだが、けっこう技術が必要である。


この水域は深いたまりは無くて比較的浅いが、思いのほか流速がある流れで足下の小砂利がみるみる流され足下がぐらりとくるので要注意。
この日は小型オショロコマが多く、また釣れる魚の数もそう多くはなかった。






岸辺のいたるところにある湿地に足をいれると底なし沼みたいに、ずぶーっと沈んで脱出するのに一苦労。
転倒でもしようものなら一人ならおぼれてしまうかもしれない。
川の中を歩くと激しく濁るのでこれまた釣りにならないので岸つたいに釣り下るしかない。


今日は クロユリが満開でいたるところに咲いていてまるで別世界のようだ。クロユリをかなり撮影した。

クロユリは恋の花と歌われるロマンチックなイメージの花だが、この曲の作詞者はクロユリのことをまったく知らないのだと思う。

歌の歌詞のなかでは、愛する人にささげれば必ず恋はかなうとされるが、もしこの花の臭いを嗅いだならあまりの悪臭にのけぞってしまいます。

クロユリはこのひどい悪臭に集まるギンバエを利用して受粉するのです。
恋は、かなうどころか、たちまち終わること間違いありませんん。
川を再び釣り登って帰るのは大変なので岸が牧草地に近づいたところで崖をよじ登って川から上がった。

牧草地はタンポポの花が終わり綿毛がみわたすかぎりあって壮観であった。

タンポポはすべて攻撃的外来種セイヨウタンポポで在来種のエゾタンポポは見あたらなかった。


少し上流のリンドウの群落があるところからまた川に入った。
夏場はうっそうとして、底なし沼様の川岸で閉口するのだが今日は水量がいつもより少なく、ヨシなどの川岸の草がなく見通しがよいのでいつもは入って行かない上流方向へ川岸をつたって釣り登ってみた。


オショロコマ若魚が5匹、ニジマス若魚3匹が釣れた。










ニジマスはこの川特有の白っぽい個体で恐らくスチールヘッド系の種苗だろうか。


体形が細くなり、ウロコが銀色を帯びるようになり、ヒレが透明化し、辺縁が黒化して、渓流のトラウトたちがギンケ化して降海型となるときの一般的な外見的変化を示している。

このほか魚体がずんぐりして赤い帯が鮮やかな別の種苗と思われる一般的な外観のニジマスもみられる。


この湿原の渓流では、この10数年、ニジマスとオショロコマの力関係には変化がなく、いくつかの理由で他の水系のようにオショロコマが一方的に圧倒されている気配はない。
この水域も、やはり川岸はぬかりやすく危険を感じ100mほどで引き返した。
帰りに時期遅れだが依然おいしそうなコゴミと新鮮な水草クレッソンも少し採集した。