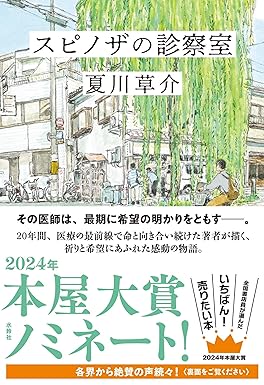
「スピノザの診察室」
和菓子と哲学をこよなく愛する町医者が、終末期の患者と向き合う日々を通して生と死を問う、静かな感動作。
大学病院での熾烈なエリート競争から訳あって抜け出し、姥捨て山のような地域病院に自転車で通い、老人たちを看取る雄町医師(マチ先生)。周囲からは惜しまれていたが、本人は充足した日々を過ごしていた。
「たとえ病が治らなくても、仮に残された時間が短くても、人は幸せに過ごすことができる。できるはずだ、というのが私なりの哲学でね。そのために自分ができることは何かと、私はずっと考え続けているんだ」
京都の街並み、そして矢来餅、阿舎利餅、長五郎餅、赤福、梅が枝餅といった、マチ先生が好きな和菓子が色々出てくるのが楽しい。
映画化が決定したようです。

「大使とその妻」
世界がパンデミックに覆われた2020年、軽井沢に住むアメリカ人の翻訳家ケヴィンは、隣家の元外交官夫妻と親しくなる。能を舞い、たおやかに着物を着こなす典雅な夫人、貴子には意外な出生の秘密があったが、夫妻は突然消息を絶ってしまった。ケヴィンは貴子の数奇な半生を、日本語で書き残そうと決意する。
その夫がケヴィンに語った言葉が、印象に残りました。
「あのまれびとは、どうも月に住んでる人たちと交信してるようなんですよ。そんな時に約束を破って邪魔しちゃあいけないと思ってね」
「(能は)舞台芸術である以前に、祈りのようなもんらしいですよ。舞い降りてくる神様にじぶんの芸を捧げてね、自分がこうして生きていることのありがたさって言うのかな。そんなようなものを感じながら、死んでしまった人たちの鎮魂を祈る…」
こんな言葉をもっと前に聞いていたら、私も能楽をもっと楽しめたのにね?
和菓子と哲学をこよなく愛する町医者が、終末期の患者と向き合う日々を通して生と死を問う、静かな感動作。
大学病院での熾烈なエリート競争から訳あって抜け出し、姥捨て山のような地域病院に自転車で通い、老人たちを看取る雄町医師(マチ先生)。周囲からは惜しまれていたが、本人は充足した日々を過ごしていた。
「たとえ病が治らなくても、仮に残された時間が短くても、人は幸せに過ごすことができる。できるはずだ、というのが私なりの哲学でね。そのために自分ができることは何かと、私はずっと考え続けているんだ」
京都の街並み、そして矢来餅、阿舎利餅、長五郎餅、赤福、梅が枝餅といった、マチ先生が好きな和菓子が色々出てくるのが楽しい。
映画化が決定したようです。

「大使とその妻」
世界がパンデミックに覆われた2020年、軽井沢に住むアメリカ人の翻訳家ケヴィンは、隣家の元外交官夫妻と親しくなる。能を舞い、たおやかに着物を着こなす典雅な夫人、貴子には意外な出生の秘密があったが、夫妻は突然消息を絶ってしまった。ケヴィンは貴子の数奇な半生を、日本語で書き残そうと決意する。
その夫がケヴィンに語った言葉が、印象に残りました。
「あのまれびとは、どうも月に住んでる人たちと交信してるようなんですよ。そんな時に約束を破って邪魔しちゃあいけないと思ってね」
「(能は)舞台芸術である以前に、祈りのようなもんらしいですよ。舞い降りてくる神様にじぶんの芸を捧げてね、自分がこうして生きていることのありがたさって言うのかな。そんなようなものを感じながら、死んでしまった人たちの鎮魂を祈る…」
こんな言葉をもっと前に聞いていたら、私も能楽をもっと楽しめたのにね?










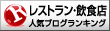
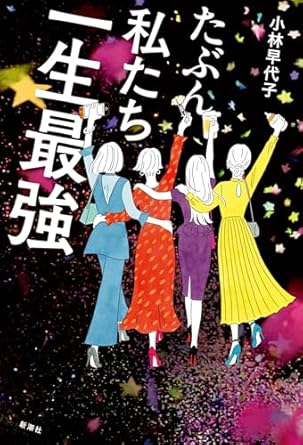

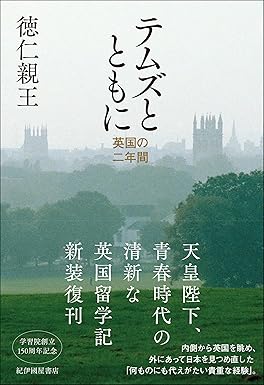





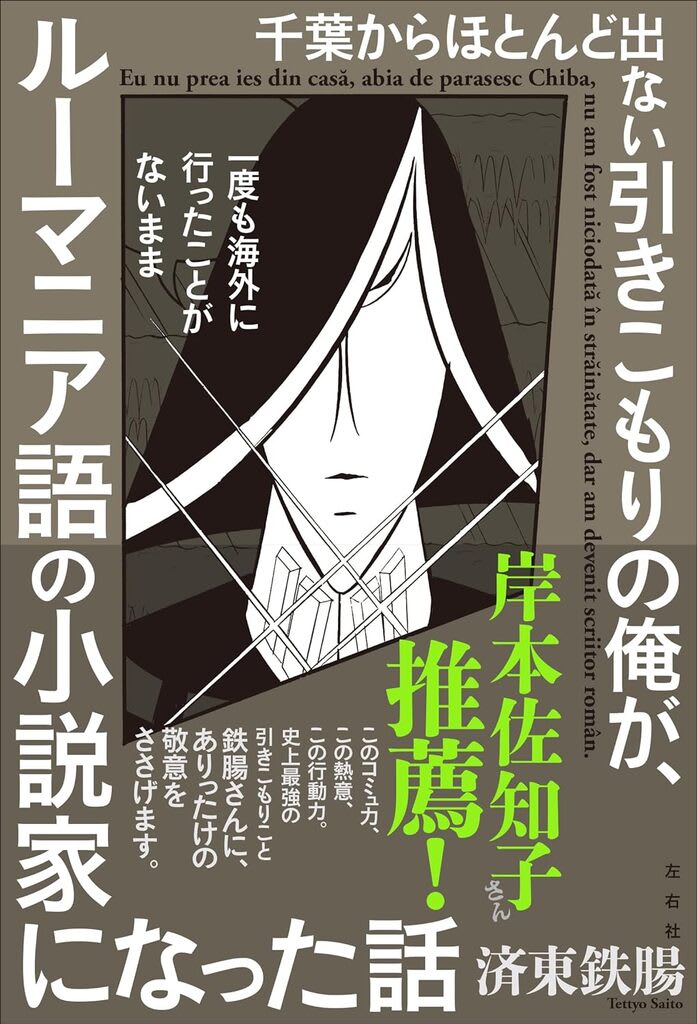


 (明治学院大学礼拝堂)
(明治学院大学礼拝堂) (山の上ホテル)
(山の上ホテル) (関西学院大学)
(関西学院大学) (一柳夫妻)
(一柳夫妻)




