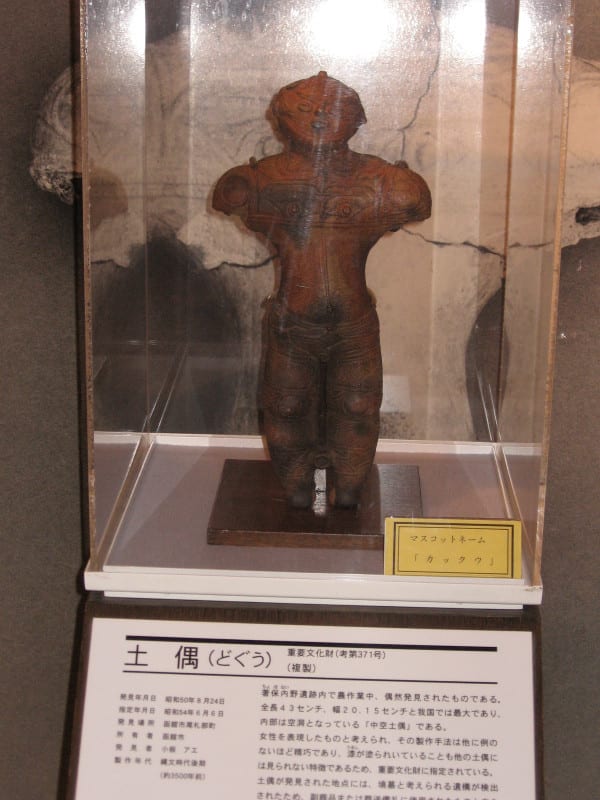2012.10.14(日)曇
夏は一般的に大衆受けする催しが多いが、秋は玄人というか特化した分野の展示会が多い。文化の秋のなせるわざと言うところか。行きたい催しがいくつかある。行きたいと行けるとは別問題で、金銭的な理由で行けないものがある。
高句麗壁画古墳報道写真展
日本新聞博物館 横浜市中央区 12月16日まで
共同通信社が昨年、一昨年平壌やその周辺で取材したもので、メディア、研究者とも簡単に行けるところでは無いので大変貴重なものだ。日本の古代文化との関連を発見できるものだろう。横浜まで出かけられないが、関西などでも開催されないものなんだろうか。
丹後古代の里資料館
京丹後市丹後町宮 火曜休館
丹後建国(713年)1300年を前に展示品を刷新して、鉄の丹後王国の繁栄から衰退までを分かりやすく紹介している。
これは期間展示ではなく、常設の展示と思われるが近くでもあるので是非行ってみたい。それはやはり近年盛んになった製鉄遺跡の発掘である。もちろん過去から製鉄遺跡は発掘されていたのだが、あまり注目されていなかったというか、重要視されていなかったようである。ところが近年国家の成立、国権、文化の発展などに金属とりわけ鉄の有り様が大きくクローズアップされてきた。
今ここに「日本の古代遺跡27」という古代遺跡、特に古墳についての非常によくできたガイドブック的な本がある。大変身近な遺跡の概要が分かりやすく述べられているのだが、金属の産出、精錬という視点はまるで無い。石器、土器、銅鐸、鏡、石棺などが主人公で、もちろん大刀や銅鐸など金属製品は登場するのだが、金属の産出、精錬という観点は無いようである。
やがて古代国家の成立と発展に金属が重要な位置を占めることが理解されはじめ、製鉄遺跡や鍛冶遺跡が注目されるようになったのだろう。特に丹後では遠所遺跡の発掘が大きなウェイトを占めるようになった。
そういう所にこの資料館の刷新というのも在るのではないだろうか。
特別展「王者の証」
綾部市資料館開館20周年記念特別展示 11月25日まで
横穴式石室墳がメインテーマということで、市内からの出土品、藤ノ木古墳の出土品の一部も展示されるそうだ。
あまり興味ないのだけど確実に行けるので取りあげてみた。
秋は文化的催しが目白押し、普段文化に触れることの無いあなた、この秋ちょっと覗いてみませんか。
【晴徨雨読】75日目 (2006.10.14)八戸~田野畑
フェリーで八戸に着いたのは暗い内でその寒いこと、車の連中はそそくさと出かけるが、二輪と自転車のわたしは待合室で夜明けを待つ。外に出る気がしないわけだ。これから冬に向かう京都への道のりを思うと、不安が込み上げてくる。それでも明るい日差しが差し込んでくると勇気が湧くものだ。種差海岸など風光明媚な海岸線を走る。絶好のサイクリングコースだ。岩手県に入ると道はやや複雑になるのだが、種市海水浴場という知られていないのに素晴らしい景色を見る。

久慈あたりで一泊と思ったが何となく変わりばえのしないところなので足を伸ばすと、玉川鉱山なんてのがあった。なんとこれがマンガン鉱山なのだ。
観光鉱山も一人で入ると不気味である。
京都のマンガン鉱山と違って規模がでかい。少し走って海沿いの烏帽子岩のそばに宿をとる。
【今日のじょん】:今日は葛禮本神社の秋祭りだ。幟のところからお参りする。