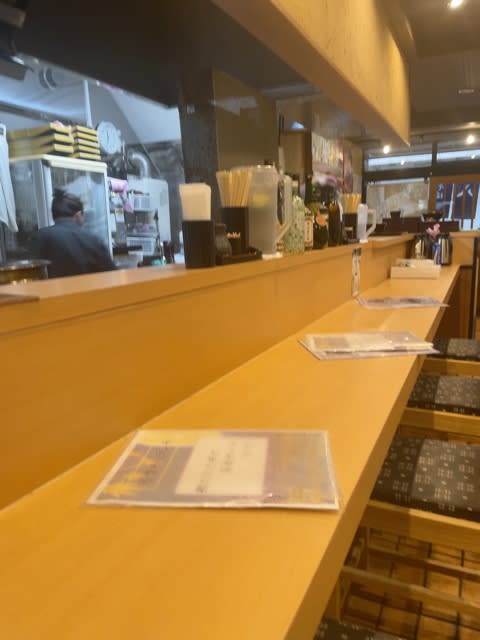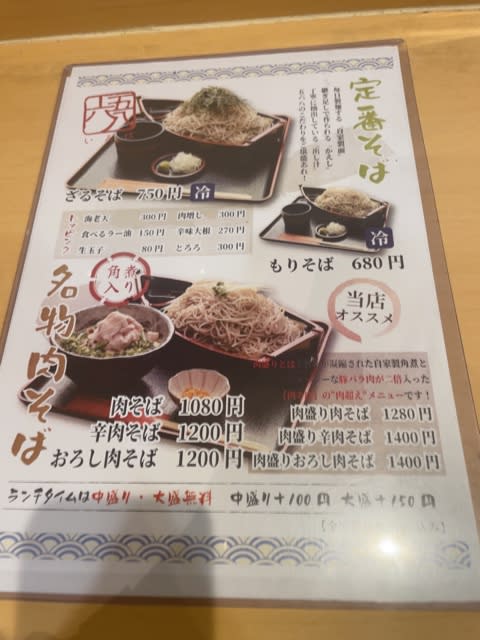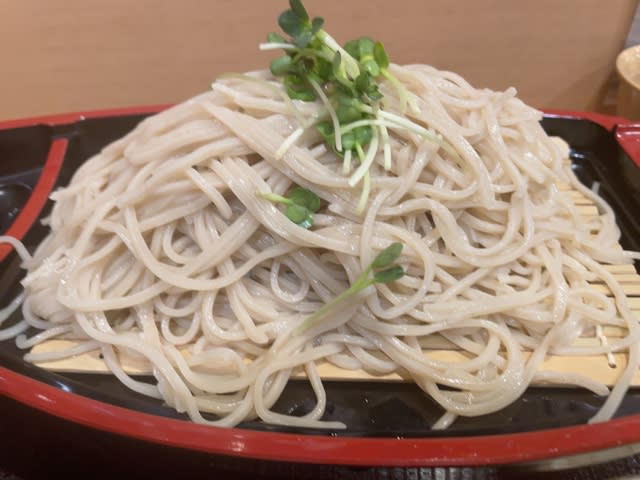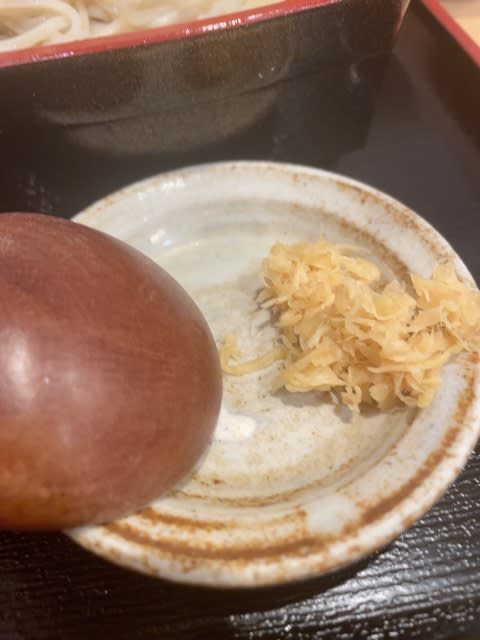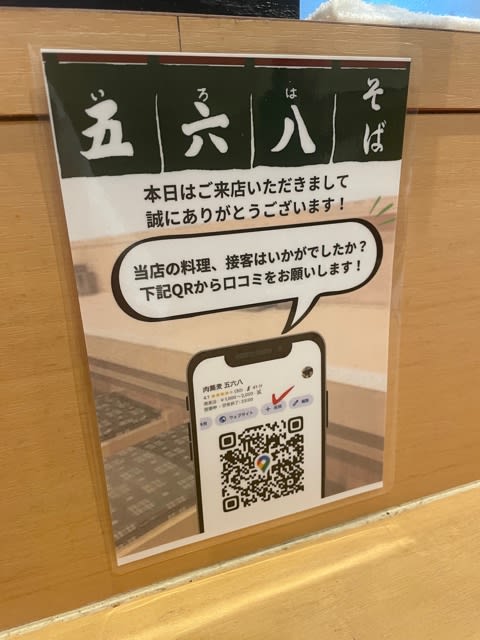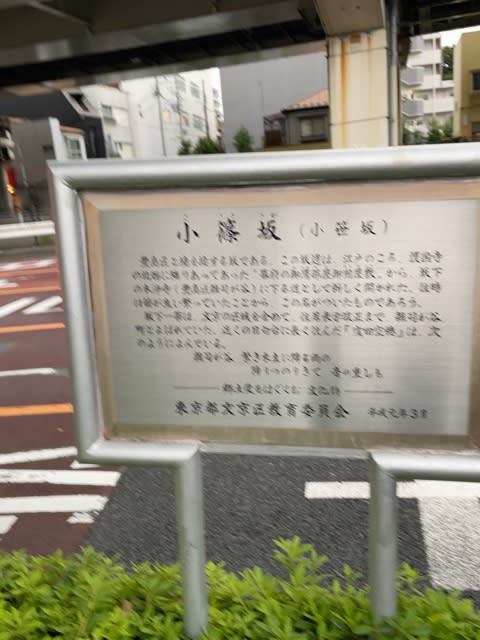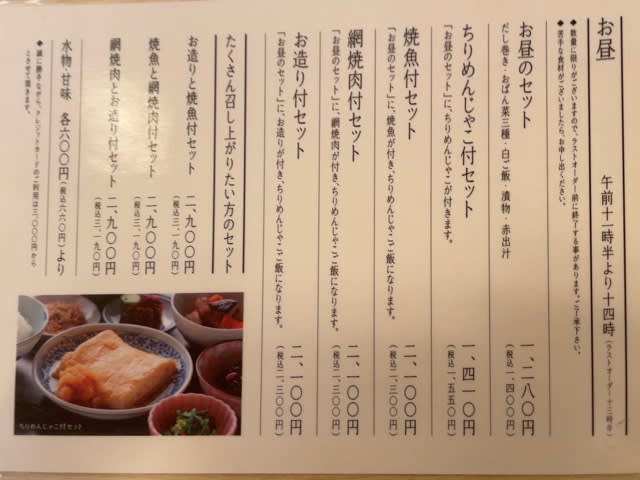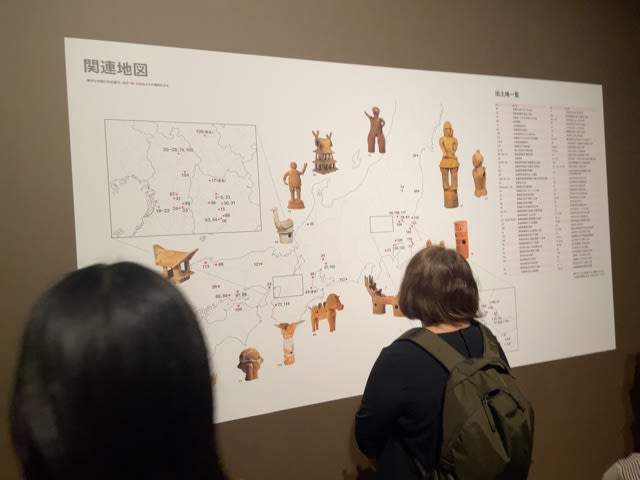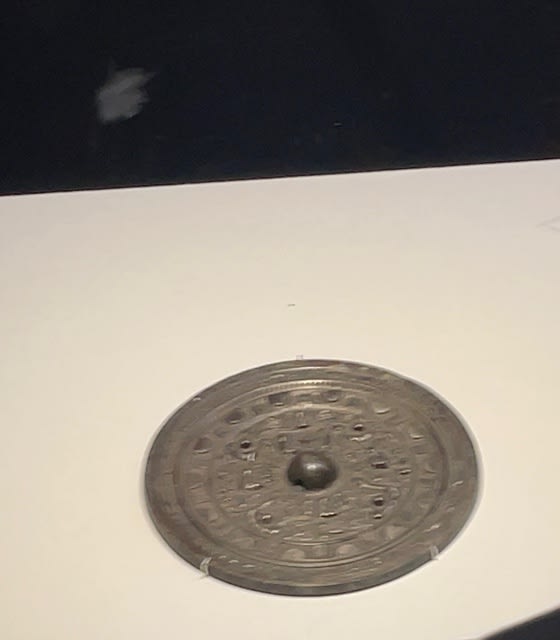『久我山歳時記』(52)、11月7日は立冬、つまり暦上は冬に入る。11月6日に富士山が初冠雪というニュースも入る。

ただ、富士山レーダー館で先日伺った所によると今まで最も遅かった初冠雪が10月22日だから今年はいかに季節が進まず、暦だけが過ぎていくのがわかる。

(11月1日)
11月に入ると酉の市の話題も。11月の酉の日に市が立つのだが、今年は一の酉が11月5日、二の酉が11月17日、三の酉が11月29日。

三の酉まである年は火事が多いという故事があるが、30日ある11月を12で割ると2あまり6日、つまり二の酉までの年が6回、三の酉まである年が6回だから確率50%で三の酉まであることになり、あまり説得力のある故事とは言えない。


七十二侯によると『山茶始開(つばき始めて開く)〜11月11日』『地始凍(ちはじめてこおる)〜11月16日』『金盞花咲(きんせんかさく)〜11月21日』となる。

(つばき)

(さざんか)
山茶とは椿、金盞花とは水仙、地始凍は霜や霜柱のことを指す。まだ、椿は咲いていないが、山茶花は咲き始めている。

(24/11/3)

(23/11/3)
久我山のシンボル的なユリノキもようやく葉が黄色くなりかけてきている。ただ、昨年11月3日に撮った写メと比べると明らかに遅くなっている。

(24/11/3)

(23/11/3)
同様に近所の蔦の紅葉も明らかに遅れていることに加え、今年は紅葉せずに茶色になって散ってしまっていた。

そんな街歩きの途中に道端でタンポポを発見。アスファルトの隙間からけなげに咲いているのである。色は黄色ではなく、真っ白である。珍しいと調べたところ、ケイリンシロタンポポというアジア大陸に生える白いタンポポであった。(日本原産のシロバナタンポポより少し花が大きい。)

すでにひたちなか海浜公園が有名なコキアもかなり赤くなっていてポツンと一つ咲いていたが美しかった。


我が家の庭はさすがにモミジアオイも花が終わり、たくさんの種を採取。なぜか季節外れのスズランが花をつけた。


日々草も葉が黄色くなり、花も咲かなくなったため、パンジーに植え替え、あわせて今年はガーデンシクラメンを植えてみました。


パンジーを農協に買いに行くと商品のパンジーの花から蜜を吸うキタテハ、そばに寄っても逃げることなく堂々としていました。


最後の三連休を終え、激しい雨が止んでからは驚くほど朝の気温が下がってきた。木枯らし1号も吹き、あっという間にユリノキのたくさんの葉も落ち葉になってしまうのである。