日本経済を読む 日本経済は回復軌道に乗ったのか②
的を得ていない政策
桜美林大学教授 藤田実さん
安倍晋三首相は自らの経済政策(アベノミクス)の効果を自画自賛していますが、本格的な経済回復の軌道には乗っていません。それは当然で、アベノミクスは的を射ていないからです。
消費増の中身
アベノミクスの公共事業拡大政策は需要不足を短期的に公共事業の拡大で解消し、市場に大量の資金を流し込めば、インフレ期待で消費が盛り上がるので、設備投資が増大するだろうという想定の下でなされています。異常な金融緩和政策も、円安効果により輸出が拡大し、それにより企業は収益を拡大させるので、設備投資と雇用を増大させます。そのことによって消費の増大と連関し、経済は成長軌道に乗るというように想定しているのです。
4~6月期のGDP速報で、家計最終消費支出は0・8%増で、3期連続でプラスとなりました。これだけ見ると消費は拡大しているように見えますが、「家計消費状況調査」(季節調整値、名目、2010年=100)によれば、消費支出は4月から6月まで、10年水準を下回っています。
また7月の「消費動向調査」によれば、消費者心理を表す消費者態度指数(2人以上の世帯、季節調整値)は前月から0・7ポイント低下の43・6と、2カ月連続で悪化しています。マスコミでも、宝石や高級車などの高額消費の増加が報道されましたが、これは株価上昇などの恩恵を受けた高所得層を中心とした消費行動であって、一般消費者にまでは波及していません
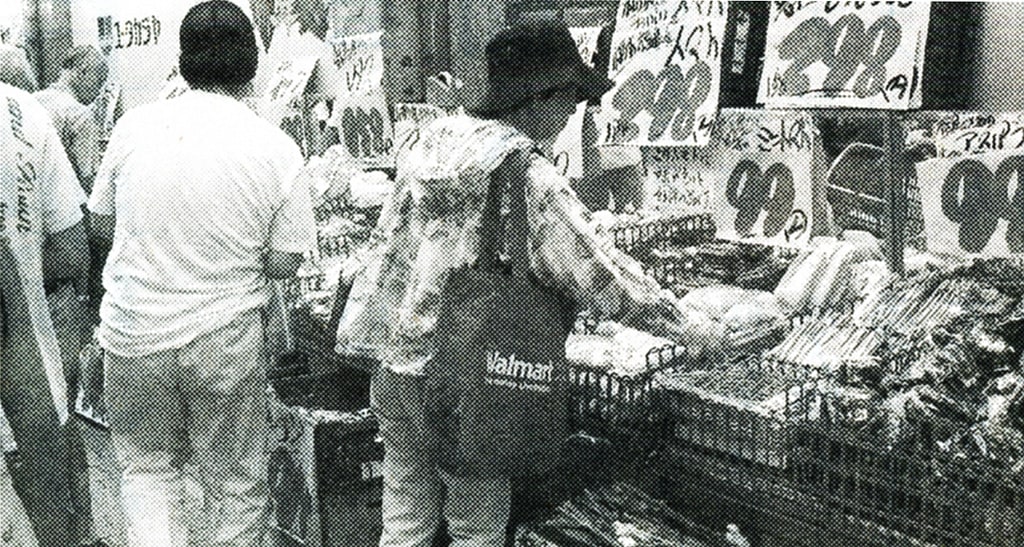
店頭で商品を選ぶ買い物客=東京都内
構造的な不足
このように公共事業の拡大や異常な金融緩和政策を行っても、設備投資や個人消費は持続的に拡大する傾向にはありません。なぜでしょうか。それは日本経済の停滞は短期的な需要不足によるのではなく、日本経済の構造変化と企業行動に起因する構造的な需要不足によるものだからです。
一つは少子高齢化が進み、旺盛(おうせい)な消費行動が見られなくなったからです。いわば、日本市場自体が縮小しているのです。第二には、社会保障の切り下げなどで将来不安が高まり、消費を抑制するようになったからです。第三にリストラによる雇用の不安定化や非正規雇用の増大、長時間労働の蔓延(まんえん)などによって、労働者が安定的に消費できない環境にあるからです。第四には家電品などの物的な需要は飽和状態に陥る一方、新しい商品開発やサービスが停滞していることです。第五には内需が停滞していることで、企業は海外展開を強めており、国内での設備投資が落ち込んでいることです。
こうした構造的な要因と企業行動により、日本経済は内需が拡大しない状態にあり、そのため需要不足に陥っているのです。
ですから、公共事業や金融緩和で企業収益を高めても、実体経済停滞の原因で艦ある消費と内需の拡大につながるような政策を打ち出さない限り、日本経済の本格的な回復はありません。
その上、消費税増税を決定すれば、賃金は増加しない一方、物価上昇と消費税負担で家計消費そのものを縮小させ、日本経済に大きな打撃を与える危険性があります。
(この項おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年8月22日付掲載
消費増の内訳が眉唾だって話しだけでなくって、個人消費不足の構造的な問題だって言われれば、ここ数年で解決できる問題ではないなあ…。
確かに、消費高齢化、社会保障の切り捨てによる将来不安などで、消費市場そのものが小さくなっている。
ここを解決するために政治の力が必要です。
的を得ていない政策
桜美林大学教授 藤田実さん
安倍晋三首相は自らの経済政策(アベノミクス)の効果を自画自賛していますが、本格的な経済回復の軌道には乗っていません。それは当然で、アベノミクスは的を射ていないからです。
消費増の中身
アベノミクスの公共事業拡大政策は需要不足を短期的に公共事業の拡大で解消し、市場に大量の資金を流し込めば、インフレ期待で消費が盛り上がるので、設備投資が増大するだろうという想定の下でなされています。異常な金融緩和政策も、円安効果により輸出が拡大し、それにより企業は収益を拡大させるので、設備投資と雇用を増大させます。そのことによって消費の増大と連関し、経済は成長軌道に乗るというように想定しているのです。
4~6月期のGDP速報で、家計最終消費支出は0・8%増で、3期連続でプラスとなりました。これだけ見ると消費は拡大しているように見えますが、「家計消費状況調査」(季節調整値、名目、2010年=100)によれば、消費支出は4月から6月まで、10年水準を下回っています。
また7月の「消費動向調査」によれば、消費者心理を表す消費者態度指数(2人以上の世帯、季節調整値)は前月から0・7ポイント低下の43・6と、2カ月連続で悪化しています。マスコミでも、宝石や高級車などの高額消費の増加が報道されましたが、これは株価上昇などの恩恵を受けた高所得層を中心とした消費行動であって、一般消費者にまでは波及していません
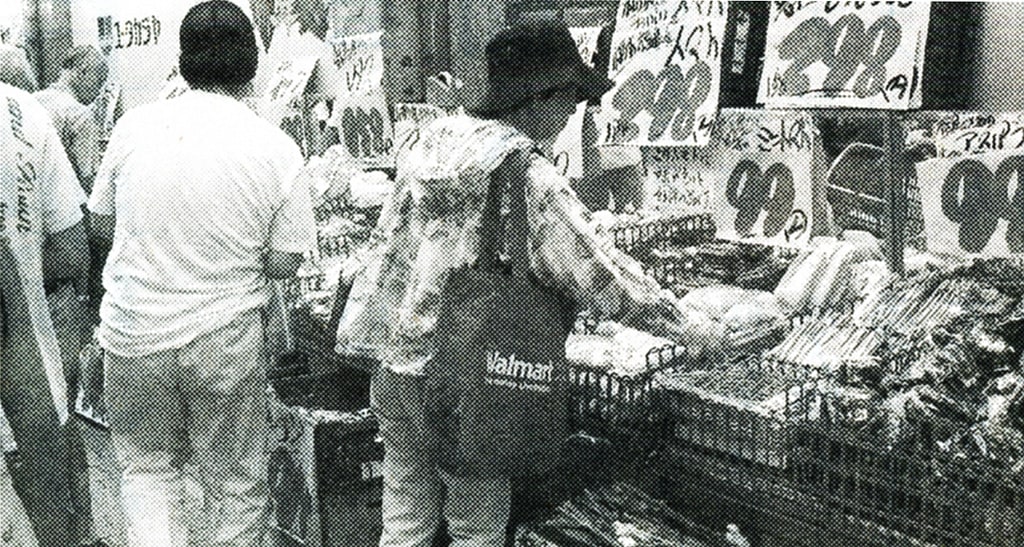
店頭で商品を選ぶ買い物客=東京都内
構造的な不足
このように公共事業の拡大や異常な金融緩和政策を行っても、設備投資や個人消費は持続的に拡大する傾向にはありません。なぜでしょうか。それは日本経済の停滞は短期的な需要不足によるのではなく、日本経済の構造変化と企業行動に起因する構造的な需要不足によるものだからです。
一つは少子高齢化が進み、旺盛(おうせい)な消費行動が見られなくなったからです。いわば、日本市場自体が縮小しているのです。第二には、社会保障の切り下げなどで将来不安が高まり、消費を抑制するようになったからです。第三にリストラによる雇用の不安定化や非正規雇用の増大、長時間労働の蔓延(まんえん)などによって、労働者が安定的に消費できない環境にあるからです。第四には家電品などの物的な需要は飽和状態に陥る一方、新しい商品開発やサービスが停滞していることです。第五には内需が停滞していることで、企業は海外展開を強めており、国内での設備投資が落ち込んでいることです。
こうした構造的な要因と企業行動により、日本経済は内需が拡大しない状態にあり、そのため需要不足に陥っているのです。
ですから、公共事業や金融緩和で企業収益を高めても、実体経済停滞の原因で艦ある消費と内需の拡大につながるような政策を打ち出さない限り、日本経済の本格的な回復はありません。
その上、消費税増税を決定すれば、賃金は増加しない一方、物価上昇と消費税負担で家計消費そのものを縮小させ、日本経済に大きな打撃を与える危険性があります。
(この項おわり)
「しんぶん赤旗」日刊紙 2013年8月22日付掲載
消費増の内訳が眉唾だって話しだけでなくって、個人消費不足の構造的な問題だって言われれば、ここ数年で解決できる問題ではないなあ…。
確かに、消費高齢化、社会保障の切り捨てによる将来不安などで、消費市場そのものが小さくなっている。
ここを解決するために政治の力が必要です。












