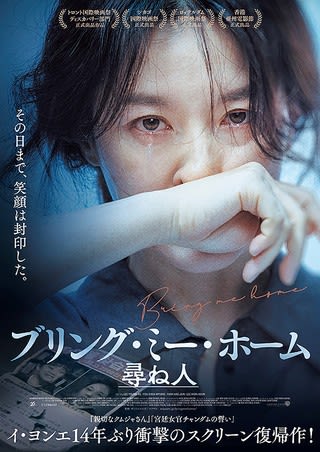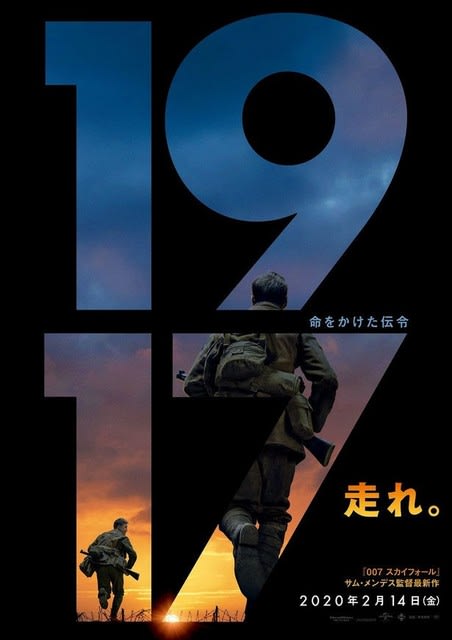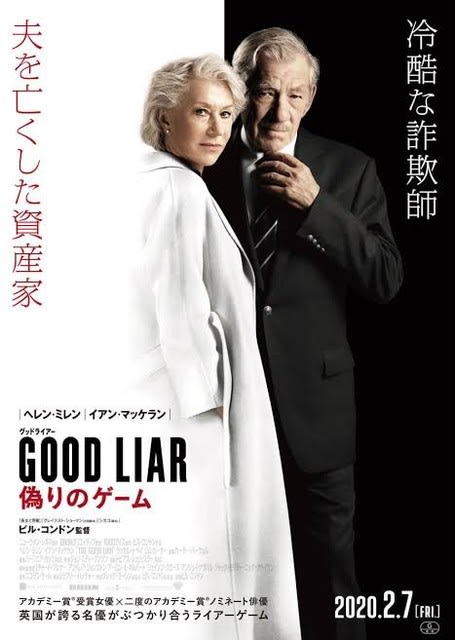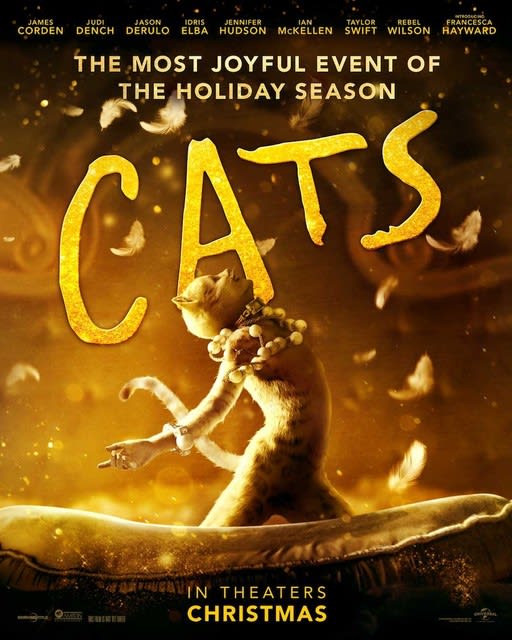2020.09.18 『TENET テネット』鑑賞@TOHOシネマズ日比谷
約3か月ぶりの劇場鑑賞。7月からPCR検査陽性者が増えたため自粛してた。公開作品も少なかったし😅 今回も少し迷ったのだけど、クリストファー・ノーランの最新作なら絶対大画面で見たい!ってことで行ってきた~

 ネタバレありです! 結末にも触れています!
ネタバレありです! 結末にも触れています!
「ウクライナの劇場である作戦に加わった主人公は、ロシアの組織に拘束されてしまい、自決用カプセルをかみ砕く。目覚めるとテストに合格したので新たな任務に就くように言われる。それは第三次世界大戦を阻止せよというものだったが・・・」というあらすじはホントに導入部のみで、全然上手くない💦 なので、魅力が全然伝わらないのだけど、そもそもちゃんと理解できていないので、これが限界 でも、めちゃめちゃおもしろかった! ノーラン節炸裂です!
でも、めちゃめちゃおもしろかった! ノーラン節炸裂です!
クリストファー・ノーラン監督作品。ファンなので監督作品は『フォロウィング』以外は全て見ている。感想書いてるのは『ダークナイト』(感想は コチラ)、『インセプション』(感想は
コチラ)、『インセプション』(感想は コチラ)、『ダークナイトライジング』(感想は
コチラ)、『ダークナイトライジング』(感想は コチラ)、『インターステラー』(感想は
コチラ)、『インターステラー』(感想は コチラ)、『ダンケルク』(感想は
コチラ)、『ダンケルク』(感想は コチラ)。
コチラ)。
映画について毎度の Wikipediaから引用しておく。『TENET テネット』(原題:Tenet)は、2020年公開のクリストファー・ノーラン監督・脚本・製作によるSF映画である。脚本と監督をこなしたクリストファー・ノーランは、TENETの背後の着想を20年間に渡って温めたが、「私はこの脚本の練り直しに6, 7年は掛けている」と発言している。原題「TENET」は、回文であり、前から読んでも後ろから読んでも同じである(邦題「TENET テネット」では、この通りではない)。ノーランは、スパイ映画からの影響を、自らの記憶のみに留めるように意識的に努力した。映画『ウエスタン』(1968年)から脚本の着想を得た。理論物理学者のキップ・ソーンは、時間と量子力学の主題について相談を受けた。
Wikipediaから引用しておく。『TENET テネット』(原題:Tenet)は、2020年公開のクリストファー・ノーラン監督・脚本・製作によるSF映画である。脚本と監督をこなしたクリストファー・ノーランは、TENETの背後の着想を20年間に渡って温めたが、「私はこの脚本の練り直しに6, 7年は掛けている」と発言している。原題「TENET」は、回文であり、前から読んでも後ろから読んでも同じである(邦題「TENET テネット」では、この通りではない)。ノーランは、スパイ映画からの影響を、自らの記憶のみに留めるように意識的に努力した。映画『ウエスタン』(1968年)から脚本の着想を得た。理論物理学者のキップ・ソーンは、時間と量子力学の主題について相談を受けた。
SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS ラテン語による回文。三行目(三列目)に TENET が表れる。ケネス・ブラナー演じるアンドレイ・セイターの姓が SATOR。キエフ・オペラの OPERA。ゴヤの贋作者の名前が AREPO。オスロ空港の警備会社が ROTAS。
さて、今作。ノーラン作品にしてはかなり説明的なセリフがあるけど、なにぶん見ている側の理解が追いつかず💦 今に描かれていることが現段階、もしくは未来に実現可能であるという科学的根拠があるのかも分からない💦 半分も理解できていないし、細かい部分も覚えていない。なので、適当に端折ったり、割愛したり、順番を入れ替えることがあるかと思います。間違っていることは書かないつもりだけど、そもそも間違って解釈しているかもしれません。あくまでそう理解したという感想になります。毎度どうでもいいと思うけど、断り書きとして書いておく😌
冒頭、キエフの劇場でのテロシーンから始まる。武装した兵士?たちが銃を手に突入していく。その中に名もなき男(ジョン・デイヴィッド・ワシントン)の姿もあった。実は見ている間は全く気付いてなかったのだけど主人公は名前がない。公式サイトでキャスト情報見てビックリ! 名前呼ばれてなかったの気づかなかった😲 このシーンではアメリカ人って呼ばれており、CIAのエージェントということだった。
劇場内に突入するとしばらく銃撃戦が続く。激しいアクションシーンから始まるのは、もはやノーラン作品の定番だけど、今回はまた一段とスゴイ! 満員の観客を催眠ガスで眠らせるのだけど、CGを極力使わないノーラン監督だから、この人たちはエキストラなんでしょうね🤔 公式サイトによると、このシーンはエストニアの首都タリンにあるコンサートホールで、長年放置されていたため荒れていて、撮影にあたり美術スタッフがステージを建て直したり、外壁を直したりとかなりの手直しをしたらしい😲
このシーンは結構な長さ続くけど、ここでのポイントはテロは偽装であること、名もなき男のピンチを救った人物がいたこと。かなりの人数の兵士?が導入されているわけだけど、偽装であることを誰がどこまで知っているのか不明。名もなき男の任務は潜入捜査官?と、彼が持ち出した"プルトニュウム241"を手に入れるため。だったよね? というくらい、早くも全く理解が追いつかないけど、めちゃおもしろい!
名もなき男は捕えられ、鉄道車庫の線路の上に椅子に縛られて座らされている。"プルトニュウム241"のありかを話すように言われる。名もなき男の前には椅子に縛られたまま横たわる男。後ろ姿のみで顔は分からない。彼はどうやら何かを喋った様子。しかし、肝心な部分は名もなき男から聞き出したいらしい。決定的な場面は見せないけどペンチで歯を抜く拷問を受けているっぽい😱 たしか列車が向かってきて選択を迫られた気がしたけどどうだっけ? とにかく、倒れている男が後ろ手に差し出した自決用カプセルを飲み込んだところで暗転。
目覚めると船室にいた。名もなき男はフェイ(マーティン・ドノバン)という人物からテストに合格したので、任務の指令が出るまで待機するように言われる。この時、君はTENET(テネット)という言葉さえ知っていればいい的なことを言われる。"言語"と字幕が出ていたような気も?🤔 TENETについて詳しい説明はなかったし、その後TENETという言葉が出て来ることもなかったと思う。TENETとは前述したとおり、SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS ラテン語による回文。その後、名もなき男は海上にある風力発電所の建物内で訓練し時を待つ。この風力発電所はデンマーク沖のバルト海に実際にある施設だそう。
訓練を終えた名もなき男は、研究機関のような所を訪ねる。名称とか表示されていたかもしれないけれど覚えていない💦 そこで、バーバラ(クレマンス・ポエジー)という科学者から説明を受ける。あまり理解できていないのだけど、ある日未来から石の壁の一部が送られてきて、その壁は時間が逆行していることが分かったらしい。名もなき男がバーバラに言われた通り銃を撃とうとすると、壁の中から弾が戻って来る。このように、未来から様々な物が送られていきているので、それを研究しているらしい。
時間の逆行はエントロピーを減少させると起きるそうで、これが利用されて人類が絶滅するのを防ぐのが名もなき男の任務。と、理解したけど合ってるか? とにかくエントロピーって何?という状態なもので😅
名もなき男はムンバイへ向かう。銃の出処だろうと思われる武器商人サンジェイ・シン(デンジル・スミス)に会うため。厳重警備の高層マンションから一歩も外に出ないサンジェイ・シンに会うのは不可能。そこで名もなき男はある人物に連絡を取る。これ何でこの人物に連絡取ることにしたんだっけ?🤔
待ち合わせ場所のレストランに現れたニール(ロバート・パティンソン)は、なぜか男の飲み物の好みを知っていた。これは後の伏線。映画、特にサスペンス作品をたくさん見ると、疑って見るクセがつく。なので、ニールは裏切るんじゃないか? 実は黒幕なんじゃないか?と思って見ていた😅 ロバート・パティンソンという人選が絶妙
2人は伸縮性のあるワイヤー的な物を使って逆バンジーでサンジェイ・シンの部屋に侵入する。向かいのビルの屋上からバーンと飛び移ってビョンビョンしながらよじ登るの楽しい。ボディーガード?を倒して部屋に侵入した2人を迎えたのはプリヤ(ディンプル・カパディア)というサンジェイ・シンの妻。実は、実際に組織を動かしているのはプリヤの方だった。プリヤは未来から来た武器?はロシア人のアンドレイ・セイター(ケネス・ブラナー)から買ったと言う。
このセイターが今回のヴィラン。とはいえ、実はニールが黒幕なんじゃないかと疑ってたけど😅 セイターは前述したTENETの語源である、SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS のSATORから命名されているらしい。セイターに会うのは不可能ということで、彼の妻に接触して会わせてもらうと考える。
そこで、名もなき男はMI6のマイケル・クロスビー卿(マイケル・ケイン)に会いにロンドンへ行く。スーツが必要だとかニールとふざけた会話をしていた気がするけどどうだったかな?🤔 高級レストランで食事中のクロズビー卿は、紳士的だけれど名もなき男を見下した態度😅 まぁ、名もなき男の態度も高級レストランにふさわしいものではなったけれど。ノーラン作品常連のマイケル・ケイン、前作は声のみだったのでウレシイ😍
クロズビー卿によると、セイターはロシアの地図に載っていないスタルスク21という土地の出身だと言う。たしか核実験が行われた土地で、そのため存在を隠されているということだったと思う。なので、セイターは実は存在しない人間ということじゃなかったかな?🤔 そのスタルスク21で最近、何かが爆発した痕跡があるとのことだった。
クロズビー卿は名もなき男にゴヤの贋作を渡す。描いたのはアレポという人物で、どうやら絵画鑑定人である妻は、アレポと組んで贋作をオークションに出したが、その絵をセイターが落札し脅される羽目になったらしい。アレポという名前もSATOR AREPO TENET OPERA ROTAS から由来しているらしいけれど、結局この人物は名前のみで登場しなかったと思う。
名もなき男はセイターの妻キャット(エリザベス・デビッキ)と話す機会を得る。何かのパーティー会場だったように思うけど、どうだったかな? 入手したゴヤの贋作の効果抜群だったが、キャットの状況はなかなかキビシイものだった。オークションで競り落とした贋作をネタに脅されて離婚もできない状況。
そもそも、キャットはベトナム旅行中に離婚を切り出すと、セイターは離婚するなら息子には二度と会わせないと言われていた。その後、息子と観光から戻ると、セイターのクルーズ船から若い女性が海に飛び込む姿を目撃した。夫の愛人だと思うが、彼女には自由があってうらやましかったと語る。実はこれは後の伏線だった。
えーと💦 結局、この時にはセイターに会わせてもらう約束はできなかったと思うのだけど、2人の会話がどう終わったのか失念😣 名もなき男は厨房でセイターの部下と思われる男たちとアクションを繰り広げて倒し、悠然と裏口から出てきたところを、車中のキャットが見ていた記憶があるのだけども?🤔
結局、後日キャットが息子マックス(ロウリー・シェパード)の学校の門の前で、一目会おうと待ち伏せしているところを捕まえて、セイターが購入した贋作を取り戻すことを条件に、セイターに引き合わせることを約束させることに成功。この学校のシーンが出て来たのは、後の伏線なのかな?
贋作を奪うため保管先であるオスロ空港内のセキュリティー会社?へ向かう。名もなき男とニールは客を装ってセキュリティーシステムなどを聞き出す。どうやら、何かしらのアクシデントが起きた場合、保管室内に消火ガス?が噴霧され、従業員はガスが充満する数十秒間に脱出する仕組みになっているとのこと。
そこで2人は協力者であるマヒア(ヒメーシュ・パテル)と、金を運ぶ輸送機を強奪し事故に見せかけて倉庫に突っ込ませ、ガス噴霧後の数十秒間で贋作を奪い脱出する計画を実行する。CGなどを極力使わないノーラン監督だけに、このシーンでは本物のボーイング747を突っ込ませたとのこと。ちなみに、オスロ空港となっているけれど、撮影場所はロサンゼルス国際空港のターミナル。
事前にどれだけ息を止められるか試したり、実行時にもちょっとしたアクシデントが起きたりとハラハラさせるけど、結局贋作は保管されてなかったんだっけ? ここで重要なのは逆行装置が作動して、時間を逆行してきた武装した男2名と格闘したこと。
逆行装置は何ヶ所か設置されているのかな? この後、もう1カ所出て来る。形状としては回転扉のようなもので、装置を挟んでガラス張りの2つの部屋が並行して存在している。ちゃんと理解できていないのだけど、時間を逆行しているだけで、ある日ある時の過去にタイムスリップするということではないらしい?🤔 理解が追いつかない💦
武装した人物との格闘で、名もなき男は相手の腕を切りつける。廊下で格闘を続けるも逃げた男を、ニールが追いかける。2人は名もなき男の死角に入る。戻って来たニールはどこか様子がおかしい。これは後の伏線。とにかくこんなに大掛かりな作戦だったわりに贋作は取り戻せず。
名もなき男はキャットと再会し、贋作は処分したのでセイターに紹介するように依頼する。キャットは乗り気ではなかったものの、仕方なく名もなき男とボートで停泊中のセイターのクルーズ船に向かう。夕食に招かれた名もなき男は、キャットの浮気相手と疑われ、マフィア特有の殺し方で殺すと脅す。例のモノを口に突っ込むアレね😅
競技用ヨット?に名もなき男とキャットが同乗し、セイターとレース的なことをしたのはいつだっけ? これはなかなか迫力があって楽しそうだった✨ この時、キャットがセイターを殺そうとロープを切ってセイターを海に落とすが、名もなき男がセイターを助ける。これは計画だったのかな? そういう描写はなかったような?
命を救ってくれたお礼にと、セイターは名もなき男に身の上話をする。セイターは少年の頃、スタルスク21で核実験の残骸を回収する仕事をしていたが、ある日自分宛ての契約書を見つけた。それ以来、世界各地からアルゴリズムを回収していて、"プルトニュウム241"が最後の一つだと言う。名もなき男は、協力してそれを回収しようと言う。冒頭のテロで回収しようとしていたプルトニュウムだよね? あれってどうなっっていたんだっけ?🤔
えーと💦 たしか夜中に大きな荷物が運び込まれて、それを盗み見ていた名もなき男はセイターの部下に見つかってしまったと思うのだけど、これってどうなったんだっけ? 名もなき男がどうやって船降りたか忘れてしまったわ😅
ニールと合流した名もなき男は、"プルトニュウム241"の強奪計画を実行する。"プルトニュウム241"は装甲車でどこかに運ばれるようで、名もなき男とニールの指示で一台また一台とトラックが現れて装甲車を取り囲んでいく。これ、それぞれのシーンにスピード感はないんだけど、何が起きてるの?というワクワク感があっておもしろい。そして、これもCGなしで撮影しているのかしらね?
名もなき男は装甲車に飛び移り、しばしのアクションシーンの後、"プルトニュウム241"を奪うことに成功。そして、ニールが運転する車に戻って来る。そこに逆行してきた車が並走して来る。後部ドアが開いており、中にはキャットに銃を向けるセイター。セイターは名もなき男に"プルトニュウム241"をよこせと言う。
この時、横転していた車が突如元に戻り逆行して来る。セイターのじゃまをしようとしているようだけれど、結局はどうなったんだっけ? とにかく、これは後の伏線!
結局、名もなき男は"プルトニュウム241"をセイターに渡す。セイターは車を降りるがキャットは取り残されたままだった。名もなき男はキャットの車に飛び車を止める。このシーンでも、これに続くシーンでも名もなき男はとにかくキャットを救おうとするのだけど、見ている間は何故そこまでするんだろうと思っていた。イヤ、見捨てて欲しいわけじゃないけど😅
実はキャットはこの後の大きなカギを握る人物なのだけど、見ている側にはこの時点ではキャットは単なるセイターとのつなぎ役だと思っているので、ちょっと違和感。イヤ、もちろん見捨てていいわけではないのだけど、人類が滅びるかもしれないという状況でする選択ではないような🤔 まぁ、もちろん本物を渡してはいないのだろうと思ってはいたけれど。
えーと💦 詳細は忘れてしまったけど、名もなき男とキャットはセイターの部下に捕まってしまう。で、オスロ空港内にあったガラス張りで隔てられた部屋にそれぞれ監禁される。その部屋には逆行装置がある。えーと💦 ここもちょっと理解が追い付いていないのだけど、キャットがいる部屋が逆行で、名もなき男がいる部屋が順行なのかな?
で、とにかくセイターはキャットを撃つと脅し"プルトニュウム241"の隠し場所を話すように言う。名もなき男は車の中だと言うけど、セイターはキャットのお腹を撃つ。これ何で撃ったんだっけ? なんだか順行と逆行が入り混じって良く分からない💦 で、とにかく逆行なのか順行なのか、だとしたらどの時点だか分からないけど、とにかくキャットを撃ちます! そして、主人公はニールとアイブス(アーロン・テイラー=ジョンソン)の部隊に助けられる。
このアイブスの部隊にはホイーラー(フィオナ・ドゥーリフ)という女性隊員もいたりするのだけど、どういう部隊なのか説明あったっけ? 冒頭の劇場でのテロもこの部隊と突入してたんだよね? うーん💦
で、セイターはキャットを連れて逆行装置に入って行ったのだけど、何故キャットは部屋に残ってたんだっけ? 最初に主人公とは別の部屋にいたキャットとセイターは時間を逆行していて、それで順行のセイターがキャットを連れて逆行して行ったということかな? とにかく、名もなき男たちは、セイターが時間の挟み撃ちをしたと考える。この時間の挟み撃ちの意味がよく分からず😅
名もなき男は自分も逆行して、逆行して"プルトニュウム241"を取に戻ったセイターを追うことにする。逆行中は普通に呼吸ができないため、酸素マスクを付ける必要があるらしい。逆行してたセイターってマスクしてたっけ?🤔 気づいてなかった😅 主人公が逆行することになったため、観客は初めて逆行の映像が主体的に見ることが出来る。名もなき男以外は全て逆に動いておもしろい。実際は名もなき男が逆行しているわけなのだけど。
車に乗ってセイターを追っていくのだけど、実は先ほどのセイター車と名もなき男車の間に割って入った謎の逆行車は、今逆行している名もなき男だった。おおー😲 先ほどの順行の時には、この逆行車は横転しているところから逆行してきたわけだから、最終的に今逆行している車も横転してしまう。そこにセイターがやって来て、逆行車から流れているガソリンに火をつける。名もなき男は必死に脱出しようとするけれど、逃げられない。炎に包まれた逆行車は凍ってしまう。何故?
目が覚めるとニールが逆行で炎に包まれたので低体温症になったと言う。エントロピーが減少するとそういう世界になるの? ニールによるとセイターの語るアルゴリズムというものは、9つに分かれた物質?を1つにすることで、それにより全世界のエントロピーを減少させて逆行することができるが、それをすれば生命が消滅してしまうということらしい。全く理解できないけど、そう言うんだからそうなんでしょう!🙄
さて、瀕死のキャットを救わなければならないということで、オスロ空港に向かう。これ、何でキャットを救うために逆行してオスロ空港に行かなきゃならなかったんだっけ? 説明していたと思うけどちゃんと理解できていなかったし、よく覚えていない😅 そして、相変わらず何故そこまでしてキャットを救わなければならないのか理解できない。イヤ、もちろん死んでいいと思っているわけではないのだけど。
えーと。オスロ空港でアヒムが起こした飛行機の事故時点に逆行してきたので、当然ながら事故が起きる。で、その爆風で名もなき男は建物内部に吸い込まれてしまう。そこは、贋作奪還作戦時に名もなき男とニールが謎の武装男と遭遇した部屋で、まさに贋作奪還作戦続行中の名もなき男とニールに遭遇する。あの時、名もなき男が対決したのは逆行してきた自分だった。ニールの様子がおかしかったのは、武装男が名もなき男だったから。もうややこしくて自分で書いててもなんのこっちゃ😅 でも、別の視点からあの時のアクションが再現されるのはおもしろかった。
で、たしか逆行装置の中にストレッチャーに乗せたキャットと入ってたよね? これは? 逆行してたから順行に戻ったということ? キャットは逆行で撃たれたので、順行に戻って治療する必要があったってこと? あれ?(o゚ェ゚o) とにかく、キャットは治療を受けます😅
さて、主人公はプリヤに会いに行く。会いに行くというか何かの式典? 儀式?をしている中、無理やり押しかけて行ったのだけど。そこでプリヤから真相を聞き出す。未来のある科学者がアルゴリズムを作ったけれど、自分の作り出した物の恐ろしさに自殺してしまった。自殺する前にアルゴリズムを9個に分けて過去に隠した。未来人の中にはそれを使いたいと考えている人々がいて、そのうちの誰かがセイターに回収する契約を送ったということらしい。
セイターは最後の一つだった"プルトニュウム241"を入手。既に9つを1つにする作業も終わっていると思われる。さらにセイターは自分が死ぬとアルゴリズムが作動するよう設定したと言う。えー💦 っていうか、そういう大事なことはもっと早く言ってよプリヤ(*`д´) と思うけど、それだと謎解きの醍醐味がないからね。
えーと、名もなき男とニールとキャットはアイブスの部隊と合流する。何故、船に乗ってたのか忘れちゃったけど、逆行してたので過去のある時点に向かっているということ? どうも、この時間の観念というか、順行と逆行の兼ね合いが分からない💦 とにかく、この船のシーンで重要なのは、キャットのセイターに関する一言。セイターは末期の癌で余命僅か。おそらく全世界を巻き添えにして死ぬつもりなのだ。ォィォィ 迷惑だな😅
となると、セイターが自殺する前にアルゴリズムを奪う必要がある。キャットはセイターが自殺するなら最後に家族が揃ったベトナムでないかと考える。キャットが離婚を切り出した日はスタルスク21で爆発が起こった日だった。なので、名もなき男たちは逆行しているらしい。そして、キャットはアヒムとベトナムへ向かう。ここからは名もなき男の部隊と、キャットの2つのシーンが交互に描かれるけど、適当にまとめて書いていく。
キャットの役割は名もなき男たちがアルゴリズムを回収するまでセイターが自殺しないように食止めること。この役割があるからキャットは殺せなかったのでしょうし、後に種明かしがあるけどこの任務を遂行している"今"の名もなき男はキャットの役割は知らなかったはずで、テロシーンでは多少の犠牲は仕方ない的な感じだったのに、キャットのみ救おうとするのはちょっとご都合主義的に感じるかな🤔
まぁ、それは置いておいて、とりあえず殺したいほど憎む気持ちを抑えて、キャットはもう一度やり直したいと、あの手この手で頑張る。ベッドシーンはなしです。そういえばノーラン作品てあまりベッドシーンとかないかも?🤔 別にいいけど。
一方、名もなき男たちの部隊は、会議室的な所でアイブスから作戦の説明を受ける。どうやら時間の挟み撃ちをするらしい。よく理解できていないのだけど、要するに部隊を2つに分けて赤チームは順行、青チームは逆行してアルゴリズム奪還を狙う。ニールは青チーム、赤チームはホイーラーが隊長を務め、名もなき男とアイブスは別行動をする。
ということで、さらに3つの視点が加わり、4つの場面が同時進行することになる。初めこそ順行と逆行が分かりやすく、逆に歩いたりしているのだけど、もう途中から何がなにやら💦 例えば、一般的な突入作戦だと身を潜めていた部隊が、敵の隙をついて「今だ!」の号令で突入したりするけど、その敵の隙が見ている側に全然分からないタイミングで「今だ!」の声がかかり部隊が移動するのだけど、何故今なのか? そして何をしたのか?全く理解できない💦
でも、つまらないというわけではなく、めちゃめちゃおもしろい! 戦闘シーンというよりも戦闘ゲームを見ているような感覚で、役者さんたちがゲームのキャラに見える。そこを狙っているのかは分からないし、ゲーム全然詳しくないけど、なんとなく疑似体験している感じになって、バーチャルゲームのようで楽しかった。
名もなき男とアイブスはアルゴリズムが埋められていると思われる洞窟へ向かう。洞窟に入ると爆発が起き、退路を断たれてしまう。奥へと進むと、アルゴリズムはカギのかかった鉄格子の中で、その手前には部隊の兵士の遺体があった。彼はオレンジの紐のキーホルダーを付けている。セイターから指示を受けた部下がアルゴリズムを起動しようとしている。すると遺体が起き上がり、部下と格闘しカギを開ける。この人は逆行したっていうこと?🤔 名もなき男は部下を倒し、アルゴリズムに近づく。
一方、セイターと向き合っていたキャットにも時間が迫っていた。あの日、船を離れていた自分と息子が戻って来ており、セイターに対する嫌悪感も限界だった。キャットはセイターを撃ち海へ飛び込む。あの日、キャットが見たのは、未来の自分だった。
えーと💦 キャットが先にセイターを殺してしまいそうになりハラハラさせるけど、世界が滅亡していないので、名もなき男はキャットより先にアルゴリズムを回収できたのでしょう。とにかく、4つの視点が交互に映し出され、さらに順行、逆行入り乱れ、そして単独行動のニールも加わるから、全くついて行けない💦💦
逆行チームだったはずのニールがいつの間にか単独行動で順行していたのだけど、とにかく爆発寸前にニールがロープを垂らし、そのまま車を走らせると、ロープにつかまった名もなき男とアイブスが地上に出て来る。これは何で爆発したんだっけ? 重複するけど世界が滅亡していないから、アルゴリズムが爆発したわけではないらしい。
アイブスはアルゴリズムを3等分し、3人でそれぞれどこかに隠し、その後口を割らないように死のうと念押しして去って行く。え 死ぬの
死ぬの 😲
😲
と、思っていると、ニールはまだ任務が残っているから行くと名もなき男に告げる。俺たちの友情は始まったばかりだと言う名もなき男に、これが俺たちの友情の終わりだと言うニール。名もなき男と共にどういうこと?と思っていると、背を向けたニールのリュックにはオレンジの紐のキーホルダーが付いていた。あの遺体はニールだった 😲
😲
去り行くニールに、お前を雇ったのは誰だと聞くと、未来のお前だと答える。なんと! この作戦の黒幕は名もなき男だったのだった!😲 そしてニールは去って行く。えーと、ニールはこれから逆行して、名もなき男とアイブスのためにカギを開けるためにあの場所に戻り、そしてセイターの部下に殺されるということだよね? それを承知で任務に向かうということ? カッコイイ! カッコイイよニール!😭😭😭
場面変わってマックスの学校の前で息子を待つキャット。彼女を車の中から銃で狙うプリヤ。すると後部座席から名もなき男が現れる。名もなき男がプリヤの車にどうやって入ったかは不明だけど、ここに居合わせたのは何かあったら居場所を録音するようにキャットに指示したから。これは名もなき男がキャットのメッセージを聞いて逆行してきたということ? でも、酸素マスクしてたっけ? 覚えていない😅
プリヤがキャットを殺そうとしたのは、彼女が多くを知り過ぎているからだと思うのだけど、その辺りの事はいいのかな? まぁ、散々な目にあったキャット自ら何か言うことはないだろうし、彼女がマックスとの世界を壊そうとは思わないだろうけれど、誰かが彼女を脅迫して聞き出そうとするかもしれないよね? と、ずーっとキャットを生かしておくのはおかしいと思っている感じになっちゃってるけど、何度も言うけど死んで欲しいわけじゃなくて、なんとなく無理やり感があるというか、しっくりこない感じがあるんだよね。何故そこまで名もなき男がキャットの幸せにこだわるのか🤔
映画はキャットとマックスが去って行く後ろ姿で終わる。このラストにしたのは、名もなき男が守ったものは人々のささやな幸せであるということを象徴しているのだと思うし、これだけ大風呂敷広げた世界観の落としどころとしては、この感じで良かったのかなとは思う。まぁ、ニールとのあの感じで終わりでもいいと思うけれども。
そもそもの発端となった未来の科学者が誰なのか? 今回アルゴリズムを回収したことで未来がどうなるのか? 作戦の黒幕だった名もなき男は何故こんな回りくどい作戦を立てたのか? ニールはともかく、アイブスと名もなき男は秘密保持のためい本当に命を絶つのか? となると、作戦自体はどうなるのか? などなど謎だらけ🥴
なんだけど! そんなの全く関係ないくらいおもしろくて、見終わった時点でほとんど理解できていなかったけど、なんだかすごいものを見た感があった。そもそも、前述の疑問点も作中で語られていたのに理解できてなかっただけかもしれないし😅
キャストは皆良かった。アイブス素敵だなと思ってたら、まさかのアーロン・テイラー=ジョンソン。全く気付いてなくてビックリ💦 プリヤのディンプル・カパディアも敵か味方か分からない感じが良かったし、キャットのエリザベス・デビッキは190cmの長身で、クラシカルな高級スーツを着こなして素敵✨ アクションシーンもこなしヒロインを好演。正直、自分の中ではしっくりこなかったケネス・ブラナーのセイターだったけど、さすがの存在感ではあった。
名もなき男のジョン・デイヴィッド・ワシントンは初めて見たけど、とてもカッコよかった。デンゼル・ワシントンの息子と知ってビックリ😲 見事に作品を引っ張ったと思う。しかし、何といってもニールのロバート・パティンソンが良かった! 正直『トワイライト』シリーズ(感想は コチラと
コチラと コチラ)の役が好みでなく、どうも苦手意識があった。でも今作めっちゃいいです
コチラ)の役が好みでなく、どうも苦手意識があった。でも今作めっちゃいいです 頭が良くてアクションもこなすけど、主人公のサポートに徹するニールを、まさにそのままに出過ぎることなく存在感を示す。自分の運命を知りながら任務に向かう姿が最高にカッコイイ✨ ファンにはなってないけど、とても良い役者だと認識を新たにした。
頭が良くてアクションもこなすけど、主人公のサポートに徹するニールを、まさにそのままに出過ぎることなく存在感を示す。自分の運命を知りながら任務に向かう姿が最高にカッコイイ✨ ファンにはなってないけど、とても良い役者だと認識を新たにした。
ホイテ・ヴァン・ホイテマの映像が相変わらずカッコイイ✨ 特に逆行時の映像は、下手するとコミカルになってしまうけれど、スタイリッシュな感じにしているのがスゴイ。ずっと不安をあおる感じのルドヴィグ・ゴランソンの音楽も効果的。そして音響もスゴイ! おそらくこの辺りの技術部門はアカデミー賞取るのでは? まぁ、どんな形であれ開催されればの話ですが😅
ということで、せっかく公開初日に見に行ったのに書くのが遅くて1ヶ月以上経ってしまった💦 でも、まだ公開中だと思う。今更感満載だけど、とにかく絶対に映画館で見ることをオススメする!
 『TENET テネット』公式サイト
『TENET テネット』公式サイト

 コチラ)
コチラ)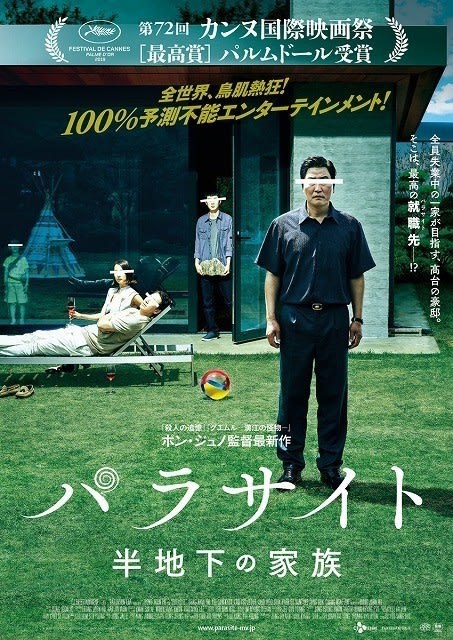
 コチラ)
コチラ)


 コチラ)
コチラ) 【参考:過去のmaru's BEST】
【参考:過去のmaru's BEST】













 ネタバレありです! 結末にも触れています!
ネタバレありです! 結末にも触れています! でも、めちゃめちゃおもしろかった! ノーラン節炸裂です!
でも、めちゃめちゃおもしろかった! ノーラン節炸裂です!
 死ぬの
死ぬの 😲
😲