'10.04.23 『RAILWAYS ~49歳で電車の運転士になった男の物語』(試写会)@よみうりホール
yaplog!で当選。いつもありがとうございます。49歳で電車の運転手になった元エリートサラリーマンの話。たしか実話ベースだった気がするけど違ったかな? ちょっと気になったので応募、見事当選した。
*ネタバレありです!
 「大手電器メーカー企画室長の筒井肇は、同期の親友が工場長を勤める工場を閉鎖させる。親友は見事に工場を閉めた後、事故に合ってしまう。そんな時、実家の母が倒れたという知らせが入る。末期ガンで余命わずかとのこと。悩んだ末に肇が出した結論は、幼い頃の夢だった電車の運転手になることだった…」という話。これはなかなか良かった。ちょっと、ところどころやり過ぎというか、あまりにもベタなシーンが気になるけれど、全体的に流れがよかったし、役者さん達が上手いので、落ち着いて見られて、じんわり感動する作品になっている。
「大手電器メーカー企画室長の筒井肇は、同期の親友が工場長を勤める工場を閉鎖させる。親友は見事に工場を閉めた後、事故に合ってしまう。そんな時、実家の母が倒れたという知らせが入る。末期ガンで余命わずかとのこと。悩んだ末に肇が出した結論は、幼い頃の夢だった電車の運転手になることだった…」という話。これはなかなか良かった。ちょっと、ところどころやり過ぎというか、あまりにもベタなシーンが気になるけれど、全体的に流れがよかったし、役者さん達が上手いので、落ち着いて見られて、じんわり感動する作品になっている。
49歳で電車の運転手になるという設定が、夢を叶えるにはずいぶん遅いスタートであるという点や、その夢が電車の運転手という、これまた49歳で挑戦するにはちょっとビックリな職業であることを除けば、仕事に追われ生活に潤いをなくした主人公が、ふと立ち止まって夢に向かって進んで行くストーリーとしては、とっても王道。だから何となく話の展開は分かる。前半、肇がキリキリ仕事に追われている様子が描かれて、それがやや長い気もするけれど、そこで肇が取締役に推薦されるくらいきちんと仕事ができる人物であるから、このビックリ・チャレンジもちゃんとできるんだということに説得力がある。それは肇がエリートで選ばれた人間だからということじゃなくて、きちんと仕事に取り組む人物であるということ。そして働く場所や、仕事の種類は違っても、やっぱり鍛えられているということ。それは面接でのそつのない対応もそうだし、 実際勤務についてからの危機管理能力なんかもそう。上手く言えないけど、瞬時に判断が下せるというか… それはもちろん、肇がエリートであることが、より説得力のある感じにしていることは間違いないけれど。この辺りは同じく新人運転手の宮田大吾との対比となっている。
この大吾にも実はドラマがあって、夢が破れた後の人生に絶望している。この感じもとっても王道で、正直特別必要ない気がしないでもない。後に彼が原因である事件が起こる。その事件自体についても、ちょっとやり過ぎな気がしないでもないけど、前から伏線が貼ってあって流れとしては上手い。この件がもとで肇は、辞表を提出することになる。その辺りは"責任"を負うという管理職に就いていた人である感じや、肇の生真面目さなんかを表しているのだと思う。それは仕事人間であったということだけではなく、自分の夢に対しての責任でもあるのかなと思ったりもする。ただねぇ… その後のシーンが(笑) まぁ、王道と言われれば、これ以上にないくらい王道ではあるのだけど、ちょっとあまりにも… これは何とかならなかったかな(笑) というわけで、そういうベタなシーンがところどころ入ってくるのが若干気がかりではある。娘が入院中の祖母の病室の窓に向かって、顔を見せてと叫ぶシーンは、祖母に元気になって欲しい一心であるということが大前提にあっても、かなりベタ。まぁ、病院で大騒ぎしちゃダメでしょというツッコミはあえてしませんが(笑)
もう少しだけ気になる点としては、肇が乗客が荷物を忘れたり、落としたりするのを放っておけず、手助けして進行時間を乱してしまうというエピソード。これは、自分が職務をまっとうするためには、親友の工場さえも閉鎖させるような人であった肇が、母の病気や親友の死に際して、人生を見つめ直し、人間らしく生きているということを表しているし、伏線でもあるのだけれど、ちょっと多いかな(笑) そんなにみんなウッカリしてないでしょう。でも、それがまたキリキリしている東京と、のんびりしている地方の対比としているのだと思う。個人的には今のところ東京から離れて住むことは考えられないし、地方の風景の美しさや、のんびりとした雰囲気は好きだけれど、あまりに都会はゆとりがなくて人間味に乏しく、田舎暮らしこそ人間的な暮らしという感じには、全面的に賛成というわけにはいかないのだけれど…
と、まぁ気になるシーンはあるのだけど、全体の流れがいいのと、役者さん達が上手いので、全体的にはじんわり感動できる作りになっている。49歳で運転手になれるのか?という疑問も、応募資格20歳以上というザックリとした説明で解決するのもいいし、きちんと研修場面を描いているので、肇が運転手になることにも説得力があった。東京で研修を受けることになるけどという面接での質問に、「東京に持ち家があります!」と即答するのもおもしろかった。研修シーンが楽しそうでよかった。多分、京王電鉄の講師役で鉄で有名なホリプロの南田マネージャーが出てたのが個人的にツボ。
そして、バタデンこと一畑電車がイイ! 明治44(1911)年創業。宍道湖沿いを2両の電車が走る。払い下げ車両も走っているみたいだけど、この作品にも登場するデハ二50形は昭和8年から走っているそうで、現役車両としては日本最古級。これがカワイイ! オレンジの車体がなんともレトロでまるでおもちゃみたい。もちろんドアも手動式。デハニには意味があって、作品内で肇がうれしそうに答えていたけど忘れてしまった(笑) 運転席と客車は分かれていなくて、ホントに簡単な仕切り棒だけなのにはビックリ。実はこれも伏線となっている。駅もレトロな感じで感じでいい。田舎の風景の中をカワイイ電車が2両走っている姿はホントに和む。自身の田舎はないので、この風景は自分のものではないけれど、なんだか懐かしい気がするのはやっぱり原風景なのかな。そのカワイイ電車を守る整備士さん達のエピソードもよかった。
 そして、これは家族再生の話でもある。仕事一筋で家庭を省みなかった肇。一応、会話はしているけれど、上の空なことに肇だけが気づいていない。大学生の娘も、最近ハーブショップを開いた妻も、肇のことは諦めている。女の人は話すことでコミュニケーションを取ろうとする。もちろん、そうでない人もいるとは思うけれど… 例えば、いつも買っている洗剤が、今日は100円安かったとか、男の人にはたわいもない話でも聞き流されるのは辛い。外で仕事をしているのと、専業主婦では見ている世界が違う。それはもちろん、どちらが上で、どちらが下かという問題じゃない。そもそも、みんな見てる世界違うと思うし。でも、だからこそ「洗剤が100円安かった」を、取るに足らないことだという態度を取られたら、自分を否定されたように感じてしまうのかも。もちろん、毎回いちいちそんな風に思っていないだろうけれど、その時感じた違和感や淋しさが積み重なって諦めてしまうのかも。その感じは短いけれど、前半のシーンで伝わってきた。でも、全員それぞれの範囲内でそれぞれを心配しているし、それぞれのやり方で気遣っているのも伝わってくる。だから、会社を辞めたことを伝えた時に妻が言う「あなた息切れしてたから」という言葉には説得力があった。お互い、それぞれ大切なものを見つけて、それはたまたま一緒には出来ないのであれば、夫婦2人の選択もありなのかも。変に支える妻に描かなかったのは好感が持てる。ただ、少し妻の存在感が薄かった気もするけれど。
そして、これは家族再生の話でもある。仕事一筋で家庭を省みなかった肇。一応、会話はしているけれど、上の空なことに肇だけが気づいていない。大学生の娘も、最近ハーブショップを開いた妻も、肇のことは諦めている。女の人は話すことでコミュニケーションを取ろうとする。もちろん、そうでない人もいるとは思うけれど… 例えば、いつも買っている洗剤が、今日は100円安かったとか、男の人にはたわいもない話でも聞き流されるのは辛い。外で仕事をしているのと、専業主婦では見ている世界が違う。それはもちろん、どちらが上で、どちらが下かという問題じゃない。そもそも、みんな見てる世界違うと思うし。でも、だからこそ「洗剤が100円安かった」を、取るに足らないことだという態度を取られたら、自分を否定されたように感じてしまうのかも。もちろん、毎回いちいちそんな風に思っていないだろうけれど、その時感じた違和感や淋しさが積み重なって諦めてしまうのかも。その感じは短いけれど、前半のシーンで伝わってきた。でも、全員それぞれの範囲内でそれぞれを心配しているし、それぞれのやり方で気遣っているのも伝わってくる。だから、会社を辞めたことを伝えた時に妻が言う「あなた息切れしてたから」という言葉には説得力があった。お互い、それぞれ大切なものを見つけて、それはたまたま一緒には出来ないのであれば、夫婦2人の選択もありなのかも。変に支える妻に描かなかったのは好感が持てる。ただ、少し妻の存在感が薄かった気もするけれど。
キャストはみな良かったと思う。娘役の本仮屋ユイカは、特別上手いとは思わなかったけど、滑舌良くセリフが聞き取れて、普通の女子大生をきちんと演じていたと思う。妻役の高島礼子はやや見せ場が少ないながら、迷いつつ自分の夢と夫の夢とを尊重する妻をきちんと演じていたと思う。親友役の遠藤憲一は好きな役者さん。彼の存在が肇を立ち止まらせる役でキーマン。生きる速度が違ってしまった親友を見送る表情が良かった。肇の決意に説得力があった。こちらも好きな役者さんで、ヒロトの弟甲本雅裕が入社後の指導担当者を演じている。初めて運転した電車の切符を記念にくれたり、鉄なんだろうなって感じが微笑ましい。母親役の奈良岡朋子がさすがの存在感。ガンが進行してどんどん小さくなってしまうのが悲しい。でも、その姿に自分の母親を重ねてしまう。幸い両親とも元気でいてくれているけれど、いずれこんな風に別れる日が来るのだと思うと切なくて泣いてしまった。何をしてても、自分が楽しければそれでいいと言うセリフがいい。まるごと受け止めているということ。何があっても親だけは受け入れてくれるんだと思ってまた泣くみたいな(笑)
肇役の中井貴一はやっぱり上手い。この役すごく合ってると思うし。エリート時代の仕事に追われて、ピリピリしているのも、運転手になって責任を取って辞表を提出するのも、彼がとっても真面目だから。よく考えると大企業のエリートから、49歳で運転手になるという、わりと共感しにくい設定ながら、その息切れやそうせずにいられない感じには、何となく思いあたるふしがあって、すんなり入ってくるし、共感できる。前半と後半では別人の様に人が変わるけど、そこにも違和感がない。基本は彼が真面目だからだということに説得力がある。ややキャラ作りすぎな脚本ではあるけれど、コミカルな感じも入れつつサラリと演じているので、気にならない。なにより研修中からずっと楽しそう。その感じが良かった。でも、老けたね… そして横分け(笑)
監督は島根県出身とのことで、島根をとっても美しく描いている。なによりバタデンがカワイイ! 宍道湖沿いを走る姿は鉄じゃなくても乗りたくなる。中高年が夢を叶える話としても、家族再生の話としても、時々やり過ぎちゃうけど楽しめる。そして、鉄だったら絶対楽しいと思う。
そんなに重くなく、サラリと感動したい方、そして鉄の方にオススメ。
 『RAILWAYS』Official site
『RAILWAYS』Official site
yaplog!で当選。いつもありがとうございます。49歳で電車の運転手になった元エリートサラリーマンの話。たしか実話ベースだった気がするけど違ったかな? ちょっと気になったので応募、見事当選した。
*ネタバレありです!
 「大手電器メーカー企画室長の筒井肇は、同期の親友が工場長を勤める工場を閉鎖させる。親友は見事に工場を閉めた後、事故に合ってしまう。そんな時、実家の母が倒れたという知らせが入る。末期ガンで余命わずかとのこと。悩んだ末に肇が出した結論は、幼い頃の夢だった電車の運転手になることだった…」という話。これはなかなか良かった。ちょっと、ところどころやり過ぎというか、あまりにもベタなシーンが気になるけれど、全体的に流れがよかったし、役者さん達が上手いので、落ち着いて見られて、じんわり感動する作品になっている。
「大手電器メーカー企画室長の筒井肇は、同期の親友が工場長を勤める工場を閉鎖させる。親友は見事に工場を閉めた後、事故に合ってしまう。そんな時、実家の母が倒れたという知らせが入る。末期ガンで余命わずかとのこと。悩んだ末に肇が出した結論は、幼い頃の夢だった電車の運転手になることだった…」という話。これはなかなか良かった。ちょっと、ところどころやり過ぎというか、あまりにもベタなシーンが気になるけれど、全体的に流れがよかったし、役者さん達が上手いので、落ち着いて見られて、じんわり感動する作品になっている。49歳で電車の運転手になるという設定が、夢を叶えるにはずいぶん遅いスタートであるという点や、その夢が電車の運転手という、これまた49歳で挑戦するにはちょっとビックリな職業であることを除けば、仕事に追われ生活に潤いをなくした主人公が、ふと立ち止まって夢に向かって進んで行くストーリーとしては、とっても王道。だから何となく話の展開は分かる。前半、肇がキリキリ仕事に追われている様子が描かれて、それがやや長い気もするけれど、そこで肇が取締役に推薦されるくらいきちんと仕事ができる人物であるから、このビックリ・チャレンジもちゃんとできるんだということに説得力がある。それは肇がエリートで選ばれた人間だからということじゃなくて、きちんと仕事に取り組む人物であるということ。そして働く場所や、仕事の種類は違っても、やっぱり鍛えられているということ。それは面接でのそつのない対応もそうだし、 実際勤務についてからの危機管理能力なんかもそう。上手く言えないけど、瞬時に判断が下せるというか… それはもちろん、肇がエリートであることが、より説得力のある感じにしていることは間違いないけれど。この辺りは同じく新人運転手の宮田大吾との対比となっている。
この大吾にも実はドラマがあって、夢が破れた後の人生に絶望している。この感じもとっても王道で、正直特別必要ない気がしないでもない。後に彼が原因である事件が起こる。その事件自体についても、ちょっとやり過ぎな気がしないでもないけど、前から伏線が貼ってあって流れとしては上手い。この件がもとで肇は、辞表を提出することになる。その辺りは"責任"を負うという管理職に就いていた人である感じや、肇の生真面目さなんかを表しているのだと思う。それは仕事人間であったということだけではなく、自分の夢に対しての責任でもあるのかなと思ったりもする。ただねぇ… その後のシーンが(笑) まぁ、王道と言われれば、これ以上にないくらい王道ではあるのだけど、ちょっとあまりにも… これは何とかならなかったかな(笑) というわけで、そういうベタなシーンがところどころ入ってくるのが若干気がかりではある。娘が入院中の祖母の病室の窓に向かって、顔を見せてと叫ぶシーンは、祖母に元気になって欲しい一心であるということが大前提にあっても、かなりベタ。まぁ、病院で大騒ぎしちゃダメでしょというツッコミはあえてしませんが(笑)
もう少しだけ気になる点としては、肇が乗客が荷物を忘れたり、落としたりするのを放っておけず、手助けして進行時間を乱してしまうというエピソード。これは、自分が職務をまっとうするためには、親友の工場さえも閉鎖させるような人であった肇が、母の病気や親友の死に際して、人生を見つめ直し、人間らしく生きているということを表しているし、伏線でもあるのだけれど、ちょっと多いかな(笑) そんなにみんなウッカリしてないでしょう。でも、それがまたキリキリしている東京と、のんびりしている地方の対比としているのだと思う。個人的には今のところ東京から離れて住むことは考えられないし、地方の風景の美しさや、のんびりとした雰囲気は好きだけれど、あまりに都会はゆとりがなくて人間味に乏しく、田舎暮らしこそ人間的な暮らしという感じには、全面的に賛成というわけにはいかないのだけれど…
と、まぁ気になるシーンはあるのだけど、全体の流れがいいのと、役者さん達が上手いので、全体的にはじんわり感動できる作りになっている。49歳で運転手になれるのか?という疑問も、応募資格20歳以上というザックリとした説明で解決するのもいいし、きちんと研修場面を描いているので、肇が運転手になることにも説得力があった。東京で研修を受けることになるけどという面接での質問に、「東京に持ち家があります!」と即答するのもおもしろかった。研修シーンが楽しそうでよかった。多分、京王電鉄の講師役で鉄で有名なホリプロの南田マネージャーが出てたのが個人的にツボ。
そして、バタデンこと一畑電車がイイ! 明治44(1911)年創業。宍道湖沿いを2両の電車が走る。払い下げ車両も走っているみたいだけど、この作品にも登場するデハ二50形は昭和8年から走っているそうで、現役車両としては日本最古級。これがカワイイ! オレンジの車体がなんともレトロでまるでおもちゃみたい。もちろんドアも手動式。デハニには意味があって、作品内で肇がうれしそうに答えていたけど忘れてしまった(笑) 運転席と客車は分かれていなくて、ホントに簡単な仕切り棒だけなのにはビックリ。実はこれも伏線となっている。駅もレトロな感じで感じでいい。田舎の風景の中をカワイイ電車が2両走っている姿はホントに和む。自身の田舎はないので、この風景は自分のものではないけれど、なんだか懐かしい気がするのはやっぱり原風景なのかな。そのカワイイ電車を守る整備士さん達のエピソードもよかった。
 そして、これは家族再生の話でもある。仕事一筋で家庭を省みなかった肇。一応、会話はしているけれど、上の空なことに肇だけが気づいていない。大学生の娘も、最近ハーブショップを開いた妻も、肇のことは諦めている。女の人は話すことでコミュニケーションを取ろうとする。もちろん、そうでない人もいるとは思うけれど… 例えば、いつも買っている洗剤が、今日は100円安かったとか、男の人にはたわいもない話でも聞き流されるのは辛い。外で仕事をしているのと、専業主婦では見ている世界が違う。それはもちろん、どちらが上で、どちらが下かという問題じゃない。そもそも、みんな見てる世界違うと思うし。でも、だからこそ「洗剤が100円安かった」を、取るに足らないことだという態度を取られたら、自分を否定されたように感じてしまうのかも。もちろん、毎回いちいちそんな風に思っていないだろうけれど、その時感じた違和感や淋しさが積み重なって諦めてしまうのかも。その感じは短いけれど、前半のシーンで伝わってきた。でも、全員それぞれの範囲内でそれぞれを心配しているし、それぞれのやり方で気遣っているのも伝わってくる。だから、会社を辞めたことを伝えた時に妻が言う「あなた息切れしてたから」という言葉には説得力があった。お互い、それぞれ大切なものを見つけて、それはたまたま一緒には出来ないのであれば、夫婦2人の選択もありなのかも。変に支える妻に描かなかったのは好感が持てる。ただ、少し妻の存在感が薄かった気もするけれど。
そして、これは家族再生の話でもある。仕事一筋で家庭を省みなかった肇。一応、会話はしているけれど、上の空なことに肇だけが気づいていない。大学生の娘も、最近ハーブショップを開いた妻も、肇のことは諦めている。女の人は話すことでコミュニケーションを取ろうとする。もちろん、そうでない人もいるとは思うけれど… 例えば、いつも買っている洗剤が、今日は100円安かったとか、男の人にはたわいもない話でも聞き流されるのは辛い。外で仕事をしているのと、専業主婦では見ている世界が違う。それはもちろん、どちらが上で、どちらが下かという問題じゃない。そもそも、みんな見てる世界違うと思うし。でも、だからこそ「洗剤が100円安かった」を、取るに足らないことだという態度を取られたら、自分を否定されたように感じてしまうのかも。もちろん、毎回いちいちそんな風に思っていないだろうけれど、その時感じた違和感や淋しさが積み重なって諦めてしまうのかも。その感じは短いけれど、前半のシーンで伝わってきた。でも、全員それぞれの範囲内でそれぞれを心配しているし、それぞれのやり方で気遣っているのも伝わってくる。だから、会社を辞めたことを伝えた時に妻が言う「あなた息切れしてたから」という言葉には説得力があった。お互い、それぞれ大切なものを見つけて、それはたまたま一緒には出来ないのであれば、夫婦2人の選択もありなのかも。変に支える妻に描かなかったのは好感が持てる。ただ、少し妻の存在感が薄かった気もするけれど。キャストはみな良かったと思う。娘役の本仮屋ユイカは、特別上手いとは思わなかったけど、滑舌良くセリフが聞き取れて、普通の女子大生をきちんと演じていたと思う。妻役の高島礼子はやや見せ場が少ないながら、迷いつつ自分の夢と夫の夢とを尊重する妻をきちんと演じていたと思う。親友役の遠藤憲一は好きな役者さん。彼の存在が肇を立ち止まらせる役でキーマン。生きる速度が違ってしまった親友を見送る表情が良かった。肇の決意に説得力があった。こちらも好きな役者さんで、ヒロトの弟甲本雅裕が入社後の指導担当者を演じている。初めて運転した電車の切符を記念にくれたり、鉄なんだろうなって感じが微笑ましい。母親役の奈良岡朋子がさすがの存在感。ガンが進行してどんどん小さくなってしまうのが悲しい。でも、その姿に自分の母親を重ねてしまう。幸い両親とも元気でいてくれているけれど、いずれこんな風に別れる日が来るのだと思うと切なくて泣いてしまった。何をしてても、自分が楽しければそれでいいと言うセリフがいい。まるごと受け止めているということ。何があっても親だけは受け入れてくれるんだと思ってまた泣くみたいな(笑)
肇役の中井貴一はやっぱり上手い。この役すごく合ってると思うし。エリート時代の仕事に追われて、ピリピリしているのも、運転手になって責任を取って辞表を提出するのも、彼がとっても真面目だから。よく考えると大企業のエリートから、49歳で運転手になるという、わりと共感しにくい設定ながら、その息切れやそうせずにいられない感じには、何となく思いあたるふしがあって、すんなり入ってくるし、共感できる。前半と後半では別人の様に人が変わるけど、そこにも違和感がない。基本は彼が真面目だからだということに説得力がある。ややキャラ作りすぎな脚本ではあるけれど、コミカルな感じも入れつつサラリと演じているので、気にならない。なにより研修中からずっと楽しそう。その感じが良かった。でも、老けたね… そして横分け(笑)
監督は島根県出身とのことで、島根をとっても美しく描いている。なによりバタデンがカワイイ! 宍道湖沿いを走る姿は鉄じゃなくても乗りたくなる。中高年が夢を叶える話としても、家族再生の話としても、時々やり過ぎちゃうけど楽しめる。そして、鉄だったら絶対楽しいと思う。
そんなに重くなく、サラリと感動したい方、そして鉄の方にオススメ。
 『RAILWAYS』Official site
『RAILWAYS』Official site










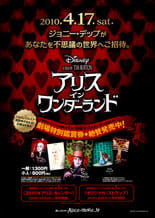





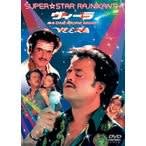
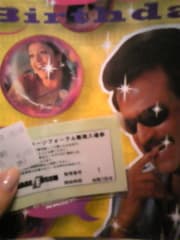
 スーパースター & 整理券1番
スーパースター & 整理券1番
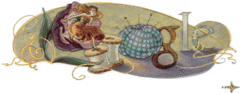
 (笑)
(笑)





