毎度のGoogleのロゴがこんなことに!
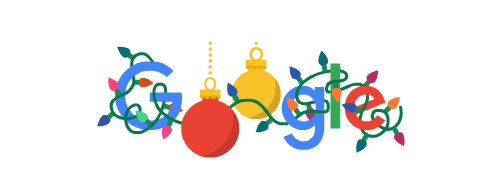
2019年ハッピーホリデー
3日目
今日はクリスマスってことで、毎度のWikipediaから引用
クリスマス(英: Christmas)は「キリストのミサ」という意味で、
あくまで誕生を祝う日であって、イエス・キリストの誕生日ではない。
え キリストの誕生日じゃないの
キリストの誕生日じゃないの
毎年12月25日に祝われるが、正教会のうちユリウス暦を使用するものは、
ただし、キリスト教で最も重要な祭と位置づけられるのはクリスマスではなく、復活祭である。
キリスト教に先立つユダヤ教の暦、ローマ帝国の暦、およびこれらを引き継いだ教会暦では,
現代の常用時とは異なり、日没を一日の境目としているので、
クリスマス・イヴと呼ばれる12月24日夕刻から12月25日朝までも、
教会暦上はクリスマスと同じ日に数えられる。
したがって、教会暦ではクリスマスは「12月24日の日没から12月25日の日没まで」である。
キリスト教国(en:christendom)以外でも、年中行事としても楽しまれ、
ジングルベルなどのクリスマスソングは多くの人に親しまれている。
うーん💦 この時点でもう難しい😅
新約聖書には、イエス・キリストの誕生日を特定する記述は無い。
え そうなの
そうなの
概要、起源、名称などの記載が続くけど長いので割愛😌
日本のクリスマスを少し抜粋して終わりとする。
1552年(天文21年)に周防国山口(現在の山口県山口市)において、
カトリック教会(イエズス会)の宣教師であるコスメ・デ・トーレスらが、
日本人信徒を招いて降誕祭のミサを行ったのが、日本で初めてのクリスマスである。
しかし、その後江戸幕府の禁教令によってキリスト教は禁止されたことで、
明治の初めまでの200年以上の間、隠れキリシタン以外には全く受け入れられることはなかった。
思ったより早くてビックリ😲
日本でクリスマスが受け入れられたのは、
その頃からクリスマス商戦が始まったことが大きな契機であった。
なんと! まさかの明治屋😲
多くのカフェや喫茶店においてはクリスマス料理の献立を用意し、
その店員はクリスマスの仮装をして客を迎えた。
1948年(昭和23年)7月20日に「国民の祝日に関する法律」が施行され、
大正天皇祭は休日から外されたが、
以降もクリスマスは年中行事として定着し、行事も盛大に行われるようになった。
なるほど。
しかし・・・
日本でもクリスマスは大きなイベントとして定着したが、
やはり本場のキリスト教圏と比べるとその規模は小さいという指摘もある。
2014年に旅行サイトのスカイスキャナーが発表した
「宗教的あるいは個人的、思想的な理由などでクリスマスを祝う習慣がなく、
クリスマスの大騒ぎを避けたいと思っている」人に勧める
「クリスマスを避けるために行く国トップ10」のランキングでは、
仏教国のタイ、社会主義国家の中国や北朝鮮などを押さえ、日本が1位となっている。
「サンタをたまに見かけるかもしれないが、
日本はクリスマスが祝日でなく、12月25日も人々は普段通り仕事をする」ためである。
あら~😅
検索画面のロゴはこんな感じ


よいクリスマスを~🎄🎅


























※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます