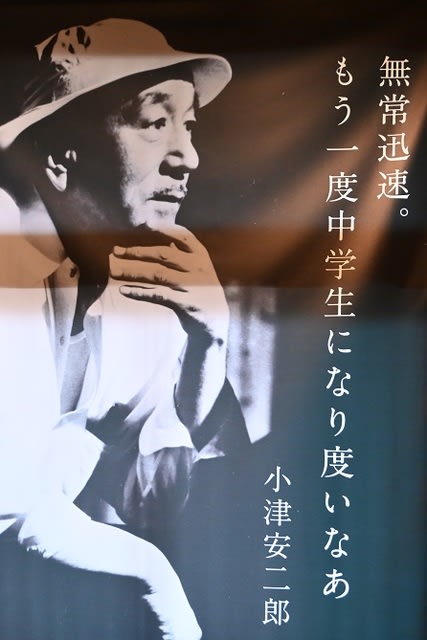鬼行列のトリは「役行者」と「鎮西八郎為朝」 ~上野天神祭 ⑤

「役行者列」のトリを務めるのは。もちろん、古代史のヒーロー、修験道の開祖「役行者」。
この行列は役行者が鬼を従えて、大峰山に入山する姿を表現するもので、1688~1704年頃に上野天神祭に加わったとされている。
伊賀流忍者の元祖ともいわれており、その面は初代藩主の藤堂高虎の眼病平癒の祈祷をした結果、早く癒えたことから、その返礼として寄進を受けたものと言われている。










もうひとつの行列は日本一の将軍といわれる、こちらも中世のヒーロー、鎮西八郎為朝(源為朝)の行列。
鬼ヶ島を征伐し、凱旋する姿を表現している。
鎮西八郎為朝の身の丈は7尺を越えたというから、ジャイアント馬場より高かったことになり、その威風堂々たるや・・・少し、滑稽である。







わんちゃんもびっくりである。