

これは2000年、二柄先生に紹介していただいた、京都のギャラリーでの個展のDMですが、そこに賛辞を寄せていただいたものです。
もちろん、根源現成とまではいきませんが、その方向に向かっていることを認めていただいた内容で喜んだことを覚えています。
ところが今、先生の「東西美術史」を読みながら、私にはその溝を越えられないのではないかという疑問が沸き起こってきたのです。
なぜなら、私の制作方法はまさに先生の云う西洋絵画そのものと言っていいからです。下図を描き、鉛筆一本とはいえ、描き進むうちに修正もしますし、ことによったら部分的に描きなおすことさえします。まさに書の筆墨とは対照的な、つまり西洋絵画なのです。
しかし私はそれでも先生の所に行きたい。道はどこかにあるはずです。
「東西美術史」では、東西の統合を呼びかけながらも、現実に展開したのは、墨象芸術と西洋の抽象芸術が、戦後最接近をしたものの、数年で挫折した事実でした。
その後の墨象の動向を追いながら、結局「東西美術史」は芸術論として、東西の統合を果たすことが出来なかった。そのあとがきを読みながら、さどかし心残りではなかったかと思わざるを得ませんでした。
二柄先生の、根源現成の学説は、前回みましたように、書における特性に着想を得たものでした。
つまり、あらかじめスケッチして段階を踏みながら描くことが出来ない、一回きりの描線、そのスタイルに根源現成の表れを見たわけです。
そしてそれを(感性的なものを超える精神的なもの)と結論付けるのです。
すると私の絵はどうなるのでしょうか。
私の実感としては、二柄先生の提唱される根源現成の理論は私の精神的な支柱であり、その方向に一抹の迷いもありません。だとすれば、どこかにボタンのかけ違いがあるはずです。それは何なのでしょう。
それを知りたくて、ここまで書きながら考えを進めてまいりました。そしてようやく一つの光明を見たのです。
それが論者と作者の目の差異でした。視点の違いが引き起こした、たった一点の錯誤が、この論文にあったのです。
端的に言って、二柄先生(美学者)に見えなくて、私(作者)に見えた風景は、書の作品の背後にある反故紙の山です。
確かに書は、作品としてそのものだけを見る限り、あらかじめスケッチして描くことができない一回きりの描線、であることは間違いのない事なのですが、作者はその作品を世に出す前に、自分の気に入る作品が出来るまで何枚も同じものを書きます。そして作品以外は反故紙として捨てるわけですね。
たとえ偶然に最初の一枚が作者の気に入ったものだったとしても、その場合は反故紙は出ませんが、なおそこに、作者の感性による選択・決定があったわけです。
つまり西洋であれ東洋であれ、作者は、己の感性で作品を生み出すのであって、精神が造るのではないということです。
「東西美術史」のただ一つの欠点は、書の制作手段が持っている唯一無二の墨筆の画面を、精神の現れと読み解いたことだったのです。それはその部分だけを切り取って見る限り、正しい解釈ではありますが、しかし当の作者の内面はそうではなかった。そこには明確に己を主張する感性としての自己があったのです。
たとえもし精神が描いたとしても、それを作者の感性が愚作と認めれば、その作品はけっして世に出ることはないわけですし、そもそもそれは起こりえないということです。
もし作品が精神の現れだとするなら、この唯一無二の作品を、作者は己を無にし、宇宙と一体になって生み出したということであり。当然そのものの感性を通り越して、作品は自動生成されたとになるわけですね。作者は根源そのものとなって消えるしかない。
芸術家として、それに耐えられるものは一人もいないでしょう。
幸いなことに、書であっても、創作は精神によるのではなく、まさに己の発露たる感性が働いて世に生み出されていたのです。
それはつまり、私が絵を描き進めている状況となんら変わることのない創作過程だといえます。描きながら、自分の気に入る空間を作っていくその行程は、書道のように、進む道筋は違っても、最後に作品として世に出す決定を下す時点で相並ぶ訳ですね。そしてその決定は作者の感性というほかはないのです。
これらの作品、
制作過程や、その方法、道具や行為に、それこそ西洋と東洋の違いの中にさえ、私たちが芸術として認める一切のものは、精神ではなく感性が生み出しているということです。
なぜなら、すべての芸術は、その作者が、意志を持って作品を世に送り出すことなのですから。その時、その作品を「良し」とする主体は、人間たる当の作者以外にないのですね。そしてその作品を「良し」と判断するのはほかでもない作者の感性だという訳です。
もしそれが精神だとしたら、逆に恐ろしい風景が見えてくるでしょう。精神主義はいかなる場合でも、人間が口に出してはならないのです。
もちろん、二柄先生が精神主義を主張している訳ではありません。ただ精神の発露と言っている訳で、それは傾倒に値する言葉なのです。問題は、その道筋の中に、ただ一点、すでに申し上げた、書の特性を精神の現れとする視点が問題を醸し出す訳です。
まさに作者の作者たる証しは、精神ではなく、いのちそのものから生まれ出ている感性以外にはないということですね。
そもそも、精神とは、人を指す言葉ではないのです。精神とはその者に現れる思考の流れに見出される一つの傾向を指す言葉であり、心の状態を表す言葉ですから、それは心そのものではありません。
それゆえに、精神は良い意味で感性の発揚を促しますが、悪い意味では自由なる個性を阻害するわけですね。
つまり、心の本性は精神ではなく、感性なのです。
しかし決して、この指摘が、二柄先生の根源現成の理論を貶めるものではありません。
それはかえって、「東西美術史」に描かれた内容を深め、先生の念願であった東西美術の統合を可能にするものなのです。
至宝である「東西美術史」が、残念ながら世に広く浸透していない。その原因が私に生まれたような素朴な疑問にあるとするなら、そのとげを抜くだけでいいわけですし、
実際、根源現成の思想は芸術家にとっても、誰にとっても、今だ至宝と言えるものなのです。
私の考えでは、この「東西美術史」で描き出された東洋と西洋を統合する思想は五次元思考です。
奇しくも、一つの誤謬から導き出した根源現成の理論は、その意味で五次元になり損ねたのです。
五次元の本懐を見ながら、感性を見落としたために、時間の概念を失い、五次元となるはずの理論が空間とスケールという四次元になってしまったのだと思います。
時間の概念を失うと、五次元世界はただ動きを失った存在だけとなってしまい、そこから生まれる理論は理想論に終わってしまうしかないのです。































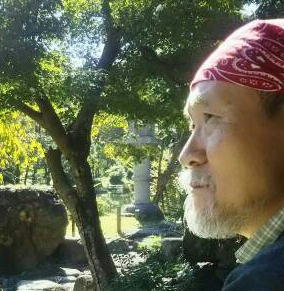

明から暗が見える
中間色から暗と明の橋渡りが
暗でも明でも明暗でもない実体から
ここ
が見える
さて
見えているのは
闇だろうか、ろうそくだろうか
ろうそくが消えると
さて
見えているのは
闇だろうか、己だろうか