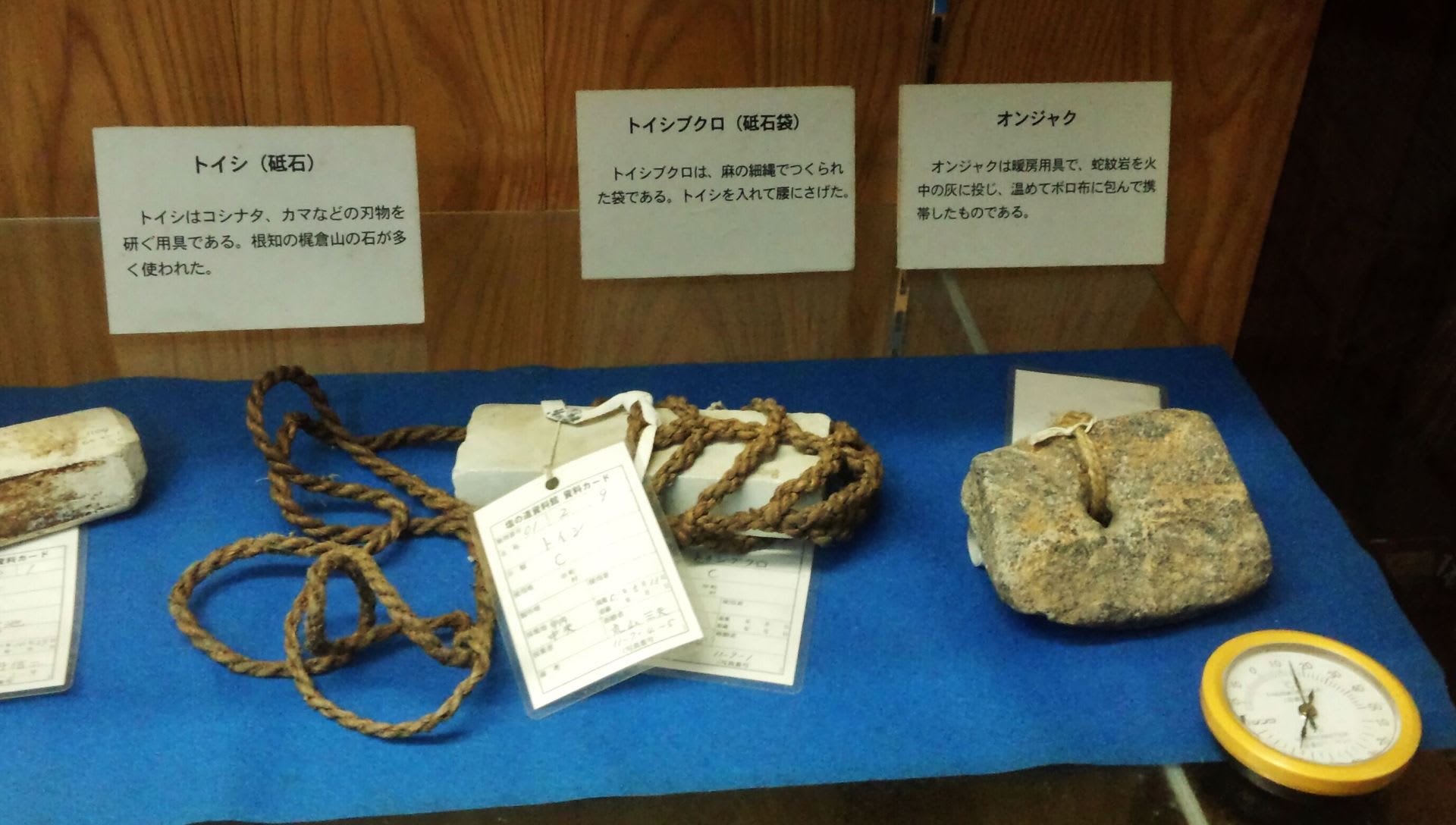節分が近くなると俄かに脚光を浴びるのが鬼。
以前のブログでインドの鬼について書いた事があるが、今回はその続き。

オートリクシャーに飾られた鬼

チャンナイの商店に飾られた鬼
鬼の姿は牛の角を生やして虎皮のパンツを纏い、金棒を手にするのが一般的で、これは平安時代に道教の影響によって生まれたものであるらしい。
当初のオニは目に見えないモノノケ(モノの気配)という意味で隠(オヌ)と呼ばれ、その後に中国語の鬼(キ)が当て字されたという。
モノノケのモノとは、魑魅魍魎や後年の怨霊などの人に禍する実体無き気配のことだろう。
牛の角と虎皮は、鬼門である丑寅の方角を象徴しているとの事だが、日本人に馴染みのある鬼の姿そっくりの魔除けキャラクターがインドにもいるのだ。
主に南インドのチェンナイ(旧マドラス)からケラーラ州にかけての商店の軒先や、三輪タクシーのオートリクシャーのテールに飾られており、地元の人に名前を聞いても「デビル」と英語名しか答えてくれないので、古い魔除けではないのかも知れない。
もしかしたら日本の鬼が輸入された?
インド人の誰に聞いても詳しい事が分からないが、インドでテレビを観ていたら新型テレビノコマーシャルに鬼のCGが出てきた事があり、最後に「ONIX」とメーカー名が出てきたのだ。

チェンナイの自動車修理工場に飾られた鬼の横に、椰子の実製のオニモドキが(笑)椰子の実は硬く、内部には滋養が蓄えられているという特質が強さを象徴しているのだろう・・・強いモノには魔が取り付けないのだ。
想像を逞しくすると、海外輸出向けの日本の家電メーカーONIXのマスコットキャラクターが鬼で、インド進出を機会に鬼の本場の一つである南インドに広まった?(笑)
モノの語源は、南インドの言語であるタミル語であるという説もあるのだ。
いずれにしても鬼は赤い口を大きくあけて、目を見開く顔付きをしている。本来はバイオカラーを象徴する赤鬼が基本だろうと思う。
日常は隠されている赤い身体内部を曝け出すような異様な面相は、怒りの表情であると共に生物にとって最も無防備な姿と言える。
内なるチカラの誇示・・・弱点を曝け出す事ができるのは強さの証拠で、顔付きだけで魔除けにはなるだろう。

鬼の面相は、糸魚川市の春の風物詩「けんか祭り」の魔除けであるジョウバの赤い顔、大きく見開いたギョロ目と口に良く似ている。
ジョウバは除魔と漢字表記するのである。
鬼もジョウバであり、魔除けなのだ。