




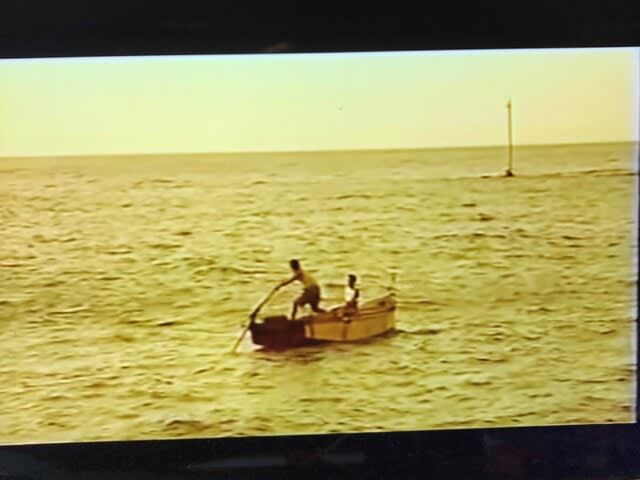


筒石でブラカトリ。



クールジャパンやインバウンドと、最近は外国に日本の良さを知って貰おうという気運が高まってきている。
でもなあ・・・肝心の日本人が日本の文化や伝統を外国人に語れるのかな?

私の子供の頃からある正月飾り。
英語が堪能でも、日本の文化を語れる日本人がどれだけいるのか?
例えば年中行事の花形といえる正月。
初詣やお年玉の慣習は残っていても、門松や正月飾り、お節料理を作って歳神様を迎える準備をする家がどれだけ残っているのか?

糸魚川の伝統的なお節料理も残していきたいが、自宅でお節料理を作る家も少なくなってきているようだ。
私の子供の頃は正月二日には年始客が次々と訪ねてきて賑やかだったが、最近は嫁いだ姉家族以外は親戚も来なくなった。
次世代に節目の行事や慣習を継承していかないと、「かってはこんな行事があった」という過去形になってしまうし、なりつつある。

そこで今年の正月は友人家族を招いて、総勢十人で賑わった正月。笑う門には福来る!

レンジでチンしたモチをモチと言えるのか?モチを火鉢で焼いて、膨らんでいく様を目の当たりにしないとモチ体験とは言えないと思うのだ。
今時の子供でも、宝引きやカルタ遊びといった昔の遊びに歓声を挙げる。
こんな昔ながらの正月の風景に癒される。
旅先のドライブインの便所にこんな張り紙が貼ってあった。
便器の外を小便で汚すなという婉曲的表現の注意書きだが、手書きの五七調の狂歌である事に注目したい。

いいぢゃないか。
風流である。
ドライブインは年季のいった古い焼肉屋だったが、店のオヤジさんが書いたのだろうか。
女性は知らないだろうが、男子トイレにはたまにこんな狂歌が貼られている事があり、俺の母校の糸魚川中学にも貼ってあった。
糸中の張り紙は、「一歩前進 心静かに手を添えて 外に散らすな 竿の露」とかと書いてあったと記憶している。
こっちは諧謔や捻りが少ないけど、用務員さんの仕事かな?
対して下は国道沿いの公衆トイレの張り紙・・・プラスチックだけどね。

国道の便所は、カチッとした(印刷?)横書きで、注意事項が直接的に書かれている。無味乾燥として風流じゃない。
古典落語「掛取り万歳」にこんな場面がある。
大晦日(オオツゴモリ)に長屋の店賃(タナチン・家賃のこと)を取りに来た家主(イエヌシ)に、貧乏で店賃を払えない男が言い訳をする。
直接的に言い訳をしないで、「人は好きなものには心奪われるっていうじゃねえか。」と、家主の趣味の狂歌で言い訳をするのだ。
男は如何に貧乏をしているかを次々に狂歌を詠みあげる。
「貧乏の この家(ヤ)に風情あり 質の流れに借金の山」・・・男
「いいねえ・・・山水かい。こうなると貧乏も風流だねえ~。」・・・家主
家主は風流な言い訳に関心して、借金返済を待って機嫌よく帰っていく。
己の貧乏でさえも諧謔で笑い飛ばす江戸庶民の文化があってこそ、ありそうでない笑い話が話芸として成立するのだ。
おおらかな時代である。
俺の好きな落語の話しをしても、オオツゴモリ?タナチン?質の流れ?という具合に、最近の若者は言葉の意味を知らないので、いちいち説明しないと通じないので苦労しますな。
若者じゃなくても、直接的表現を直接的にしか理解できない日本人が増えてきたように感じる。
まるで異文化の外人と会話している気分になる時がある。
四角四面な堅苦しい世の中になってきたのではないか?
子供の頃から落語好きで聴いていたが、子供でも意味の解らない言葉は前後の脈絡から察することができたし、古典落語は江戸から明治大正にかけて語り伝えられているので非常に練られており、誰が聴いても面白く出来ているのだ。
噺家さんも、現代人に馴染の薄くなった言葉や風俗を「まくら」でさりげなく説明をしてくれる。
まくらとは、落語本題に入る前の軽妙で簡素な説明・・・のようなもの。
つまり落語を聴くという事は、江戸庶民の教養講座であったという事ですな。
狂歌で婉曲的表現をする文化や古典落語は、共有された生活文化があって初めて同じイメージが持てるというモノ。
基層文化が失われては、言葉が通じないのは道理だ。
昭和の男としては寂しい限りですわ・・・まだ十分若いけどね。

くだんの焼肉ドライブインの便所入口には、昭和の匂いがプンプンするポスターが貼ってあった。
店の構えと雰囲気、客層も昭和そのもの。
駐車場にはカーテンで運転席を隠した長距離トラックがズラリと並んでいる。
運ちゃん達はドライブインで焼肉食って、そして本当はいけない事なのだけど、ビールでも飲んで寝ているのかな。
人間臭い、おおらかな時代の名残り。
運ちゃんのイビキは、古き佳き時代の挽歌だねえ。
ボタン雪が舞う冬の金沢市兼六園。
スキー場のない都会でも観光客で賑わっていた。

台湾からの観光客が、寒さに震えながら大勢歩いていたし、俺も「佳いなあ・・・」と想った。
雪が降って寒いところが佳いのだとさえ想える。

四百年前の殿様が愛した風景を、現代日本人も外国人も「佳い」と感じる。
雪景色に何とも言えない日本的情緒を感じるのだ。
前田公は粋な殿様ですな。

あまりに寒いので、お茶屋さんに入って抹茶セット(700円)で温まる。
たかが抹茶に700円は高いと思ったが、雪の日本庭園を観ながら古式ゆかしい日本家屋で喫する抹茶は得難い経験。
これぞ文化の価値というヤツで、安いもんだと納得できる。
糸魚川市は三月の新幹線開通に向けて、駅周辺の整備が進んでいる。
こざっぱりと綺麗になったけど、閑散として寒々しい風景だと不評のようだ。
どこにでもある、文化的奥行が感じられない近代的な街並みは、確かに寒々しく、人で賑わう場所とは想像できない。
利便性や経済効果を至上命題にして作られた建設工事は、野暮な風景ですなぁ。
以前にエキサイトブログでも紹介したのだけど、こないだフェイスブックで古い筒石漁港を紹介したら反響が高かったので、OCNブログでもアップ。
私が糸魚川市で一番好きな場所で、他県のお客さんが来ると必ず連れて行くのが今は使われていない古い筒石漁港である。
流木をそのまま使って作ったような野趣あふれる大雑把さが魅力で、夏の夕方にここで腰を下ろして読書したり夕焼けを眺めるのは乙なもの。
舟小屋のすぐ後ろが国道8号線。
丹後半島の伊根湾にはもっと凄い舟屋群があるけど、筒石漁港は内海ではなく、いきなり日本海の荒海が広がっている人の住まない舟小屋である。
目の前の海はあくまでも透明で、海の中はまるで竜宮城だ。
朽ち果ててはいるが、舟釘を打った伝統的な和船や櫓も置いてあるので、民俗学ファンも唸らずにはいられない。
残念ながら、これほど素晴らしい場所なのに、糸魚川の人でここの魅力を感じている人は少ないようだ。
夏の旧筒石漁港の海で潜ったりキャンプして遊んでいるのは信州の人ばかり。
青年会議所の人を案内したら存在さえ知らなかったのだ。
なぜ存在を知らないかというと、交通量の多い国道8号線のすぐ下にあるから気付かないらしい。
私の場合は海と船が好きだし、民俗学的野次馬根性が強いから車で通る度に気になっていて、5年前にUターン帰郷してから浜に降りてその素晴らしさに気付いたのである。


基礎コンクリートに注目!
波板トタンで生コンの型を作っている・・・この大雑把さがたまらない。
かっては筒石の集落のなかを国道8号線が通っていたらしいが、交通量が多くなって随分前に国道を海岸沿いに移動した機会に漁港をそのままにして、西に新しい近代的な漁港を作ったとのこと。
糸魚川市街地の浜もそうだが、国道が海岸に移設されると気軽に国道を横断して浜に降りていくことができなくなり、海からの距離ができてしまうようだ。
急激に進んだ海岸浸食で、テトラポットで浜が埋め尽くされたのも要因の一つ。
糸魚川人にとって海は近くて遠い存在になってしまった。
我々の祖先は、五千年も前に丸木舟にヒスイを積んで各地に運んでいた海洋民だったのにねえ・・・。
観光パンフレットにも載っていないのは勿体ない。
知人の外国人も観光スポットになるよ~って言ってた。
ヒスイ関連でパワースポットを糸魚川のウリにするのもいいけど、ヒスイだけが糸魚川の魅力じゃないぜ!
俺の生まれ育った寺町区はかって漁師町だった。
家の裏が野球ができるくらい広い砂浜で、子供達の格好の遊び場だった。
夏には学校帰りにフルチンで泳いで涼んだり、漁から戻った漁船を砂浜にで引上げる手伝いや地引網の手伝いに駆り出されたりした。
ガキ大将が付いてさえいれば、安心して盆過ぎの大きなウネリの海で面白がって泳いだ。
俺が好きだったのは、学校の帰り道に砂浜を通って廃屋になった古い漁師小屋を探検すること。ちょっとした冒険が身近にあった。
老人達も夕方になると夕涼みに浜に降りてきた。
<o:p></o:p>
おとつぁんやおっかさんも、網を繕う老漁師と呑気に談笑していた。
浜は社交場だったのだ。
<o:p></o:p>
ところが低学年の時に立派な姫川港が出来てから事情が一変した。
大きな防波堤が完成して海岸浸食が始まったのだ。
<o:p></o:p>
時を同じくして、国道8号線のバイパス道路が海と砂浜の間に完成した。
<o:p></o:p>
海に出るには交通量の激しい国道を横断しなければならないので、まず海で夕涼みする老人が姿を消した。そして学校帰りにフルチンで泳ぐ子供達も姿を消した。
<o:p></o:p>
海は近くて遠い存在になってしまった。
<o:p></o:p>
かって人で賑わった広い砂浜は、今ではテトラポットと石だらけの狭い海岸・・・寂しい風景。<o:p></o:p>
Uターン帰郷してから僅かに残る漁師小屋の記録を始めたが、今日、懐かしい小屋と再会した。それは押上区にあるコンクリート製の漁師小屋。
<o:p></o:p>

俺の子供時代には既に廃屋となっていたが、当時「海賊船」という地元のロックバンドのあんちゃん達がそこでドガチャカとバンドの練習をしていた。
<o:p></o:p>
あれから四十年近く経つが、噂ではまだ「海賊船」は現役で活動しているらしい。一体幾つになったんだぁ?
<o:p></o:p>
そしてこの場をお借りして「海賊船」に謝ります。練習中に小屋の中に爆竹を投げ入れて逃げたのは、寺町の悪ガキ達です。
<o:p></o:p>
でも俺はまだ小さかったので見ていただけです。
<o:p></o:p>
実行犯は上級生です・・・勘弁してくんないっちゃ!<o:p></o:p>
。<o:p></o:p>
<o:p></o:p>