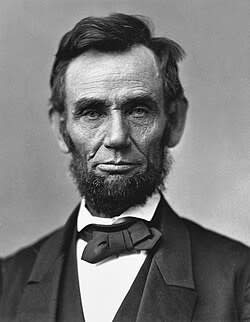
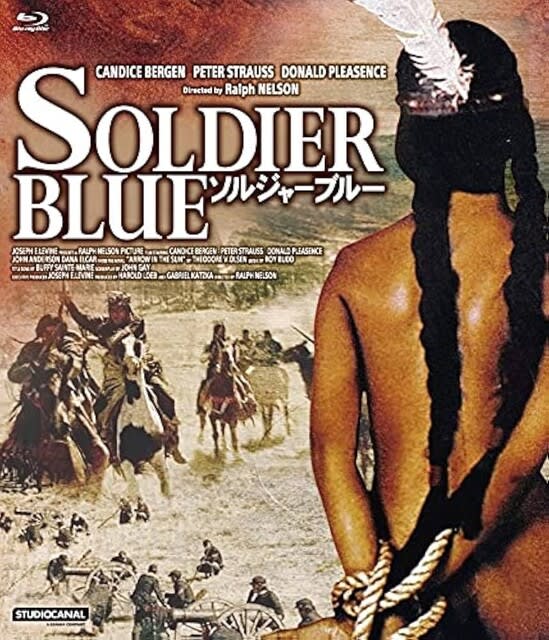

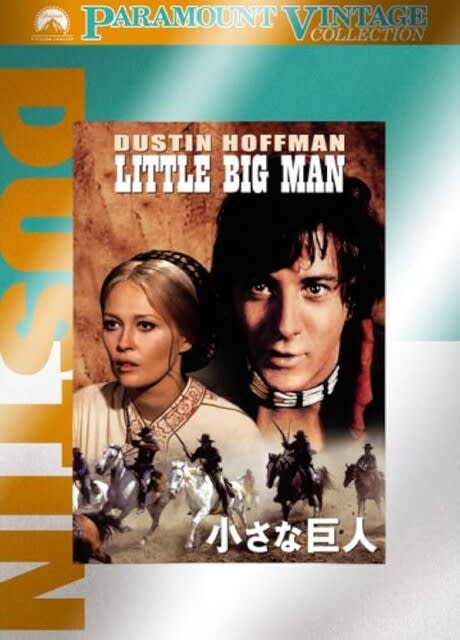
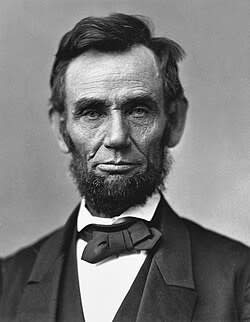
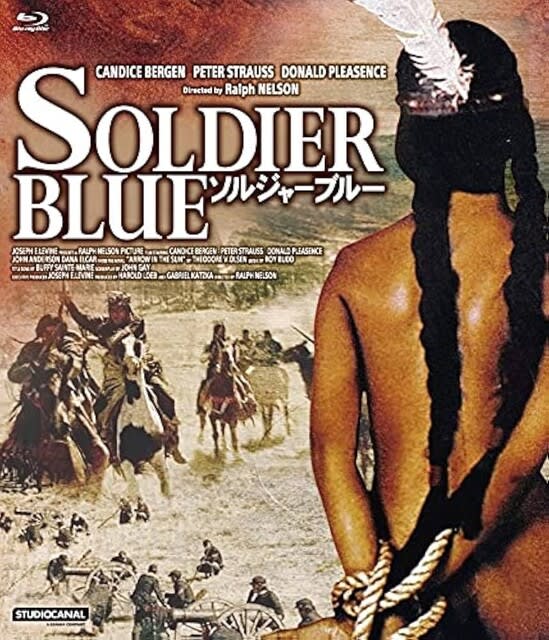

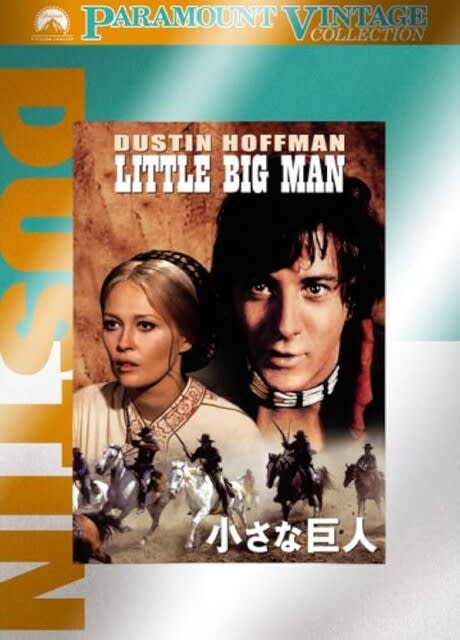




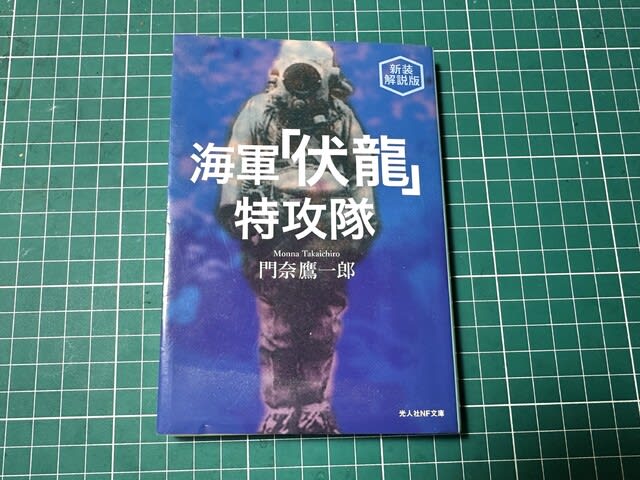












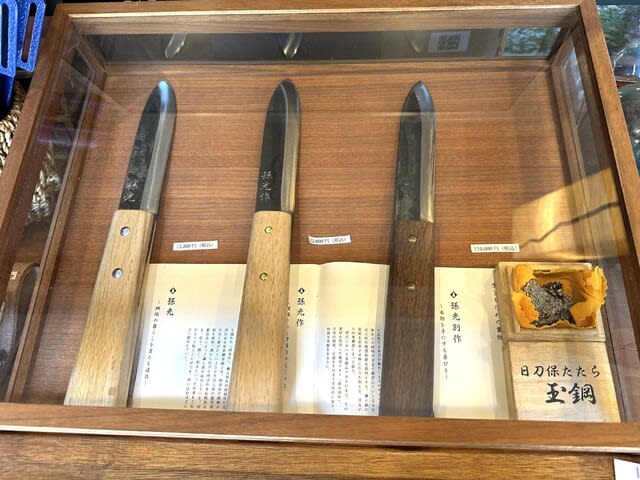

10代からボクシングキチガイと呼ばれたオヤジが亡くなってから、オヤジが遠征試合の帰りの電車でよくやっていたようにウイスキーのポケット瓶のキャップで献杯してからボクシング中継を視聴するようになった。今月は三回忌だ。
アマゾンプライムでボクシングの世界戦を二日続けて視聴したが、どれも見ごたえのある試合ばかりでオヤジが生きてたなら隣家にも聞こえる大声で「ジャブだっちゃ!ジャブ!ダボめ!なにやっとるんだやぁ!よしっボデイ!ヒット~!」と騒いでいただろう。
試合をみていて、70年代に「ボデイビルダーのような筋肉から強打」でKOの山を築いた」ロイヤル小林が、フェザー級王者の「ニカラグアの貴公子」アレクシス・アルゲリオに挑戦した試合を思い出した。
ロイヤル小林さん。確か自衛隊体育学校出身のハードパンチャーで、当時の連続ノックアウト記録保持者だったと思う・・・中学の頃の記憶(笑)
両雄がリングに上がった際、引退後に俳優になったほどの美男子で長身痩躯で足の長いアルゲリオと、扁平な顔立ちで上半身は立派でも足が短いロイヤル小林の体格差に唖然として、当時小学生のわたしでも闘う前から小林の敗北を悟った。

アレクシス・アルゲリオは端正なマスクと基本に忠実なスタイリッシュなボクシングとジェントルな試合マナーから、アマチュア選手のお手本になると言われた伝説のボクサー。わたしのアイドルボクサーだった。
「体格に劣る日本人ボクサーはスタミナとスピード、手数で圧倒するしかない」というのが当時のプロボクシング通念だった。
昨夜に的確な強打でKO勝利した中谷潤人や、一昨夜は実直なボクシングで判定勝利したユーリ阿久井もボクシングスタイルは違っても、アルゲリオの体型に似て長身瘦躯で足が長く、オヤジの言葉を借りると「ホンモン」のチャンピョンだった。
リーチ差17㎝もある体格差から勝てそうには見えない拳四郎など、強いチャンピョンをサンドバックのようにして強打を自在に見舞ってKO勝利して、体格差問題を一蹴!
主要4団体の「黄金のバンタム」王座を日本人選手が独占という、20世紀までは考えられなかった事態。その中で中谷は群を抜いている。
日本のプロボクシングは明らかに異次元の進化を遂げたようだ。
技術、スピード、パンチ力もそうだが、なによりメンタルが強くなっている。
好ましいのは態度も言動も謙虚なチャンピョンが多い傾向。これはアマチュアボクシングジムを運営していたオヤジが口うるさく指導していたが、ガッツポーズをする今どきの柔道選手より、よほど武道家にみえる。
#中谷潤人 #拳四郎 #ユーリ阿久井 #ボクシング #おやじ
