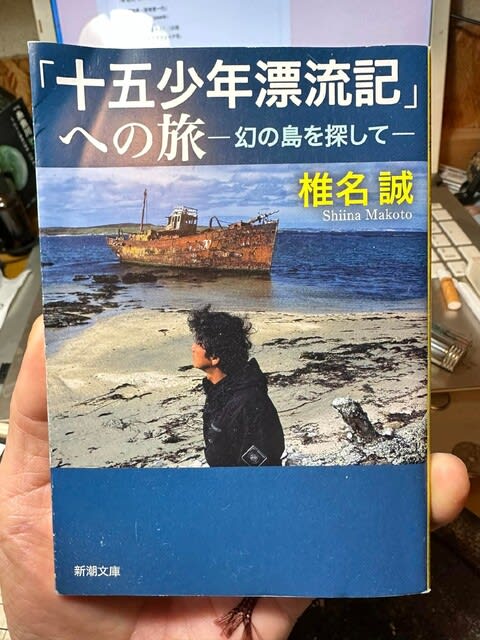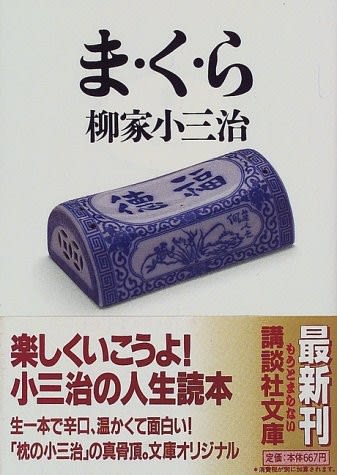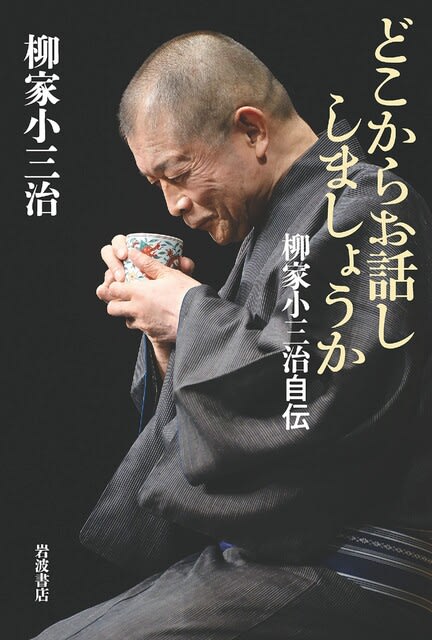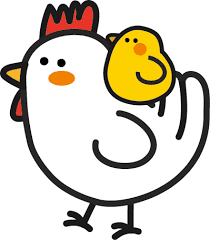トンデモ説の多くには、①つごうのいい情報だけを切り張りする②情報を検証しない③独善的に断定するといった特徴があるように思う。
ヒスイ・縄文・ヌナカワ姫と、わたしのライフワークに関したことが載っているからと京都在住の先輩から贈られた「アース・ダイバー神社編」がまさしくこの条件を備えていた。
ヒスイ加工遺跡として知られる寺地遺跡の配石遺構を、渚に作られた胎児のインスタレーションと断定し、「コシの勾玉工人たちは、渚につくられた胎児の形の配石の中で、まいにちまいにち胎児の形をした勾玉を磨っていた」と、渚と胎児にこだわって紹介しているが・・・。
寺地遺跡の配石遺構が胎児の形にみえるとすると、相当に想像力のある人だろう。こちらの図版は後述する「縄文のメドゥーサ」より
寺地遺跡は海岸から500mも内陸だから渚とはいえないし、遺跡と海岸の間には標高20mはある海岸段丘が障壁となっているので海の気配など感じようもない扇状地の遺跡だ。それに寒冷期の縄文晩期の遺跡だから、渚は現在より100~200mは後退していたハズ。
ちなみに発掘報告書では、配石遺構からは焼けた人骨やサメの椎骨の他にヒスイ原石も出土してはいるが、出土状況からモノ送りの祭祀場と考えられ、ヒスイ加工位置は多数の剥片と砥石の出土と、工作ピットらしき遺構をもつ竪穴住居内と報告されているはずだ。
「史跡寺地遺跡」の配石遺構の平面図だけを引用されている寺村光晴先生は困惑するだろう。
配石遺構がなんの形に見えるかは個人の自由だが、自説のように書いている胎児とする論説は、昨年亡くなった図像学で縄文文化の解明にとりくんでいた田中基さんの「縄文のメドゥーサ」の丸パクリではないか。田中さんの了承を得ているのだろうか?
わたしは観念論は好まない実証主義者なので、図像学で縄文文化を読み解く田中さんの研究には敬意を示しても興味はなく、頂き物の「縄文のメドゥーサ」は申し訳ないが寺地遺跡のところしか読んでいない。現代人が縄文の図像を読み解いても、当の縄文人はなんて思うだろう?という想いがあって、読み進めることができないのだ。
発掘に関係した考古者が胎児に酷似していると感じたと書いているが、主観的な感想をいわず物的証拠を客観視するのが考古学だから、報告書には無論そんなことは書かれてはいない。考古学者の誰が胎児と感じたのか明記して欲しいものだ。
また著者は「縄文時代のコシの糸魚川でつくられた胎児形の勾玉が、弥生時代のイズモで定形勾玉となった」とも断定しているが、コシとイズモという文脈はネットで拾った「古代のラブロマンス」の類いに、整合性を無視して考古学の知見を切り張りしたのだろう。
定形勾玉は弥生時代中期の北部九州が産地とする蓋然性が最も高く、そもそもイズモで勾玉つくりが本格化するのは古墳時代からだし、ヒスイ加工も確認されていない。
定形勾玉の特徴は、ちいさめで球形をした頭部が頸部にえぐりこみ、円形にちかい胴部断面が尾部にむかってスマートになる形状。こちらの勾玉は大分県の天岩戸神社に奉納するという依頼主の希望で丁子頭勾玉にしてあるし、予算の関係で白地に緑模様のヒスイを使ったが、本物の北部九州の定形勾玉は深緑のロウカンヒスイが多い。
イズモの勾玉は山陰系と分類される、ひと目で定形勾玉との違いが見分けがつくコの字形をした独特のものだし、素材も碧玉・瑪瑙・水晶だから、あまりにもデタラメすぎる。
山陰系勾玉の典型が、間延びしたコの字をした赤瑪瑙や青碧玉製。こちらは「松阪市立松浦武四郎記念館」の依頼でつくった玉類243点を繋げた「大首飾り」複製品の赤瑪瑙勾玉のひとつ。古墳時代前期なら写真のように胴部断面が円形に近く丁寧に作ってあるが、中期以降は需要量が増えたためか粗製となり平べったくなる。
著者は大衆受けするなら、事実関係はどうでもいいと考えているのだろうか?ファンタジー小説ならいいのだが、紀行文のような体裁で考古学資料を虫食い・切り張りしてつくった論説を、史実のように断定してしまうのは歴史の捏造といえないのか?
宗教史と文化人類学の大学教授の肩書をもつベストセラー作家であっても、これでは巷にあふれるスピリチュアルおじさんたちのトンデモ説と同じではないか。
著者にとっては神話の神々すらも商売のネタとも感じる。神なるものへの畏れや対象物への誠実さもなく、先人の研究成果に敬意を払わず使い捨てにして創作した妄想世界の夢物語が「中沢学」なるもの、とわたしは感じた。
追記
Facebookに投稿したら、90年代にバックパッカー旅を書いてベストセラーとなった「ゴー・ゴー・インド」の著者で、旅行作家の蔵前仁一さんが同感!とシェアしてくれた。蔵前さんも最初の「アースダイバー」がベストセラーになった時に誇大妄想の書としてブログで批判したと教えてくれたので、興味ある方は下記ブログ「旅行人編集者のーと」をご一読のほどを
https://kuramae-jinichi.hatenablog.com/entry/20071103/1203074813?fbclid=IwAR1WbmzCo-ftBPaWrosXymm_ozDBWUGVZlMKkAkd4DNn7qNAWAJ4cVHjFKg