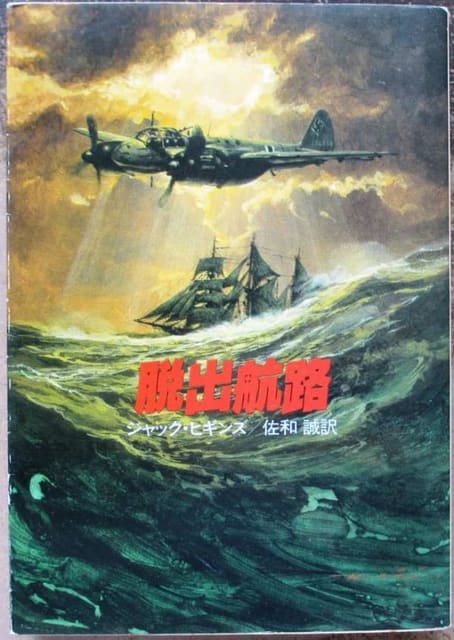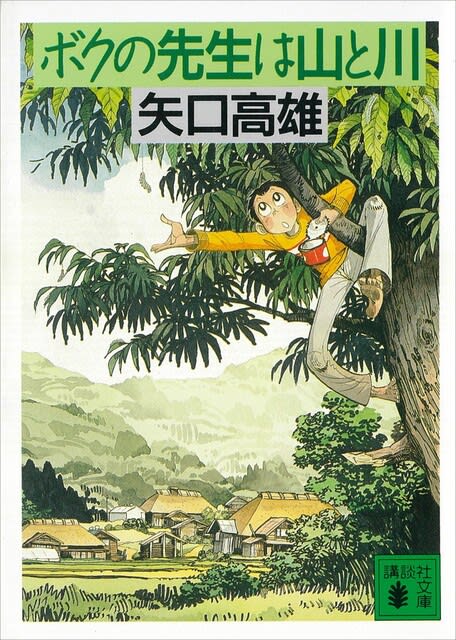坐骨神経痛に耐えつつ、吹雪の中の除雪をおえて家に入ると、わたしの苦労もしらず、どこへ行ってたニャ?と視線を送るネコ。

人間社会に我関せずの立場を守り、好きな時に寝て食うネコという生き物のフシギ、謎に迫りたいのである。
そこで「ヒトのネコ化にみる同化現象とその危険性」について、以下で若干の考察を試みたい。
今どきの家は暖かいからか、拙宅のネコはコタツで丸くならずストーブの前を好む。しかし、わたしはコタツで寝ころんで読書をしつつ、いつの間にか眠りこんでしまう行為を冬の悦楽とする者である。
これは幼少のみぎりに歌わされた「ネコはコタツで丸くなる」の擦りこみによる、面倒くさいことはせず、好き勝手に生きるネコへの憧憬があるのではないか?と睨んでいる。すなわちヒトのネコ化である。
いくらイヌが好きでも、雪が積もった庭を喜んで走りまわる成人はおりますまい。つまり、ヒトはイヌを擬人化することはあっても、ヒトそのものはイヌ化しないのだ。
言語においてもネコ化は顕著で、あニャがとニャ!こんにちニャ!と話すネコ好きは枚挙に枚挙にいとまがないが、いただきますワン!という犬好きには会ったことはないので、ヒトはイヌ化しない考察の蓋然性は担保されるのである。
いや、小学生の時に放映された学校ドラマ「熱中時代」で、船越英二と草笛光子が演じる犬好きの校長夫妻が、ワン?ワンッ!と犬語で意思疎通をする場面があったが、実際に犬語を話すヒトがいるのかは不明。
わたしなどは驚いた時にニャッ!と思わず声をあげるし、ショッキングなことがあるとニャニャニャニャ~!とベートーヴェンの「運命」をネコ語で歌ってしまう。ネコ化が「病膏肓に入る」に達しているのである。
ネコには周囲を感化させるフェロモン、あるいはウイルスがある疑いが示唆されるが、抗ネコ化ワクチンの開発が待たれる。
あまりネコ化し過ぎると危険だ、と思う次第ですニャ(=^・^=)