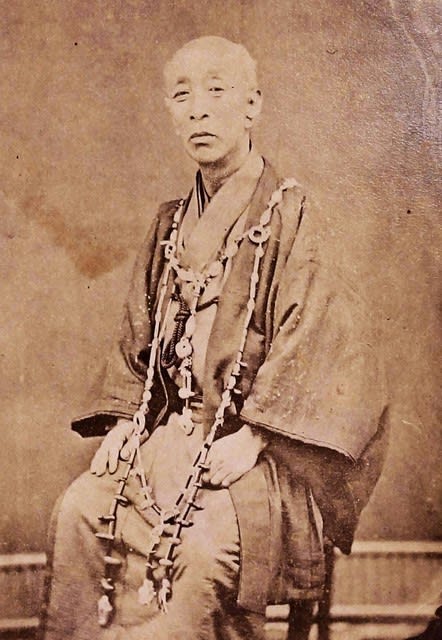急遽上京して「大首飾り」の実物を観察させて貰えることになり、「大首飾り」に含まれる6点の金環と比較するための試作品2点を作った。
金環とはC字形をした古墳時代特有の装飾品であり、耳飾りであったと推測されている。

山梨県立考古博物館に展示されている金環
ただしその種類は多種多様で、地金は金・銀・銅・鉄・木製と様々で、多くは表面に金箔や銀箔が施されている。
試作品は直径5㎜の銅製丸棒を焼きなまし、最初は手曲げしてみたが綺麗なC字形になってくれず、治具を作ってなんとか寸法通りにはなってくれたが自己採点は60点で、まだ改善する余地はある。

2点の試作品は、平面形状と寸法は合格だが、縦方向に歪みが出て平にはなっていない。

治具1号・・・焼きなまししてから鉄棒に巻き付ける方式。奥の当て木をテコにしてクイクイと巻き取っていく・・・ハズだったが固くてうまく行かなかった。

この方式はアクセサリー用のC環を作る方法の応用だが、太いので捩れが戻ってくれないのが欠点。
最大の金環は直径8㎜もあるので先が思いやられるが、古墳時代の職人も同じ方法だったのか?
この件については考古学者さんから膨大な論文を送って頂いたのだが、製法も多種多様だとされているようだ。
千七百年前の職人の知恵の深さに驚愕し、リスペクトは深まるばかり。
合格点が取れたら、メッキ屋さんでアンティーク調に金と銀を被せてもらうことになっている。