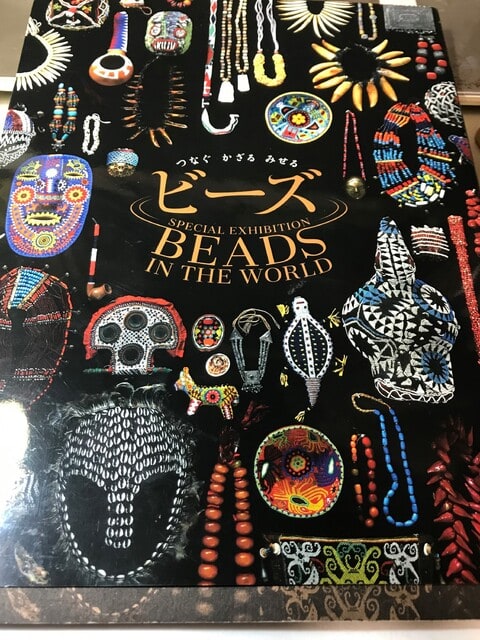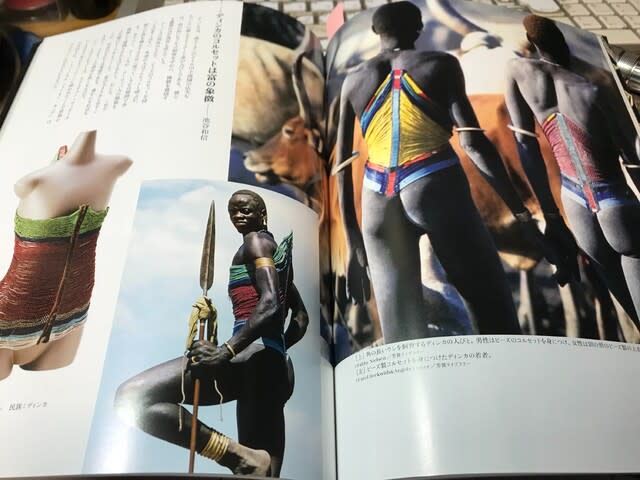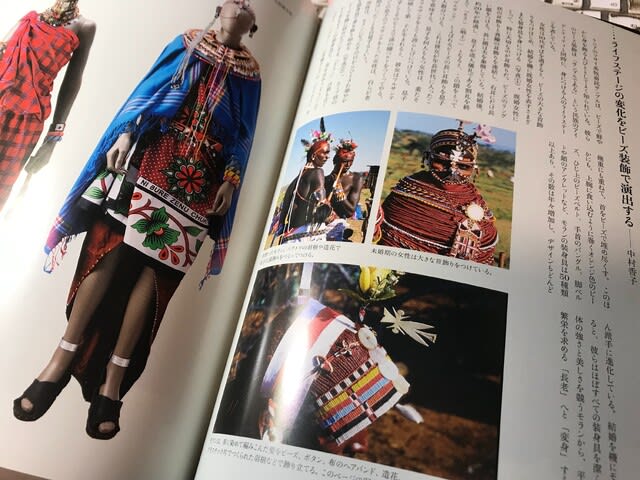6年前は大晦日まで、開けた正月は3日から、糸魚川駅北大火の被災者支援ボランティアをしていた。

焼け跡から貴重品や思い出の品を掘り出すボランティアである。

重機の解体工事が始まるまでに、人力で瓦礫をどかし、証券、仏具、貴重品などを探し出す。

黒焦げの結婚指輪に「よかったぁ!」と涙ぐむ、被災した老婦人。

それが床の間に飾られたヒスイ原石であったりしても、被災者にとっては家族の記憶を宿す記念の品。

亡くなったご主人が若い頃に拾ったヒスイは変色しているので、むろん市場価値はないが・・・。
モノの価値は市場価値にだけあるのではない。
ヒスイ拾いのガイドで「これは幾らくらいの価値がありますか?」と聞いてくる人に、大火で黒焦げになった結婚指輪やヒスイの物語りをする、わたしは面倒くさいガイドだ。
ヒスイが拾えなくても、一喜一憂しながらヒスイ拾いに興じたこと自体が旅の思い出。
現在のヒスイ人気に「ヒスイ海岸で一攫千金お宝ゲット!」といったノリを感じているが、ヒスイがかわいそうで情けなくなる。
この場合のヒスイとは金の価値で評価される希少鉱物としてではなく、万葉歌人が「拾いて得し玉かも」と詠み、縄文から古墳時代まで装身具が作られていた「ヒトとヒスイの物語」のことだ。
上杉謙信が甲斐におくった「義の塩」は、この海岸で作られた!この辺りが私の先祖の塩田だった!「けんか祭り」の朝に禊をする海!蛇紋岩は石斧の素材!と、ヒスイを抜きにしてもヒスイ海岸の物語はたくさんある。