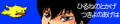Takの嘔吐蹴りはおかげさまで軽くてすみました。
金曜の明け方から始まったTakのきつい嘔吐も、1日絶食した甲斐あって、その後は順調に回復しました。
翌日には、結局、香川大学構内でやってる「科学体験フェスティバル」とやらのイベントも、どうしても、ちょっとでもいきたいというので、連れていきました。
ちょっとのつもりが、、、、正午から4時まで、たっぷり4時間、実験、工作、ハマりまくって、堪能して、大満足だったようです。
親の出る幕はなく、そのへんで立って、または、空いている椅子をみつけて座ってるだけなので、入り口で貰った「ガイドブック」をどれどれ…と、、、
「かがわけん科学体験フェスティバル」
主として香川県内の児童生徒の科学や技術に対する関心を高めあるとともに、様々の自然体験をとおして、人間としての成長をはかることを目的に、平成5年度から、毎年、県下の各地を巡回して開催してきた科学体験行事である。…
なるほどぉ~~
でっ、実態はというと、ひろ~い会場に、30以上のブースがあって、それぞれ、中学、高校の理科の先生や、科学部系の部員の人たち、技術系の企業などが、主に小学生向けの楽しい実験や、工作をやるコーナーを出展してるのです。
最初、ブースにいるこの中高生とおぼしきヤツらはいったいナンなんだ!?と思ったけど、そーゆうことだったのね。
もちろん、大人もいるんだけど、子供たちは、ここに来て、それぞれ興味を持ったブースに行って、にーちゃん達に教えてもらいながら、ブーメランや、ロケットをつくったり、3D体験、雲をつくる実験、などなど、それぞれのチームが子供達が楽しむことができる企画を考えてやってる、なかなかすてきなイベントじゃないの。
ちなみに、Takがやったのは
ブーメラン
ブーメラン型飛行機(飛ばしたら戻ってくるやつ)
傘を入れるビニール袋と色画用紙でつくるロケット
赤と青のセロファンでめがねをつくって3D体験
声の振動で、紙コップの上のモールを動かす工作
指に絡み付いて抜けなくなるヘビの工作
磁石と紙コップでつくるスピーカー
ストローとタコ糸でつくるロボットアーム
雲をつくる実験
ペットボトでつくる水ロケット
特に、「作用、反作用の法則」で勢いよく飛ぶ水ロケットは、自分で作ったロケットを、実際に発射台に設置して、空高く、勢いよく飛ばすので、すごいインパクトでした。見てる私も感動しました。
スイッチを手に発射のカウントダウン。
でも、私としては、いちばんいいなと思ったのは、中高生のにーちゃん、ねーちゃんたちに、目新しい実験や工作を教えてもらう…っていうことだな。見た目の派手さはなくとも、すごく中身の濃いイベントでした。
Takは、翌日、昨年のお誕生日に買ってもらったプラモデルを、1体、自力で完成させました。これには、ホントにびっくりしたよ。さらに翌月曜日には、図書館で、「ロボット大図鑑」という本を借りてきました。

親バカだけど、こういうのって、ほんとに嬉しいもんです。子供の興味がどんどん膨らんでいくのを見るのは、ほほえましく、頼もしいです。
金曜の明け方から始まったTakのきつい嘔吐も、1日絶食した甲斐あって、その後は順調に回復しました。
翌日には、結局、香川大学構内でやってる「科学体験フェスティバル」とやらのイベントも、どうしても、ちょっとでもいきたいというので、連れていきました。
ちょっとのつもりが、、、、正午から4時まで、たっぷり4時間、実験、工作、ハマりまくって、堪能して、大満足だったようです。
親の出る幕はなく、そのへんで立って、または、空いている椅子をみつけて座ってるだけなので、入り口で貰った「ガイドブック」をどれどれ…と、、、
「かがわけん科学体験フェスティバル」
主として香川県内の児童生徒の科学や技術に対する関心を高めあるとともに、様々の自然体験をとおして、人間としての成長をはかることを目的に、平成5年度から、毎年、県下の各地を巡回して開催してきた科学体験行事である。…
なるほどぉ~~
でっ、実態はというと、ひろ~い会場に、30以上のブースがあって、それぞれ、中学、高校の理科の先生や、科学部系の部員の人たち、技術系の企業などが、主に小学生向けの楽しい実験や、工作をやるコーナーを出展してるのです。
最初、ブースにいるこの中高生とおぼしきヤツらはいったいナンなんだ!?と思ったけど、そーゆうことだったのね。
もちろん、大人もいるんだけど、子供たちは、ここに来て、それぞれ興味を持ったブースに行って、にーちゃん達に教えてもらいながら、ブーメランや、ロケットをつくったり、3D体験、雲をつくる実験、などなど、それぞれのチームが子供達が楽しむことができる企画を考えてやってる、なかなかすてきなイベントじゃないの。
ちなみに、Takがやったのは
ブーメラン
ブーメラン型飛行機(飛ばしたら戻ってくるやつ)
傘を入れるビニール袋と色画用紙でつくるロケット
赤と青のセロファンでめがねをつくって3D体験
声の振動で、紙コップの上のモールを動かす工作
指に絡み付いて抜けなくなるヘビの工作
磁石と紙コップでつくるスピーカー
ストローとタコ糸でつくるロボットアーム
雲をつくる実験
ペットボトでつくる水ロケット
特に、「作用、反作用の法則」で勢いよく飛ぶ水ロケットは、自分で作ったロケットを、実際に発射台に設置して、空高く、勢いよく飛ばすので、すごいインパクトでした。見てる私も感動しました。
スイッチを手に発射のカウントダウン。

でも、私としては、いちばんいいなと思ったのは、中高生のにーちゃん、ねーちゃんたちに、目新しい実験や工作を教えてもらう…っていうことだな。見た目の派手さはなくとも、すごく中身の濃いイベントでした。
Takは、翌日、昨年のお誕生日に買ってもらったプラモデルを、1体、自力で完成させました。これには、ホントにびっくりしたよ。さらに翌月曜日には、図書館で、「ロボット大図鑑」という本を借りてきました。

親バカだけど、こういうのって、ほんとに嬉しいもんです。子供の興味がどんどん膨らんでいくのを見るのは、ほほえましく、頼もしいです。