(あなたは何冊読みましたか)
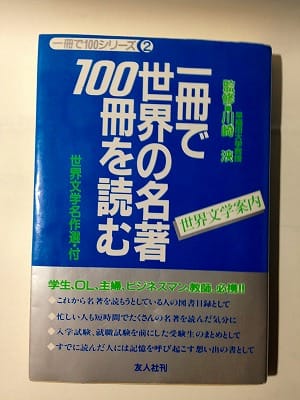 世界の名著
世界の名著
(友人社刊)
1988年7月に友人社から出版されたこの本は、世界文学の名著100冊を選び出し、それぞれ見開き2ページで作品概要を解説する実にありがたい企画であった。
ほぼ30年前の本を持ち出して、今更なにをしようというのかと疑問に思うかもしれないが、自分がこれまでに世界の名著を何冊読んできたのか検証するのも一興かと思ったからだ。
結論をいうと、僕の場合は約30作品しか読んでおらず、いかに情けない状況なのかを思い知らされる結果となった。
以下、作品+著者名を列記するので、みなさまもチェックしてみたらどうだろう。
いろいろな考え方があろうが、僕としては先人が残した優れた文学作品には、なるべく幅広く触れたほうがいいのではないかと思っている。
<作品名> <著者名> <国名> <年代>
1 イーリアス ホメロス ギリシャ 紀元前8世紀
2 オデュッセイア ホメロス ギリシャ 紀元前8世紀
3 アガメムノン アイスキュロス ギリシャ 紀元前458年
4 オイディプス王 ソフォクレス ギリシャ 紀元前420年頃
5 エレクトラ エウリピデス ギリシャ 紀元前420~410年代
6 ロランの歌 作者・未詳 中世フランス 11世紀末
7 イーゴリ遠征物語 作者・未詳 ロシア中世 1187年
8 ニューベルンゲンの歌 作者・不明 ゲルマン 1204年前後
9 神曲 ダンテ イタリア 14世紀
10 カンタベリー物語 チョーサー イギリス 1400年
11 ロミオとジュリエット シェイクスピア イギリス 1595年
12 ハムレット シェイクスピア イギリス 1603年
13 リア王 シェイクスピア イギリス 1605年
14 ドン・キホーテ セルバンテス スペイン 1605~1615年
15 マクベス シェイクスピア イギリス 1606年
16 タルチュフ モリエール フランス 1664年
17 フェードル ラシーヌ フランス 1677年
18 ガリヴァー旅行記 スウィフト イギリス 1726年
19 マノン・レスコー プレヴォー フランス 1731年
20 若きヴェルテルの悩み ゲーテ ドイツ 1774年
21 危険な関係 ラクロ フランス 1782年
22 ヴィルヘルム・テル シラー ドイツ 1804年
23 ファウスト ゲーテ ドイツ (第一部) 1808年 (第二部) 1832年
24 高慢と偏見 オースティン イギリス 1813年
25 アドルフ コンスタン フランス 1816年
26 赤と黒 スタンダール フランス 1830年
27 エヴァゲーニー・オネーギン プーシキン ロシア 1830年
28 ゴリオ爺さん バルザック フランス 1834~1835年
29 検察官 ゴーゴリ ロシア 1836年
30 アッシャー家の崩壊 ポー アメリカ 1839年
31 現代の英雄 レールモントフ ロシア 1840年
32 死せる魂 ゴーゴリ ロシア 1842年
33 嵐が丘 エミリ・ブロンテ イギリス 1847年
34 白鯨 メルヴィル アメリカ 1851年
35 オーレリア ネルヴァル フランス 1855年
36 ボヴァリー夫人 フローベール フランス 1857年
37 大いなる遺産 ディケンズ イギリス 1861年
38 父と子 ツルゲーネフ ロシア 1862年
39 レ・ミゼラブル ヴィクトル・ユゴー フランス 1862年
40 罪と罰 ドストエフスキー ロシア 1866年
41 戦争と平和 トルストイ ロシア 1869年
42 悪霊 ドストエフスキー ロシア 1872年
43 魅せられた旅人 レスコーフ ロシア 1873年
44 アンナ・カレーニナ トルストイ ロシア 1877年
45 居酒屋 ゾラ フランス 1877年
46 カラマーゾフの兄弟 ドストエフスキー ロシア 1880年
47 女の一生 モーパッサン フランス 1883年
48 ツァラトゥストラはこう語った ニーチェ ドイツ 1883~1885年
49 テス ハーディ イギリス 1891年
50 ドリアン・グレイの肖像 ワイルド イギリス 1891年
51 クォ ヴァディス ヘンリク・シェンキェヴィチ ポーランド 1896年
52 三人姉妹 チェーホフ ロシア 1900年
53 どん底 ゴーリキー ロシア 1902年
54 桜の園 チェーホフ ロシア 1904年
55 ジャン・クリストフ ロマン・ロラン フランス 1904~1912年
56 狭き門 アンドレ・ジット フランス 1909年
57 マルテの手記 リルケ ドイツ 1910年
58 息子と恋人 D・H・ロレンス イギリス 1913年
59 モーヌの大将 アラン・フルニエ フランス 1913年
60 失われた時を求めて プルースト フランス 1913~1927年
61 変身 カフカ チェコ 1925年
62 デーミアン ヘルマン・ヘッセ ドイツ 1919年
63 阿Q正伝 魯迅 中国 1921年
64 ユリシーズ ジョイス イギリス 1922年
65 チボー家の人々 マルタン・デュ・ガール フランス 1922~40年
66 肉体の悪魔 ラディゲ フランス 1923年
67 魔の山 トーマス・マン ドイツ 1924年
68 われら ザミャーチン ロシア 1924年
69 テレーズ・デスケールー モーリアック フランス 1927年
70 三文オペラ ブレヒト ドイツ 1928年
71 恐るべき子供たち コクトー フランス 1929年
72 響きと怒り フォークナー アメリカ 1929年
73 武器よさらば ヘミングウェイ アメリカ 1929年
74 無関心な人びと モラヴィア イタリア 1929年
75 人間の条件 マルロー フランス 1933年
76 嘔吐 サルトル フランス 1938年
77 怒りの葡萄 スタインベック アメリカ 1939年
78 異邦人 カミュ フランス 1942年
79 星の王子さま サン・テグジュペリ フランス 1943年
80 伝奇集 ボルヘス アルゼンチン 1944年
81 四世同堂 老舎 中国 1945~1949年
82 灰とダイヤモンド アンジェイェフスキ ポーランド 1948年
83 ライ麦畑でつかまえて サリンジャー アメリカ 1951年
84 まっぷたつの子爵 カルヴィーノ イタリア 1952年
85 失われた足跡 カルベンティエール キューバ 1953年
86 悲しみよ今日は サガン フランス 1954年
87 蝿の王 ゴールディング イギリス 1954年
88 ロリータ ナボコフ ロシア 1955年
89 ドクトル・ジヴァゴ パステルナーク ロシア 1957年
90 弟 ノサック ドイツ 1958年
91 ブリキの太鼓 ギュンター・グラス ドイツ 1959年
92 ソラリスの陽のもとに スタニスワフ・レム ポーランド 1961年
93 もう一つの国 ボールドウィン アメリカ 1962年
94 石蹴り遊び コルターサル アルゼンチン 1963年
95 緑の家 バルガス・リョサ ペルー 1966年
96 脱皮 フェンテス メキシコ 1967年
97 百年の孤独 ガルシア・マルケス コロンビア 1967年
98 ガン病棟 ソルジェニツィン ロシア 1968年
99 生きよ、そして記憶せよ ラスプーチン ロシア 1975年
100 愛人 デュラス フランス 1984年
以上、41人の執筆者と1人の監修者の手になる労作がこのシリーズで、内容まで紹介できないのは残念である。
1985年以降にブッカー賞とかノーベル文学賞を受賞した作品も、いずれ名著の仲間入りをするものと思われるが、それとてなかなか読んでいないというのが実感だ。
とりあえず、自分が何作読んでいるかチェックの参考にしていただければ幸いである。
正直、数項目を再録するだけでも半日以上かかった。やはり、学者や編集者でもない限り作品内容まで読み込むのは大変であることがわかった。
だから、この企画は当時評判を呼んだのではないか。
① これから名著を読もうとしている人の図書目録として・・・・。
② 忙しい人も短時間でたくさんの名著を読んだ気分に・・・・。
③ 入学試験、就職試験を前にした受験生のまとめとして・・・・。
④ すでに読んだ人には記憶を呼び起こす想い出の書として・・・・。
味も素っ気もない図書目録だが、いろんな使い方があるようだから、僕の労力は無駄ではなかったと思いたい。
(おわり)
a href="http://novel.blogmura.com/novel_short/"
<短編小説ブログ・ランキング用バナー>が復活しました。




























なんだか嬉しいな。
あと数冊は上乗せしたいと思っています。
おやすみなさい。
本は手元にあって読んだつもりになっていたものも、実は最後まできちんと読み通していないものがほとんどです。
しかし中身は知っているつもりになっていて・・・たぶんダイジェストされた梗概を何かで読んでわかったつもりになっていたに違いありません。
名作というものは書かれたその時代を超えて普遍性を持つのでしょうが、それはわかっているつもりでいても表現の感性がしっくりこない感じがあったりして、特に長いものは途中挫折してしまっているような気がします。
お叱りを承知の上でいうなら、文章が説明的でまどろっこしいことがその原因ではと。
それが証拠に、例えば樋口一葉の作品や中島敦の山月記など、言葉自体は新しくないけれど極限まで凝縮されていてリズム感と一緒にストレートに体に入ってきます。ごちゃごちゃ説明しなくてもすべてが体感できる。
読むたびに新しいイメージが喚起されて新鮮。
映像の世界でもいまや物語の説明シーンや段取り芝居は不要になっています。
省略しても見る側が無意識にイメージで埋めていける感性を持っているのでくどい説明はいらないのでしょう。
同じようなことが文章の世界でも起きているのではないでしょうか?
ただ名作というものが抱えている人類の根っこにつながるものは、価値が重く、ドラマや舞台やゲームなど別な表現舞台に移して新しい人類に受け継がれていきます。
名作の継承はそれで十分だと思うのですがこんな考え方はおかしいでしょうか・・・?
ぼくが読んだと思っている作品の中にも、そうしたものがいくつもある気がします。
でも、それも読んだうちに数えています。
8割がた目を通せば、時代の雰囲気や作品のテーマが掴めるので、ヨシとすることにしませんか。
一方、文学の名作と言われるものに含まれる根源的な価値観を、映像や舞台やゲームなどに移し替える試みは、必然的であり受け容れられるものだと思います。
ただ、研究者や翻訳者が提供してくれる古典文学の味わいにも、できるだけ近づいていきたい思いもあります。
名作への接し方は、人さまざまでいいのではないでしょうか。
それでも1800年代以降の作品には、できるだけ挑戦していきたいと考えています。
例えば、僕は高校時代に読んだ「赤と黒」、「ゴリオ爺さん」、「嵐が丘」、「ボヴァリー夫人」、「罪と罰」、「悪霊」、「白痴」、「カラマーゾフの兄弟」など、筋はうろ覚えでも影響を受けた実感があります。
いずれにせよ、知恵熱おやじさんの卓見には感服しております。
なかなかここまで踏み込んで考えることをしませんでしたので、たいへん刺激を受けました。
ありがとうございました。