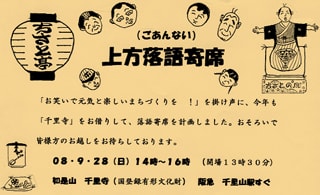この『J-POPメタル斬り』では日本大好きな有名ギタリストのマーティー・フリードマンが、日本のポピュラーソング(演歌や歌謡曲にも明るい)の魅力や特徴を、そのインターナショナル(洋楽的)な素養から面白く解説しています。彼は昨年の紅白歌合戦のオープニングでギター演奏を披露したり、以前に世良公則が弾き語りをする番組で素晴らしいセッションをしていました。
今回のテーマは曲の構成について、いわゆる“Dメロ”が鍵を握っているという興味深い指摘です。このところ再浮上しつつある安室奈美恵の新曲『Do Me More』や、ミスチルの北京オリンピック応援歌(NHK)『Gift』の曲の豪華さの一つには、このDメロの冒険的な成功に因るところが大きいと言われています。実は僕も現在ある外国のギターソロに詞を付けているのですが(明日完成アップの予定)、この原曲もそう言えばDメロ展開(今回僕は間奏として使う積もりです)の後で印象的なサビを繰り返して終わる構成になっており、確かにそのDメロのお陰で美しいメロディーや最後のサビが立体的に引き立っているように思います。
後半ではそのような構成の対極にあるシンプルなポップソングのお手本として、青山テルマの新曲『何度も』を採り上げています。AメロとBメロの橋を渡ってまたサビ(Cメロ)に戻っていく教科書的な展開を完璧なポップソングだと評価しています。僕も懐かしくて衒いのない良い曲だなと思っていました。
 | 何度も 青山テルマ,Yoshiyasu Ichikawa,Miwa Yoshida,etc. このアイテムの詳細を見る |
 | GIFT Mr.Children,桜井和寿,小林武史 トイズファクトリー このアイテムの詳細を見る |