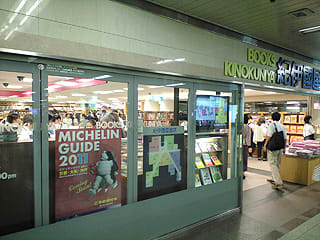千里山でも10月30日に街の誕生90周年を記念して、秋の散策会「千里山ウォーク」がまちづくり協議会の主催で企画されていますが、関西一円の大きな規模のものとして「関西あそ歩(ASOBO)」のポスターが駅ホーム掲示板に張られています。
「関西あそ歩」は関西の私鉄3社(南海・阪急・阪神)のコラボ企画で、それぞれの沿線にある名所・旧跡を訪ね歩くコースを提案し、地元のことを良く知り遊んで貰おうという主旨です。
たまたま昨日、知人のKさんのマンションに覗うことになり、話の中でこの「関西あそ歩」のパンフレットを見せて貰ったばかりです。リタイア後の第二の人生をカラオケ教室や社交ダンスなど、日頃から大いに楽しまれているKさんですが、知的好奇心と健康にも良いということで「関西あそ歩」に参加を申し込んだということでした。
Kさんの説明では、全体では120もの面白いコースが用意されていて、15人定員で一人の案内人が付き添い、参加費用は1,000円(もちろん交通費・昼食費などは別途)と格安です。Kさんは来月から再開したカラオケ教室と重なり行けない日以外は、多くの「関西あそ歩」コースに参加すると意気込んでおられました。
※ 秋の散策会「千里山ウォーク」は内容が詳しく決まり次第、自治会の掲示板などでお知らせしますので、お気軽にご参加よろしくお願い致します。