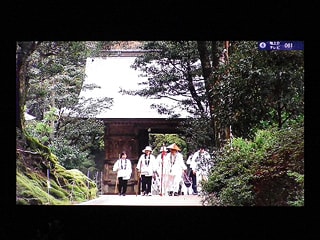一昨日ガラスコップを軽く手のひらで洗っていた時に、小さなヒビでも入っていたのか突然コップの縁が割れ、右人差し指の関節辺りを1/3ほどの深さにザックリと切りました。記憶に無いくらいに久しぶりの怪我だったので、少しパニックになりながら救急箱を探しましたが、こんな時には普段危機管理が出来ていないと全く困ってしまいます。
流水で傷口を洗った後にテイッシュを当て、暫く指の根元を握って止血しました。少し落ち着いたところで色々引き出しを探ると、いつか試供品で貰った絆創膏が出てきましたので、早速傷口に巻き付け処置をし裏の説明書を詳しく読んでみました。
それは森下仁丹の絆創膏(メディケア) の「防水ネットバン」という商品で、水やバイ菌の侵入を防ぐだけでなく、通気性(衛生的)や傷口に食い込まない(交換がしやすい)新タイプのようです。また傷口周辺の接着部も薄くて伸縮性があり、日常の作業(パソコン操作やギター演奏も)などでも剥がれにくくなっています。
翌朝、洗顔の後で恐る恐る絆創膏を剥がしてみましたが、出血も腫れもなく傷口も綺麗に塞がれていました。この分ですと水仕事やお風呂も支障なく過ごせそうで有り難く思いました。
何時どこで災難に遭うか分からないと改めて思うと同時に、有り触れた日常商品の繊細な進歩と企業努力に感謝しなければと思いました。試供品のため残り1枚となりましたので、早速近くのスギ薬局ででも森下仁丹の絆創膏(メディケア)を補給したいと思います。