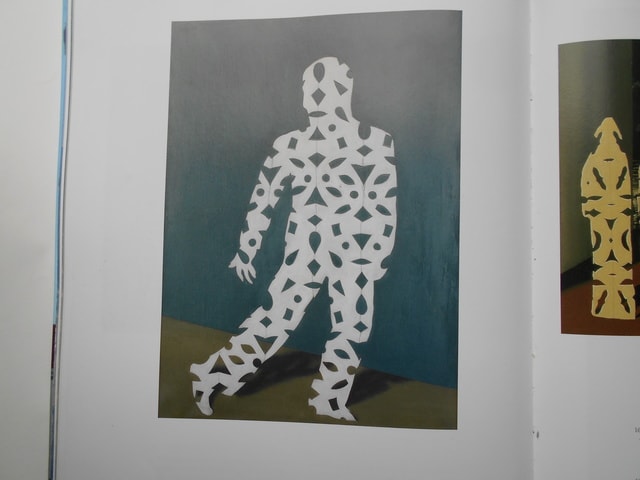大枕つくれば冬の露がつく
大枕はタイ・チンと読んで、頽、沈。
つくれば冬の(作冬)はサ・トウと読んで、砂、塔。
露がつく(露付)はロ・フと読んで、露、風。
☆頽(崩れて)沈む砂の塔、露(さらけ出した)のは風である。
大枕はタイ・チンと読んで、他意、陳。
つくれば冬の(作冬)はサ・トウと読んで、査、到。
露がつく(露付)はロ・フと読んで、露、譜。
☆他意を陳(述べている)。
査(調べて)到(いたりつく)と、露(あらわれる)譜(物事を系統的に書き記したもの)。
大枕はタイ・チンと読んで、滞、賃。
つくれば冬の(作冬)はサ・トウと読んで、嗟、党。
露がつく(露付)はロ・フと読んで、漏、腐。
☆滞(とどこおる)賃(報酬としてもらう金銭)を嗟(嘆く)党(仲間)の漏(内情)に腐(心を痛めている)。