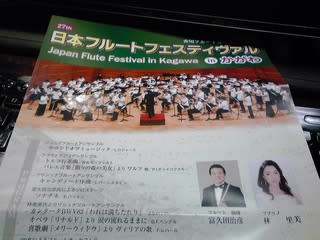電車に乗ってゆきました。向こうに妙なものがいました。
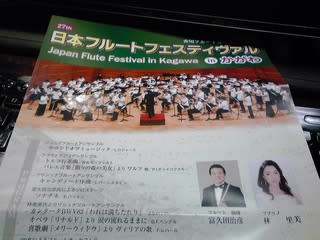
・「サウンド・オブ・ミュージック」より……ジュニアフルートアンサンブルの演奏。思ったんだが、我々素人の耳は、ビブラートかけた音より、ノンビブラートの音に美を感じるようになってきているのではなかろうか……。
・「眠りの森の美女」と「コッペリア」のワルツ、「トルコ行進曲」……フラウトマジコアンサンブルの演奏。そういえば、昔、ワルツの演奏をした後行進曲を演奏すると、行進曲も三拍子っぽくなるという噂を聞いた。
・「キャンディード序曲」……クリシュナフルートアンサンブルの演奏。キャンディードってひどい話ですよね……。
・E・バートン「ソナチネ」……富久田治彦さんのソロ。ピアノが凝ってるなあ……と思ったら、この作曲者ピアニストか……。
・カンタータ「我はみちたれり」、リナルドより「涙の流れるままに」、メリー・ウィドゥより「ヴィリアの歌」……林里美さんとクリシュナフルートアンサンブルの演奏。救い主たる赤ん坊に出会ったからといって余はもう満足じゃとは何事か、とわたくしは思うね。本当は、赤ん坊を前にしてさえ「泣かせてくれー」と思っていたにちがいない。対して、一般的には恋の歌にはそんな逡巡はないように見える。が、森の精に一目惚れで小屋に誘惑されてキスしたとか、よくわからんが「メリー・ウィドウ」はものすごく病んでいる作品のような気がする。
・ドボルザーク「弦楽セレナーデ」……90名によるフルートアンサンブル。やっぱりドボルザークは若い頃からすごいな。メロディが変わると会場の空気が変わる。各パートが人の動作みたいに自然にでてくる。すごいなあ……
・エルガー「威風堂々第一番」……同上の演奏。この曲は、イギリス人がやるよりイタリア人とかがやった方がいいような気がする。という偏見丸出しのわたくしであった。
感想……
フルート男子はモテそうな気がする。