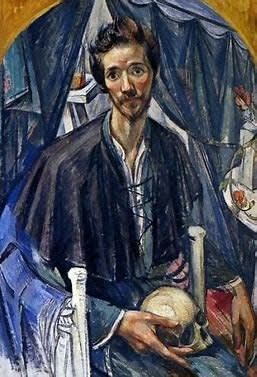花の冠をつけた ドラ・マール

緑のマニキュアをつけたドラ・マール
これいいな〜。

踊るシレノス 1933年
真正面で歪みなく写真撮るの難しくて。

ピカソのブロンズ作品は鶴。

青の風景 1917年

小さな城 黄・赤・茶色 1922年
こちらはジャコメッティ。
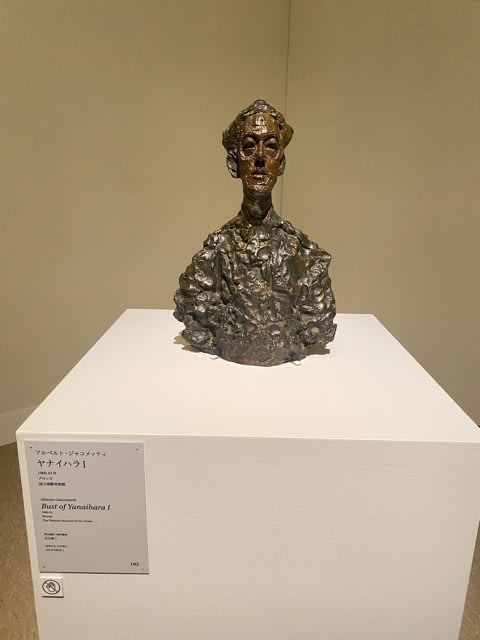
2時間半、企画展を鑑賞して、ミュージアム・レストランへ。

大はずれです。

フィンランドの画家、カッレラの











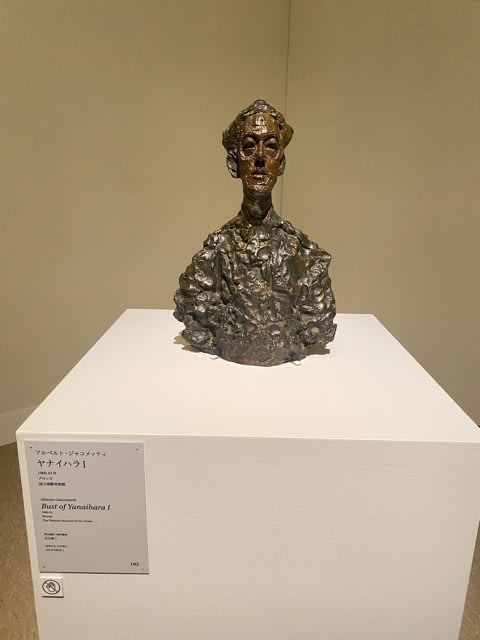







































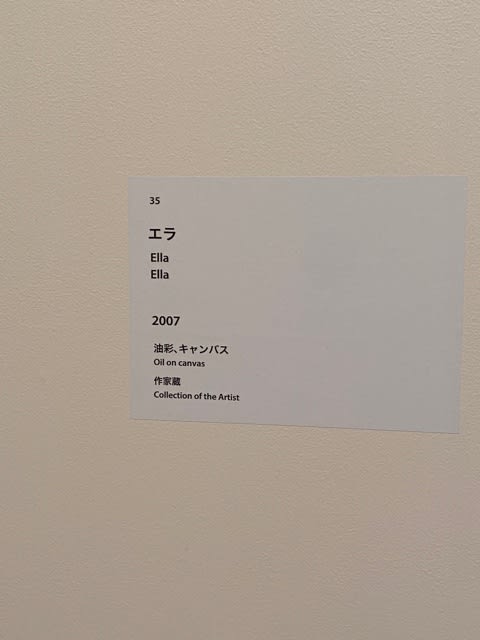


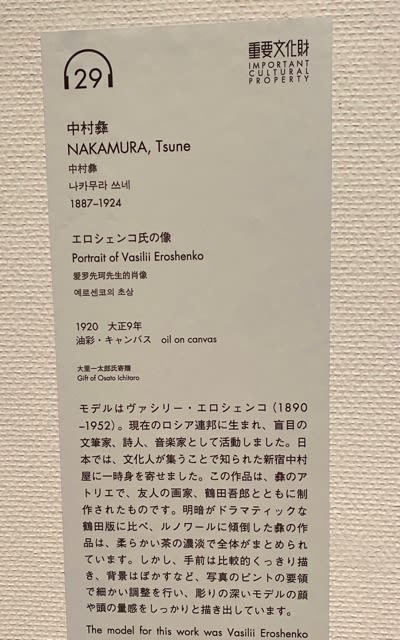


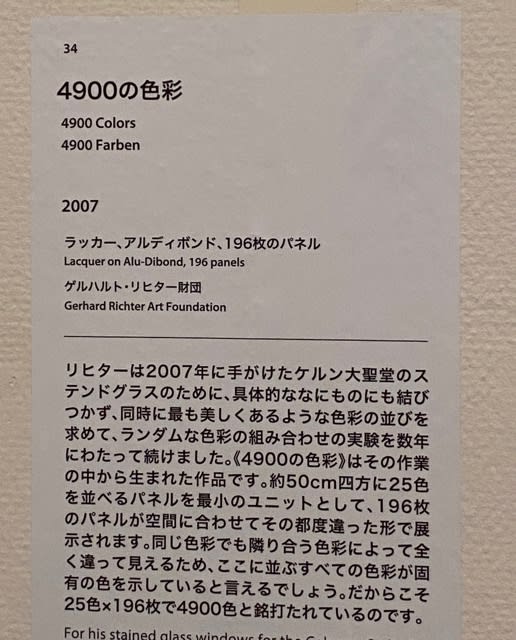
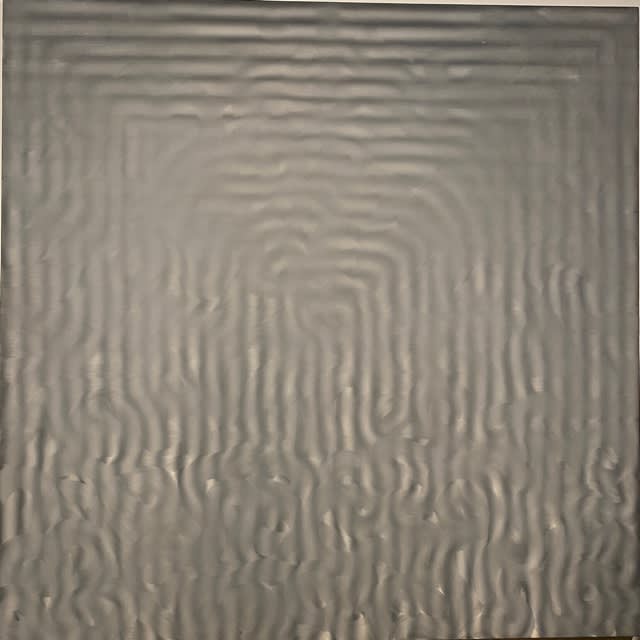
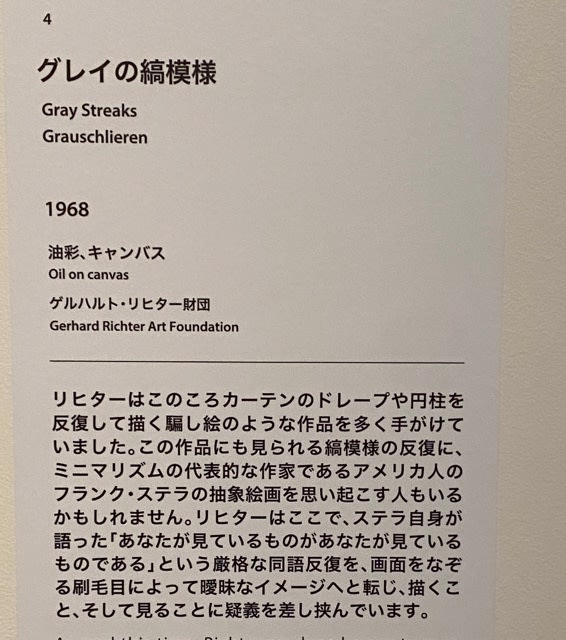








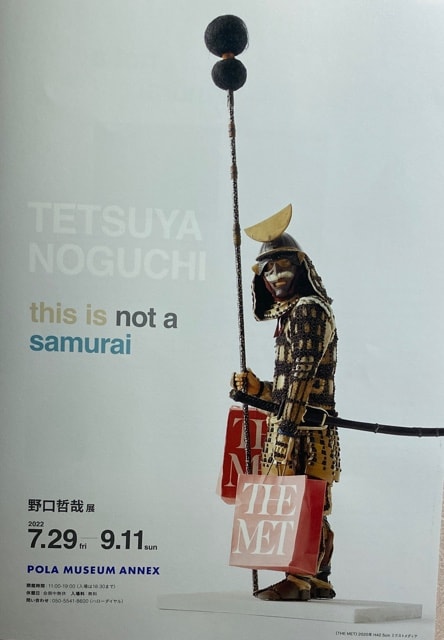
































6月5日。
2年3カ月ぶりに映画館に行きました。
友人に誘われて。
舞台挨拶があるのだそう。初体験。
阪本順治監督『冬薔薇』ふゆそうび


事故を起こして不遇の伊藤健太郎が主演。
阪本順治監督の映画は何本か観ています。
『魂萌え!』(07)、『北のカナリアたち』(12)、『団地』(16)、『一度も撃ってません』(20)。
『一度も撃ってません』は、石橋蓮司主演でした。
今回の映画、なんだか救いのない映画でしたが、役者さんが素晴らしい。
特に石橋蓮司です。
もう45年は見続けている名バイプレイヤーです。
舞台挨拶、そう言えば大昔、池袋文芸坐で原田芳雄を見たような気がしますが、今や忘却の彼方。なのでとっても面白かった。
救いがないと感じたし、歳をとるにつれ暴力シーンに耐えられなくなったので、観ているのは辛いと言えば辛い。
阪本順治監督は何を言いたかったのでしょう。
伊藤健太郎を主演として、ご自身が書き下ろしたオリジナルだそう。
子育て仲間の友人と会うのも2年4ヶ月ぶりでした。お互いの子どもたちは、学校も学年も違います。
地域の公民館で母と子向けのサークル活動で知り合って、36年。
映画はいつもひとりで観ていますが、こうして共に観て、鑑賞後の一献での語らいが、幸せでした。
















4月22日。
月に1度の美術館巡り。
今日は、朝倉彫塑館へ。
光が降り注ぐ。
屋上から下を睥睨する像が。。



































1月21日。