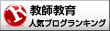■寝て食べて大きくなる赤ちゃん 「赤ちゃん」はなぜよく寝るのだろう? ヒントは動物界にあった。体が小さいハツカネズミは大きなゾウよりも何倍も眠り、食物は18倍も食べる(体重比)のだという。小さい動物の細胞ほどエネルギーが必要だからだ。赤ちゃんも同じ。体をどんどん大きくするため、よく寝てよく食べる…。「生物学」から見た“赤ちゃんの不思議”を紹介する。赤ちゃんって、しょっちゅう寝ていますね。生後数カ月の赤ちゃんなら、1日の3分の2は眠っています。なんであんなに寝ているのでしょう? 突然動物の話になりますが、ハツカネズミは13時間も眠ります。ゾウは3~4時間しか眠りません。小さなものほどよく眠る傾向がみられます。こんな傾向が生じるのには、動物がどれだけエネルギーを使って生きているかが関係していると私は考えています。 体は細胞からできており、細胞はエネルギーを必要とします。そのエネルギーを動物は食物から得ています。だから食べなければエネルギー不足になり、死ぬのです。 細胞は大きい動物のものでも小さい動物のものでも、見かけもサイズもそれほど変わりはありません。 ところがエネルギー使用量は大違いで、小さい動物の細胞ほど大量に使うのです。 だから、小さいものは体の割にはたくさん食べねばなりません。例えば、ハツカネズミは(体重当たりで比べると)ゾウの18倍も食べます。細胞がそれだけエネルギーを必要とするからです。子供は小さいけれど、よく食べますよね。「痩(や)せの大食い」もよく知られたことです。 エネルギーを使うとは、仕事をしているということです。 体の小さな動物の細胞は、より多くの仕事をしている、つまり活発に働いているのです。そして、そういうものほど長く眠るのです。よく働けばよく眠るわけです(ちなみに運動選手の睡眠時間は長いと聞いたことがあります)。 赤ちゃんの細胞は、母親の4倍ものエネルギーを使っています。極めて活発に仕事をしているのですね。 赤ちゃんの仕事とは、体をどんどん作って大きく育っていくこと。この、ものすごく大切な仕事を懸命に行っているのが赤ちゃんなのです。 だからこそ、よく眠る必要があるのでしょう。「寝る子は育つ」のです。 協力「NPO法人日本子守唄協会」
人間の赤ちゃんなぜ良く寝ているのか!本川達雄東京工業大学大学院生命理工学研究科生体システム学の本川達雄教授の科学的な根拠に基づくで良く理解出来たと思います。赤ちゃんの細胞は、母親の4倍ものエネルギーを使っています。極めて活発に仕事をしているので、細胞が活発に働き、体をどんどん作って大きく育って行っているということ、ものすごく大切な仕事を懸命に行っているのが赤ちゃんと言うことが分かりませんでしたね。これからは、若いお母さんもお父さんも赤ちゃんを見る目が違ってくるのではないでしょうか。日本では、昔から『良く食べて寝る子は、元気な子供に育つ』と言われています。
昔の人の医学的にも正しい言い伝えと言えます。
今のように医療設備も薬も整っていなかった昔からの先人の智恵をおろそかにしていけないと思いました。核家族化している今の日本で、赤ちゃん学を研究することは赤ちゃんへの正しい認識と育て方への一助となると思います。同志社大学にも2008年10月1日に、同志社大学に新しい研究センターとして赤ちゃん学研究センターが開設されました。
赤ちゃん学を少子化対策と育児ノイローゼも増え、子育への支援が重要な問題になっている今日の日本で取組まなければならない生きた研究分野と思います。
赤ちゃんが良く寝るのと同様、赤ちゃんは泣くのが商売と言われています。関西地方では昔から良く言われています。赤ちゃんは泣くことにより自分の感情や気持をお母さんや周囲の大人に発信しているのだと思いますが。今の科学の発達した現在でも医学的にも赤ちゃんのことが総て解明されているとは言えないのではないでしょうか。
今度は赤ちゃんの良く泣く事と意味も取上げて頂きたいと思います。子育ての為の母親学、生物科学の立場から解明、分析されるとなるほどと若いお母さんもお父さんも納得され、説得力が有ると思います。
子供は、良く遊んで、良く食べて、良く寝るが、元気な日本の子供達を育てる基本原則ではないでしょうか。

講演会・講習会
- 日本赤ちゃん学会第10回学術集会が、2010年6月12 日(土)13日(日)東京大学本郷キャンパス安田講堂で開催されます。(詳細)
- 近鉄文化サロン連携講座赤ちゃん学入門講座「赤ちゃんと楽しくつきあおう♪」2010年4月24日開講 (詳細 PDFファイル)で検索近鉄文化サロン阿倍野|トップページ近鉄文化サロン 阿倍野. 〒545-0052. 大阪府大阪市阿倍野区阿倍野筋2-1-40 www.d-kintetsu.co.jp/bunka-salon/<wbr></wbr>abeno/index.html
- センターの概要
同志社大学大学院心理学研究科赤ちゃん学研究センター紹介
教授 小 西 行 郎
2008年10月1日、同志社大学に新しい研究センターとして開所したのが赤ちゃん学研究センターです。 “赤ちゃん学”という名前はあまり聞きなれないかもしれませんが、小児医学や心理学のみならず、情報工学あるいは人工頭脳やロボット工学までの広い研究分野を融合し、 21世紀の始まりにふさわしい新しい学問分野の創設を目指したものです。さまざまな「子どもの心の問題」が社会問題化している現在、そうした問題の根本にある子どもの心と身体の発達とその関係について総合的に研究する必要があるとして、2001年「日本赤ちゃん学会」が設立され、多くの異種多様な分野の研究者が協力して、さまざまな成果が報告されてきています。本センターはそれを我が国で初めて実装に移したものと考えています。
まず研究としては
- 光トポグラフィーや多チャンネル脳波計などを用いて新生児から乳幼児までの脳機能計測を行う
- 視線計測装置を用いて乳幼児の認知行動の解析を行う
- 音楽の乳幼児や障害児の行動に及ぼす影響を解析する
- 発達障害の診断方法については現在精神科医によるDSM-IVという質問表を中心に行われているが、認知心理学実験をもとにした診断方法と小児神経学的診察を合わせた診断バッテリーを開発する、完成すればそれを実際の臨床の場で活用する
つぎにこうした研究を社会に還元するために、自治体やこうした事業に関心のある企業とも連携しながら育児相談や保育園、幼稚園や小学校の巡回相談などを行ってゆきたいと思っています。
現在少子化対策の重要な施策として育児支援士の養成や保育士、あるいは保育ママの資質の向上がうたわれていますが、赤ちゃん学研究の成果はこうした人たちの教育やレベルアップのために有効であるといわれており、すでに学会では大阪と東京で講座を開いています。本研究センターでもこうした講座を積極的に開講してゆきたいと考えています。
赤ちゃん学研究センターは、赤ちゃんをまるごと知るために異分野の研究者が研究をもて交流する場として、また赤ちゃんにその成果をお返しするために基礎研究と実際の現場とが交流する場として、その重要な機能を果たしてまいります。
 楽しそうにそろばんをはじく磯貝勇誠ちゃん=向日市
楽しそうにそろばんをはじく磯貝勇誠ちゃん=向日市