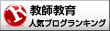5月18日15時31分配信 毎日新聞
 |
| 拡大写真 |
| 滋賀県日野町で駆除されたシカ肉を使ったカレー=近江八幡市上田町のCoCo壱番屋近江八幡サウスモール店で2010年5月17日 |
東近江五個荘店(東近江市)と近江八幡サウスモール店(近江八幡市)。いずれも日野町猟友会が町内で捕獲、解体した肉を使い、1食880円。県によると、シカは稲穂や野菜の新芽などを食い荒らし、08年度は県内で約4000万円の被害が出た。生息数は07年度の2万6300頭から年々増加し、12年度には4万4000頭に増える見込み。県は今年度、昨年度の倍の8500頭を駆除する方針。 一方、県内でCoCo壱番屋を10店経営する岡島洋介さん(46)は、鉄分を多く含み、高たんぱくで低脂肪のシカ肉に着目。今年1月、同町に新メニューを提供したいと持ちかけた。シカ肉はにおいや硬さが難点とされてきたが、圧力鍋でニンニクなどと煮込むことで克服した。売れ行き次第で扱う店舗を拡大するという。 岡島さんは「利益はほとんどないが、地域貢献のつもりです」と話している。店を訪れた藤沢直広町長(54)は「地元農家とカレー店、食べる人のみんなが喜ぶ三方良しの取り組み。これを機に消費を拡大させたい」と期待した。』
三方よしと現代企業 - 三方よしの原典
●三方よしを語る| 企業の社会的責任
●ミニ情報| 用語解説(近江商人関係・社会的責任関係)
●近江商人に学ぶ| 商法と理念 - 近江商人企業(塚喜商事株式会社・西川産業株式会社)
商取引においては、当事者の売り手と買い手だけでなく、その取引が社会全体の幸福につながるものでなければならないとう意味での、売り手よし、買い手よし、世間よしという「三方よし」の理念は、近江商人の経営理念に由来する。
旧国名を近江という現在の滋賀県に属する地域からは、江戸時代から明治期にわたって、近江商人と呼ばれる多くの大商人が次々に出現した。彼らは近江に本宅を構え、行商の初期には上方の商品と地方物産の有無を通じる持下(もちくだ)り商いに従事し、資産ができると要地に複数の出店を築き、産物廻しという持下り商いの大規模化した商法を出店間で実施して、さらに大きな富を蓄積した。近江商人という人々は、地元の近江を活動の場とするのではなく、近江国外で活躍し、原材料(地方物産)の移入と完成品(上方商品)の移出を手がけ、現在の日本の経済と経営を先取りするような先進的な商人達であった。
近江国外での他国行商を本務とした近江商人は、行商先の人々の間に信用という目に見えない財産を築いていかなければならなかった。持下り商いは、一回きりの売込みではなく、自分が見込んだ国や地域へ毎年出かけ、地縁や血縁もないところに得意先を開拓し、地盤を広げていかなければならないのである。
異境を行商してまわり、異国に開いた出店を発展させようとする近江商人にとっては、もともと何のゆかりもなかった人々から信頼を得ることが肝心であった。その他国商いのための心構えを説いた近江商人の教えが、現代では「三方よし」という言葉に集約して表現されるようになったのである。 「三方よし」の直接の原典となったのは、宝暦4(1754)年に70歳となった麻布商の中村治兵衛宗岸(そうがん)が15歳の養嗣子に認めた書置(かきおき)のなかの次の一節である。 たとへ他国へ商内に参り候ても、この商内物、この国の人一切の人々、心よく着申され候ようにと、自分の事に思わず、皆人よき様にと思い、高利望み申さずとかく天道のめぐみ次第と、ただその行く先の人を大切におもふべく候、それにては心安堵にて、身も息災、仏神の事、常々信心に致され候て、その国々へ入る時に、右の通りに心ざしをおこし申さるべく候事、第一に候
この条文は以下のように読み解くことができる。
他国へ持下り商いに出かけた場合は、持参した商品に自信をもって、その国のすべての人々に気持よく使ってもらうようにと心がけ、その取引が人々の役に立つことをひたすら願い、損得はその結果次第であると思い定めて、自分の利益だけを考えて一挙に高利を望むようなことをせず、なによりも行商先の人々の立場を尊重することを第一に心がけるべき である。欲心を抑え、心身ともに健康に恵まれるためには、日頃から神仏への信心を厚くしておくことが大切である。
「三方よし」の原典となったこの条文は、明治になってから井上政共編述『近江商人』のなかで、「他国へ行商するも、総て我事のみと思わず、その国一切の人を大切にして、私利を貪(むさぼ)ることなかれ、神仏のことは常に忘れざるよう致すべし」と、簡潔に要約されている。まさに「三方よし」の精神以上に、近江商人の到達した普遍的経営精神を示すものはないといってもよいであろう。
このような商行為の社会性を強調した近江商人は、宗岸だけではない。東本願寺の熱心な門徒であった初代小野善助は、80歳となった元文2(1737)年に遺言を書いている。そのなかで善助は、人間は人の情が分らなければどこにいても暮らし難いものであると考え、常に相手の身に良かれと心がけ、自分の奢(おご)りのためには一銭も使わず、無限の水さえ無駄にしないように始末しながら、北陸や東海地方を行商して、ついに奥州盛岡に開店できたと述べている。ここに流れている精神の重要なことは、強い信仰に裏打ちされた勤勉、始末という個人的要素だけではなく、世間への奉仕の精神が強調されている点である。
また、初代小林吟右衛門は安政元(1854)年に78歳で没する直前の述懐において、たとえ天秤棒(てんびんぼう)をかついだ小商人であっても、世の中の一員としての自覚をもち、不義理や迷惑をかけないように絶えず周囲や世間の人達のことを思いやりながら懸命に働けば、立派に一人前の商人として認められ、やがて相当の資産を築くことができるものである、と説いている。
商行為の基礎に、社会の一員という社会認識の重要性を強調する近江商人の到達した「三方よし」に代表される経営精神は、現代でも少しも古びてはいない。企業活動は、何らかの社会施設や自然環境を利用せざるをえないのであり、必然的に公的側面をともなわざるを得ない。その意味で「三方よし」は、企業は公なりという現代の企業認識とも明白なつながりをもった、長い歴史に培われた経営精神の精髄であるといえよう。
三方よし理念実践企業紹介
平成20年度
株式会社アオヤマエコシステム
大洋厨房株式会社
有限会社白浜荘
有限会社つるや
株式会社山久
株式会社住文
株式会社スポーツショップキムラ
廣瀬バルブ工業株式会社
平成19年度
カシロ産業株式会社
近畿精工株式会社
有限会社とも栄菓舗
喜楽鉱業株式会社
ティーアールエージャパン株式会社
株式会社水口テクノス
小林事務機株式会社
株式会社ミヤジマ
協和工業株式会社
藤野商事株式会社
株式会社葭本ダンボール
株式会社近江兄弟社
滋賀リコー株式会社
滋賀ダイハツ販売株式会社
平成18年度
ツジコー株式会社
有限会社豆藤
株式会社タオ
本間工業株式会社
滋賀特機株式会社
有限会社ブルーベリーフィールズ紀伊國屋
大津板紙株式会社
丸中醤油株式会社
株式会社鮎家
株式会社近江物産
甲西高周波工業株式会社
滋賀建機株式会社
株式会社湯元館
サンライズ出版株式会社
株式会社尾賀亀 平成17年度
有限会社池田牧場
株式会社井之商
株式会社岡村本家
株式会社平和堂
株式会社マルト
平成16年度
油藤商事株式会社
国友工業株式会社
株式会社黒壁
株式会社千成亭
田中建材株式会社
平成15年度
オーシャン貿易株式会社
新江州株式会社
株式会社たねや
株式会社比叡ゆば本舗ゆば八
株式会社日吉
近江商人企業
塚喜商事株式会社
西川産業株式会社
http://www18.ocn.ne.jp/~abc8181
プログランキングドツトネット http://blogranking.net/blogs/26928
日本プログ村 http://www.blogmura.com/profile/232300.html
人気プログランキング
http://parts.blog.with2.net/bp.php?id=627436:aLHKFCm5fBU"></